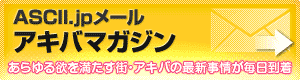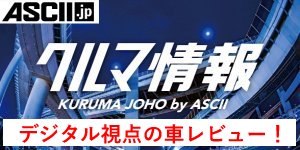●目標はFSB設定クロック150MHzだ!
今回、購入したAthlon-1.2GHzの限界クロックが1368MHzと判明した時点で一旦、原稿を区切り、第2回のお話に続けようと考えたのだが、どうしてもベストセッティングを導き出してそのパフォーマンスを試したくなった。そこで編集部に原稿締切日を少し延長してもらい検証作業をさらに進めることとした。
さて、このCPUを最大限活用できるセッティングを考えてみると、説明するまでもないが「最高FSB設定クロック」=「CPU限界クロック」÷「倍率」で見当がつけられる。そして、CPUの倍率設定ごと設定できるであろう、おおよそのFSB設定クロックを常識の範囲でいくつか割り出してテストすればいいわけだ。そのFSB設定クロックを【表3】に割り出してみた。セオリー通りならFSB設定クロックがより高いほどパフォーマンスは向上すると考えて良いだろう。しかしクロックが高くなるにしたがってマザーボードやメモリーを含めてシステム全体の不安定要素が増すわけで、頻繁にフリーズするシステムだとあまり感心できない。はたしてFSB設定クロックをどれだけ高くできるであろうか?「160MHzは欲張りだとしても150MHz辺りで使えるならベストだが」と目標は勝手に150MHzの9倍と決めた。
【表3】| 倍率 | FSB設定クロック | CPU内部クロック |
| 8.5倍 | 160MHz | 1360MHz |
| 9倍 | 150MHz | 1350MHz |
| 9.5倍 | 143MHz | 1358.5MHz |
| 10倍 | 136MHz | 1360MHz |
●K7T266 Proでの可能性を調査する
さっそく目標の150MHzを試したいところだが、ここはやはり【表3】にしたがいFSB設定クロックの低いセッティングから調べてみる。なお、以後4段階のテストを実施するが、このAthlonには全て限界クロック付近で動作してもらう。マザーボードやメモリー、ビデオカードなどは、先に実施したCPU限界クロックテストのシステム構成で臨んだ。加えてシステムのパフォーマンスは予備テストと同じスタイルで「計算タイム」と「ベンチマークスコアー」を計測し集計する。
まずは、K7T266 ProのBIOSセットアップからFSB設定クロックを136MHzとしCPU倍率は10倍(1360MHz)をセットした。一方、メモリーの設定は、SDRAM Frequence:HCLK(ホストクロックと同期)、SDRAM CAS Latency:2、SDRAM Bank Interleave:4-Way、SDRAM 1T Command:Enabledとしてみた。ただし、コア及びDDR電圧はAutoを選択し規定値のままで立ち上げた。再起動からの動作は順調でWindowsの起動を含めて全てのテストがトラブルなしで終えられた。その他にWebブラウザの動作や高解像度の画像ファイルをペーストしてみたが十分に安定していて余裕さえ感じられた。その時、筆者は少し意地悪なテストを思いついて実施した。それは、superπを419万桁でスタートさせておいて同時に3DMark2000を連続で2回走らせたのである。結果は、これまでのテスト結果を象徴するかのようにエラーもなくこの意地悪なテストを終了できた。
「それじゃ、次のFSB設定クロックではどうかな?」と今度は143MHzの9.5倍に設定を変更した。他のパラメータは、先の状態と同一で試してみる。「もしかするとメモリーに厳しいかも…」。もう、このクロックになるとシステムにしてみれば「冗談じゃないゼ! 」と言いたいところだろう。だが、筆者の心配を余所にこのFSB設定クロックでも所定のテストを順調にクリアーして完了した。「あれま、心配ご無用なのね」。そこで、先ほどの意地悪テストを再び出題してみた。ところがエラーの微塵も見せないのである。「この調子なら目標の150MHzは楽勝で動いてくれるのでは…」と好調なシステムに更なる試練としてFSB設定クロック150MHzの9倍をセットした。「たぶん、メモリーはアゴを出すだろうなぁ」とメモリーの設定画面を眺めながらセッティングを変更しようかこのままにしようかと戸惑った。「ものは試しに…」ダメならセッティングを緩めての再テストを覚悟して「変更なし」とした。