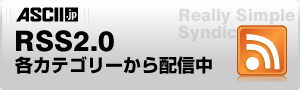PayPay以外は「副業」にすぎない
数年前から国や経済産業省などが音頭をとってきた「キャッシュレス推進」により、QRコードを使ったスマホ決済サービスが雨後の竹の子のように乱立した。しかし、経営に行き詰まったOrigamiはメルペイに救済され、そのメルペイはd払いとタッグを組んだ。また、送金に注力していたpringはグーグルに買収されるなど、すでに合従連衡が進みつつある。
筆者は、今後、QRコードを用いたスマホ決済サービスは4陣営に集約されるのではないかと見ている。その4陣営とはPayPay、d払い、au Pay、楽天ペイだ。簡単な話、「キャリアが提供しているスマホ決済サービスしか生き残らない」というわけだ。
そもそも、この4陣営は決済手数料で儲けようとはしていない。彼ら4陣営には「通信事業」や「通販事業」「金融事業」といった儲けるための本業が存在しており、スマホ決済サービスは「おまけ」であり「副業」に過ぎないのだ。
実は決済サービスに本気なのはPayPayぐらいなもの。他の3陣営が決済サービスに取り組む本当の理由は別のところにある。
PayPayは店舗向けサービスが儲けの中心に
今回、PayPayは手数料を1.6%に設定する一方で、「PayPayマイストア」というサービスを店舗向けに提供する。このサービスでは、加盟店に対して、顧客へのコミュニケーション機能を提供する。ストアページを作成でき、顧客に対してレビュー機能やクーポンなどのお得情報を発信できるようになるのだ。
どうやら、PayPayは、すでに飲食店向けには食べログが、美容室向けにはホットペッパービューティーが提供している店舗向けサービスを意識している感がある。店舗はこうしたサービスを導入すると、ユーザーに対して店の紹介をネットでできたり、予約を受け付けたり、クーポンを発行できたりする。
他社が5000円から数万円で設定している店舗向けサービス機能をPayPayは1980円で提供する。おそらく、PayPayはこの店舗向けサービスを機能強化し、月額利用料を上げる代わりに、決済手数料をゼロ円にする、という施策も今後、展開するのではないか。もはや、決済手数料で赤字さえ出なければよく、儲けの中心は店舗向けサービスにしていく可能性が考えられる。
一方、NTTドコモ、KDDI、楽天グループがスマホ決済サービスに取り組む理由はどこにあるのか。それは楽天ペイの優位性を聞けばよくわかる。
小林本部長は「楽天ポイントは年間約4700億のポイントが発行され、そのうち90%以上が消費されている」というのだ。

この連載の記事
-
第200回
トピックス
楽天モバイル 契約は絶好調だが、黒字化にはテコ入れが必要だ -
第199回
iPhone
アップル新型「iPad Pro」実物を見たら欲しくてたまらなくなった -
第198回
トピックス
ドコモ新社長は“経済圏”拡大より、ネットワーク品質とショップ網の再構築を最優先すべきだ -
第197回
トピックス
なぜソフトバンクやKDDIのネットワークは強いのか 「2.5GHz帯のTD-LTE」最強説 -
第196回
トピックス
F1の裏に“レノボ”あり 500TBのレースデータを高速処理 -
第195回
トピックス
格安スマホ、キャリアより「シンプルで安い」とふたたび注目 -
第194回
トピックス
中国スマホメーカー、日本への攻勢強める 格安折りたたみスマホで勝負 -
第193回
トピックス
ドコモが狙う“スマホの次“ iPhoneから「Vision」の時代へ -
第192回
トピックス
KDDI「povo」世界進出へ “黒子に徹する”新ビジネスとは -
第191回
トピックス
スマホ基地局を安くする ドコモとNECが世界展開する「オープンRAN」とは -
第190回
トピックス
KDDI対ソフトバンク “快適な5G”競争に本気出す - この連載の一覧へ