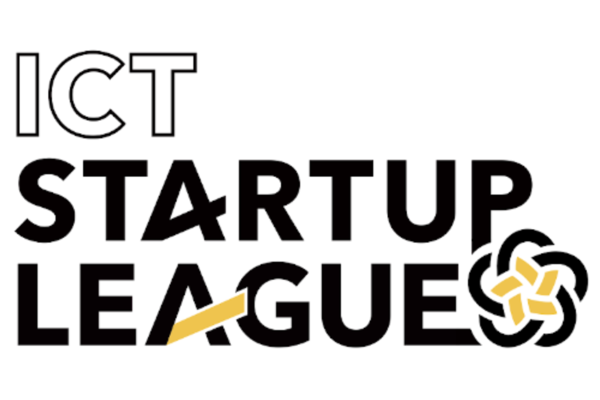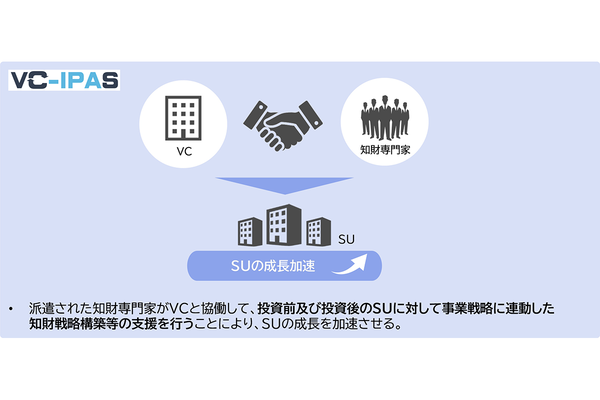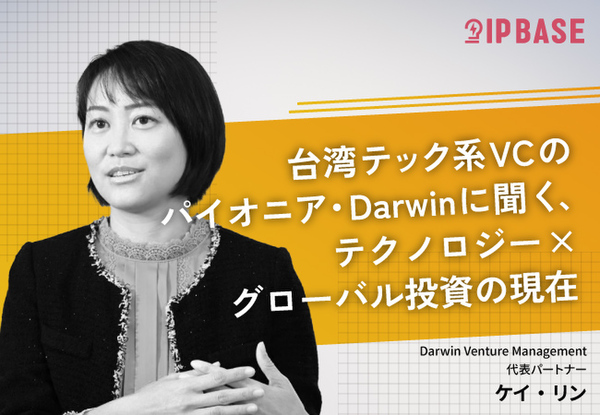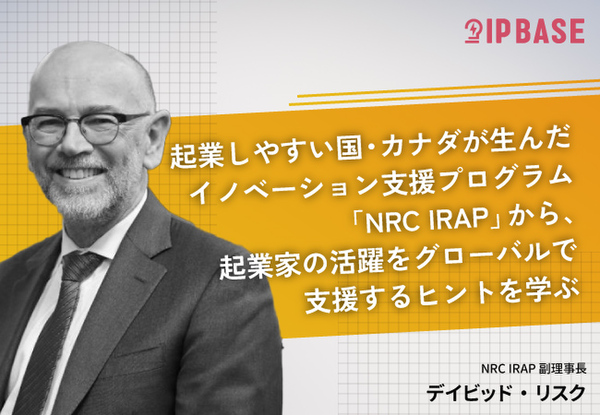AI、UIUX、ソフトウェア――スタートアップのビジネスアイデアを守るには?
「ビジネスモデルも特許になる スタートアップの知財戦略がわかる公開Q&A by IP BASE in 新潟」レポート
提供: IP BASE/特許庁
1 2
新潟県スタートアップによる公開知財相談Q&A
後半は、新潟県で起業したスタートアップの知財に関する質問に押谷 昌宗氏が回答する公開知財相談会を実施した。
1人目の相談者は、スマートスピーカーや生成AIを使った宿泊施設向け業務支援サービス「Hospitalia」を展開するTradFit株式会社代表取締役 戸田 良樹氏。
Q. 特許の優先順位はどうやって決めたらいい?
最初の質問は「特許にするべき内容と優先順位について」。押谷氏は、「外から見えるかどうかが重要。ソフトウェアがどのようなアルゴリズムを使っているのかはわからなくても、UIは誰でもわかる。外部から見て他社が模倣しているかどうかを検証できるものの優先度が高い。ただし、特許を出願すると情報が漏れてしまうので、キャッチアップされるまでの期間が長いものはノウハウとして秘匿するといい。とはいえ、ノウハウとして秘匿してもエンジニアが転職して他社に使われるリスクはある。転職が多い業界の場合は、外から見えにくいものも出願しておいたほうがいいケースもある」と答えた。
次の質問は、「コストを抑えながら、効率よく外国出願や周辺特許で特許網を築くには」。
回答として、「特許の手数料は、特許庁の支援制度や自治体の補助金などをうまく活用。専門家への依頼は、安すぎるところは避けたほうがいい。外国出願には、翻訳費用と現地の専門家のエージェント費用が発生する。審査ごとに費用がかかり、欧米は3~5回のやり取りが発生するのは当たり前。最初の出願で各国制度に精通していない弁理士に依頼すると、なかなか審査を通らず、かえって費用がかかる可能性がある。ベースの部分をしっかりお金をかけておくことが大事」とアドバイスした。
Q. AIを使ったレコメンドサービスの特許は取れる?
2人目の質問者は、新たなお酒に出会える日本酒サービス「Sakeai」、小容量の日本酒の定期便サービス「SakeaiBox」、ハイエンド日本酒ブランド「SAKE NOVA」を展開する株式会社サケアイ代表取締役社長の新山 大地氏。
新山氏は、これまで特許についてまったく考えていなかったという。そこで「日本酒のレコメンドアプリや日本酒の販売でも特許が取れるのだろうか」と相談。
押谷氏は、「AIを用いたレコメンドの手法は、アマゾンやZOZOの例が参考になる。ZOZOは、身体計測のZOZOスーツやパーソナルカラー診断ができるZOZOGLASSなどハードウェアについても出願している。AI特許は大きく2つあり、AIのアルゴリズムに関する特許と、AIに今までにないデータをインプットして新たな価値を生み出す、という仕組みに関する特許。AIでユーザーの嗜好を学習して日本酒を送るサービスは、後者にあたる。インプット→処理→アウトプットの一連の流れを押さえれば権利化できる可能性がある」と説明した。
Q. 飲料・酒に関する特許の事例は?
次の質問は「来年は自社でお酒を造ることを考えている。製造に関する特許の事例が知りたい」。
押谷氏の答えは「コカ・コーラが長年レシピを秘匿しているように、飲料の製造方法はあまり特許に向いていない。一方で、日本ではサントリーがトマトジュースの製造方法を特許にしている。大手企業が競合であれば、相対的に特許を出す価値は高くなるが、製造工程が外から見られる可能性は低いので基本的には秘匿したほうがいい」とのこと。
Q. 特許出願すると技術情報が開示されるのが心配
最後に、水耕栽培と魚の養殖を掛け合わせた次世代の循環型農業「アクアポニックス」を手掛ける株式会社プラントフォーム 代表取締役CEOの山本 祐二氏が登壇した。
山本氏の相談は、「特許を出願することによって公開されるのがデメリットに感じられる。どのように考えて特許戦略を進めればいいのか」。
押谷氏は、「特許は当業者からみて一定の再現性を開示するものでなければ登録はされないが、特許情報だけで再現できるかといえば、実はそうでもない。例えば、中村修二氏は青色ダイオードに関する特許を出願していたが、ほかの科学者はなかなか再現できなかった。つまり、特許情報には技術情報およびノウハウが100%含まれるものではなく、コアな部分を隠したまま登録することは可能」と説明する。
ただし、農業のように物理的な手法や技術は公開すると容易に模倣できてしまう。押谷氏は「模倣しやすい技術は、特許で公開せずとも、生産現場の視察などで真似されるリスクはある。ケースバイケースだが、模倣されやすい技術ほど出願する、というのもひとつの考え方」と話す。生産工程で他社の特許技術が必要になるケースもあるので、クロスライセンス等に使えるように特許を押さえておくのも戦略のひとつだ。
Q. 専任の弁理士を入れるタイミングは?
最後の質問は、「専任の弁理士を入れるタイミング」。
「ディープテック分野では創業初期から知財担当者を採用しているスタートアップもあるが、一般的には社員が100人を超えたあたりから採用するのが妥当。創業期は外部の専門家を顧問契約しつつ、外部とのつなぎ役として法務部や役員の兼務でいいので担当者を置いておくといいと思います」とアドバイスした。
1 2