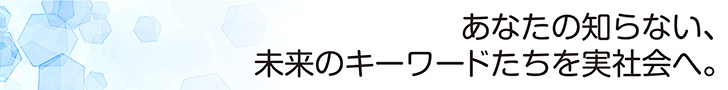生物多様性の保全をビジネスとして成立させたバイオーム
釣りと熱帯雨林が原体験
──バイオームの藤木さんは子どものころから生き物に興味があったのですか?
バ:僕自身は大阪市内出身で、特別に自然豊かなエリアで育ったわけではないんですよ。ただ、小学生のころは毎日のように近くの川や池で釣りをしていて、生態系に興味をもったのがちょうどその時期でした。ブルーギルみたいな外来魚が釣れるようになって、在来のフナやドジョウがどんどんいなくなっていることを強く実感しました。生態系というのはどんどんくずれているんだなということを現場で見て、怖いな、という感覚を持ち、なんとかしたいと思うようになりました。そこで高校生の頃から生態系やその保全の世界に進みたいと考えるようになり、京都大学農学部に進み、研究室に入ったんです。
──それが原体験というわけですね。
バ:それも原体験ですし、大学に入ってから研究で熱帯雨林に行ったこともありました。ボルネオ島の奥の奥まで入って、キャンプ生活をしながら生物調査をずっとしていたんです。熱帯雨林が伐採され、生態系がすごい勢いでなくなっていく現場をずっと見ていた。そのときの気持ちも原体験のひとつです。
──それで「自分がやらないといけない」と思ったわけですね。
バ:はい、時間がないなと思いました。
──都会に住んでいると自然に触れる機会がなくて、釣りやフィールドワークで、現場に行かないとわからないものがあります。バイオームも実際に見つけたものを写真に撮るというのは、子どもにとってもいいアプリだと思います。
バ:五感を使うことについては強く意識しています。僕が研究者だったころ、生態学は現場に行って五感を使って埋もれているアイデアを拾いあげていくことだと指導教授が口をすっぱくして言っていました。その感覚をアプリで表現したいと思ってます。
──イノラボの藤木さんはいかがですか?
イ:私の生まれは福岡県南部・筑後地方にある柳川市というところですが、柳川市は水の都と言われていています。もともとは海だったらしいのですが、陸地化して、そのときに掘っても真水を得られない地形のため、掘割を作り、水門で水を調整することで、上手に水を活用している地域でした。水田も多く、そこにいるオタマジャクシやタガメやゲンゴロウなどを観察できる環境で育ってきたんです。就職と同時に上京して、比較的自然と縁遠い生活を送ってきたわけですが、イノラボに入り、いろんな社会課題に取り組ませていただく中で、私の原体験に密接な研究をテーマにしているのかもしれない、と思ってます。
──イノラボでは里地里山、都市農園などにも注目されていますよね。
イ:それは個人的な関心が強いという点があるかもしれませんが……里地里山は素晴らしいと思っていますが、一方で人の手を必要とするため、後継者不足で無管理な状態になってしまっている場所があるという現状があります。そうすると、山のイノシシが人の生活する環境に降りてきて農作物を荒らしてしまったりする。大事なのは「自然っていいよね、だから大事にしましょう」で終わらせるのではなく、自然の怖さを理解し、人間と動物がいかにいい意味での緊張関係を持って、共生できる環境を作っていくことではないかと考えています。
──バイオームも土地開発などに意見する立場にあるのでしょうか?
バ:とてもやりたいところですね。現状は意見をする立場ではないですが、どう開発すればいいかを考えるためのデータは絶対に必要なので、それを提供して、自然環境の保全と折り合いをつけてもらうということはやっていきたいです。
──開発の際に、環境アセスメントは必ず入ってきますよね。
バ:環境アセスメントに生物の項目はよく入っていて、希少種がいないかということも見ているはずですが、限界があったり、費用がかさんだりという問題があると思います。そこで事前調査データがあると、さらに効率よくできるんじゃないかと。