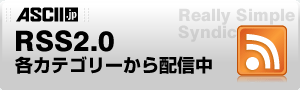“Enterprise 2.0”とは、ハーバード・ビジネス・スクールのアンドリュー・マカフィー教授が提唱している概念であり、Web 2.0の世界で一般的になっているブログ、SNSなどのいわゆるソーシャル・ソフトウェアを企業内で活用することを意味する。
ここで、用語の定義について確認しておこう。一部のメディアでは、Web 2.0的なあらゆる要素(例えば、マッシュアップなど)を企業内で活用することを、Enterprise 2.0と呼んでいるようだが、これはマカフィー教授のもともとの定義よりも範囲が広い。本コラムでは、マカフィー教授の定義を尊重し、比較的狭い意味でEnterprise 2.0という用語を使用することとしたい。
なお、マカフィー教授は自身のブログを公開しており、定期的に更新している。ビジネス・スクールの教授の中では、かなりITの現場感があり、アカデミックな議論にあまり興味がないIT実務家の方も楽しめる内容であると思う。英文ではあるがご一読をおすすめしたい。
Enterprise 2.0の概念を示す“SLATESコンセプト”
マカフィー教授はEnteprise 2.0の概念をSLATESという頭文字で表している。
(参考:Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration, MIT Sloan Management Review Spring 2006)。
S(Search):
検索エンジンで必要なコンテンツをサーチすることである。自明な機能ではあるがユーザーにとって真に重要な情報を適切に提示できる検索エンジンの構築するためには。まだ多くの解決すべき課題があるだろう。
L(Link):
これも自明だろう。ユーザーが重要なコンテンツに対してリンクを貼れるようにすることである。インターネットの世界では一般的だが、企業内においてはあまり一般的とは言えなかった。
A(Authoring):
ユーザー自身が自由にコンテンツを作成し、公開できるようにすることである。具体的には、ブログやSNSが使用されることになるだろう。多くのユーザーから共用されるコンテンツについてはWikiの活用が有効なケースもあるだろう。
T(Tag):
ユーザー自身が、コンテンツに対して分類情報を付加することである。たとえば、“役に立つ”“必読”などのタグを付加することが考えられる。多くのユーザーがタグ付けを行なうことで自然発生的にコンテンツの分類が行なわれることになる。いわゆる、“フォークソノミー”(folksonomy)という考え方だ。管理部門が行う従来型のトップダウンの分類(taxonomy)ではなく、人々(folk)によるボトムアップ型の分類を行っていこうという考え方である。
E(Extension):
ユーザーのタグ情報をシステムがパターン化/カテゴリー化し、コンテンツに新たな価値を付け加えることである。Amazonのリコメンデーション・エンジン(「この商品を買った方は以下の商品も買っています」)と同様に、ユーザーの情報検索やタグ付けのパターンに応じて、そのユーザーにとって重要性が高いと思われる情報をシステムが自動的に判別し、推奨を行なってくれるわけである。
S(Signal):
ユーザーがコンテンツをその都度見に行くのではなく、重要な情報が更新された時にシステムが自動的に通知してくれることである。かつて話題になった“PUSH”コンピューティングにも類似している。具体的にはRSSにより実現されることが多いだろう。
SLATESは、まさに一般ユーザーがインターネットの世界で行なっている典型的な情報共有のパターンである。このような自由な情報共有が有効であるのは、少なくともインターネットの世界では明らかだ。同じことを企業内でもやってみようというのがEnterprise 2.0のポイントだ。
概念はわかりやすいが現実には?
Enterprise 2.0の概念はわかりやすく、すでに情報源としてのウェブを使いこなしているものには自明とも言えるものだ。しかし、それを実際に企業内で実行し、具体的な効果を上げることは容易ではないだろう。マカフィー教授もこの点は認めており、Enterprise 2.0の実現のためにさまざまな障壁があることを認識している。そして、その多くはテクノロジー的なものではなく、企業文化的なものである。
実際、企業内でブログやSNSを活用するために導入したはよいが、ほとんど活用されずに閑古鳥化しているケースは多い。次回では、そのような障壁をどのように克服していくべきかについて考えていくことにしよう。
筆者紹介-栗原潔

(株)テックバイザージェイピー代表、弁理士。日本IBM、ガートナージャパンを経て2005年より独立。先進ITと知財を中心としたコンサルティング業務に従事している。東京大学工学部卒、米MIT計算機科学科修士課程修了。主な訳書に『ライフサイクル・イノベーション』(ジェフリー・ムーア著、翔泳社刊)がある。

この連載の記事
-
最終回
トピックス
エンタープライズサーチの真の価値を探る(9)――多様な領域に広がるサーチの可能性 -
第18回
トピックス
エンタープライズサーチの真の価値を探る(8)――「意図のデータベース」 -
第17回
トピックス
エンタープライズサーチの真の価値を探る(7)――バーチカルサーチの可能性 -
第16回
トピックス
エンタープライズサーチの真の価値を探る(6)――真の意味のマルチメディアサーチの可能性 -
第15回
トピックス
エンタープライズサーチの真の価値を探る(5)――サーチとBIとのもうひとつの関係 -
第14回
トピックス
エンタープライズサーチの真の価値を探る(4)――結構親密なサーチとBIの関係 -
第13回
トピックス
エンタープライズサーチの真の価値を探る(3)――柔軟性が求められるランキングアルゴリズムの実装 -
第12回
トピックス
エンタープライズサーチの真の価値を探る(2)――ポータルとしてのサーチ -
第11回
トピックス
エンタープライズサーチの真の価値を探る(1) -
第10回
トピックス
いまあえてWeb 2.0を分析する(10)――企業内Web 2.0と切っても切れないエンタープライズサーチ -
第9回
トピックス
いまあえてWeb 2.0を分析する(9)――Web 2.0系テクノロジーはどこが優れているのか? - この連載の一覧へ