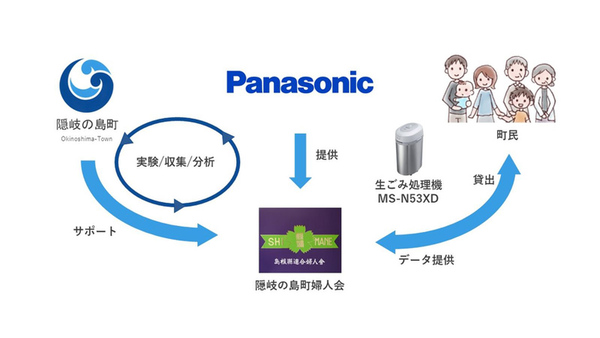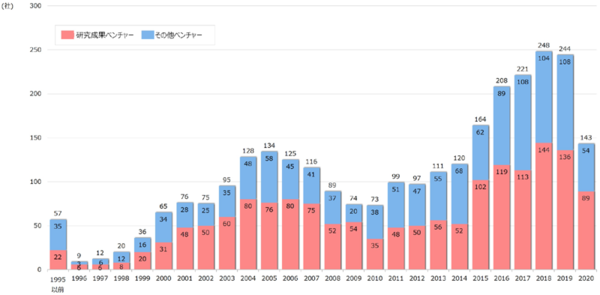再エネで要注目。特許から見るリソースアグリゲーションの動向
国内特許の紹介 1:技術の変遷
リソースアグリゲーションに関する技術開発の変遷として、黎明期から出願をしている東芝グループの特許について、出願時期の異なる以下の3つの特許を紹介します。
①特公昭60-52649
発明の名称 デマンドコントロールシステムの生産負荷監視制御方式
出願日 1980/12/15
出願人 東京電力株式会社
東京芝浦電気株式会社(現、東芝)
大崎電気工業株式会社
特許請求の範囲(メインクレーム)
デマンドコントロール装置からの減少指令信号又は増加指令信号と調整量信号とが入力する毎に、生産負荷別の現在値を監視し、現在値と調整量とから減少又は増加すべき制御量を生産負荷毎に演算し、該制御量を生産負荷の絶対量に換算し、絶対量信号を生産負荷に対して出力して、生産負荷を制御し、制御を行った所定時間後、生産負荷別の現在値を監視するようにしたデマンドコントロールシステムの生産負荷監視制御方式。
課題・目的
デマンドコントロール装置からの信号に応じて、生産負荷を迅速に且つきめ細かに監視制御することができるデマンドコントロールシステムの生産負荷監視制御方式を提供する。
図面
(解説)
従来、空調装置や照明などのオンオフの制御ができる環境設備にしたデマンドコントロールの適用が難しかったところ、減少指令および増加指令の入力ごとに生産負荷別の現在値を演算して制御を行うことで、個々の清算負荷について制御された結果が迅速に得られ、きめ細やかな監視制御を可能としています。
40年以上前の出願であり、この分野の基本発明となる特許と考えられます。 実際、14件の後願の審査において引用されており、本件を第1世代とした引用マップは150件以上の第5世代まで続いています。
②特許第4131905号
発明の名称 電力取引システム
出願日 2001/2/26
出願人 株式会社東芝
特許請求の範囲(メインクレーム)
配電業者から複数の需要家に電力を送配電する電力線と、この電力線の受電端で需要家が電力を消費する電力消費機器と、この電力消費機器に対する消費電力を需要家が制御する消費電力制御装置と、送配電業者と需要家とを双方向に通信可能な双方向通信装置と、送配電業者から双方向通信装置を介して需要家に電力消費要求を提案する手段と、需要家の状況により電力消費要求の受入可能電力を双方向通信装置を介して送配電業者に応札する手段と、送配電業者から需要家に余剰電力を消費するように依頼する手段とを備えたことを特徴とする電力取引システム。
課題・目的
電力料金は、発電に必要なコストと、送配電に必要なコストなどから算定されるべきであり、電力の蓄積が不可能であること、発電コストの低い大型汽力の出力変化に長時間必要なことから、需要電力の予測が外れた場合のリスクをコストとして計上している。
さらに、送配電業者の理由により、一方的に需要家の電力消費機器を制御することは不合理である。そのため、需要家での電力消費を制限したことに対する報奨を、電気料金の割引として行っているが、その金額が必ずしも妥当でなかった。
本発明は、上述した事情を考慮してなされたもので、送配電業者の設備費や無駄な燃料消費を抑え、安価に電力を供給することができるとともに、電力系統の安定化を図り、設備の負荷率を機器の最大効率近傍に設定可能な電力取引システムおよびその方法を提供することを目的とする。
図面
(解説)
この発明では、双方向通信により複数の需要家に電力抑制を送配電業者が提案し、電力を抑制可能な需要家が削減可能な電力とその時間を応札することにより、電力不足による送配電系統の不安定を回避します。また、送配電業者は余剰の発電設備または発電業者との買電契約を抑制することができるので、設備費や無駄な燃料消費が抑えられ、安価に電力を供給することができます。
こちらは、2000年代初頭の出願であり、先ほどの①の特許と比べると、送配電業者と需要家との間での電気の需給のバランスに応答して、供給量や消費量を調整するという、電力取引を想定したより具体的な内容となっています。
この出願は、24件の後願の審査において引用されており、電力取引における基本発明と考えられます。
③特許第7013348号
発明の名称 余剰電力取引装置およびプログラム
出願日 2018/8/31
出願人 株式会社東芝
東芝エネルギーシステムズ株式会社
特許請求の範囲 (メインクレーム)
余剰電力の買電を希望する第1需要家が電力会社から購入する単位電力量当たり料金である第1電気料金、および余剰電力の売電を希望する第2需要家が売電する余剰電力の単位電力量当たりの料金である第2電気料金を取得し、第2需要家と、当該第2需要家の第2電気料金より高い第1電気料金の第1需要家とを紐付ける需要家情報、および第2需要家の第2電気料金を電力会社の端末に通知する通知部、を備える余剰電力取引装置。
課題・目的
電力 (電流) は、電圧の高い所から電圧に低い所から流れる性質を有し、需要家間で送りたい場所に余剰電力を送電することは難しい。そのため、現状においては、需要家間において電力を売買することはできず、小売電気事業者を経由して需要家間で仮想的に電力の売買を成立させ、その後、仮想的に売買した電力の料金を事後精算とするシステムが必要となる。また、電力は、色づけされていないため、ある需要家の余剰電力がどの需要家に供給されたかを特定することができず、スマートメータ等のメータ値のみを使って事後精算することが困難である。 また、需要家間での余剰電力の取引が活性化した際に、余剰電力の買い取りの希望価格が同等の希望者 (需要家) が複数存在する場合における当該希望者に対する優先度の付け方も課題となる。
図面
(解説)
この発明は、FIT制度(電力会社による固定価格での買い取り制度)の終了による需要家間での自由競争に基づいた余剰電力の取引に備えたシステムとなっています。 すなわち、この発明では、需要家間での余剰電力の売買を仮想的に実現することで、需要家間での余剰電力の売買における事後精算を可能としています。2022年から開始されたFIP制度のもと、実装される技術と考えられます。