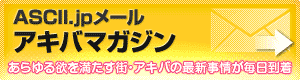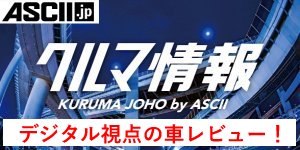まつもとあつしの「メディア維新を行く」 第65回
1週間で15カット上げる人材を育てるために必要なこと
ついにアニメスタジオでも働き方改革が始まった!~P.A.WORKS堀川社長に聞く〈前編〉
2019年12月26日 12時00分更新
ベテランの後輩指導が無駄にならない環境づくり
「若手を育てれば、いずれ自分がラクになる」
―― もしかしたら、ある人は描く時間よりも指導の時間が長くなるかもしれないけれど、それによって若手の描く効率が上がれば、全体としてはOKである、と。
堀川 そうです。うちの場合、クリエイターは実作業時間以外にも、トライアル班のミーティングや指導者ミーティング、養成所の講義の仕込み、カリキュラムの作成と、時間をとられることが多い。彼らは中長期視点で組織を強くするために時間を割いてくれているんです。
なので、たぶん業界の一線で活躍するアニメーターは、TVシリーズの原画なら10週間で60カット以上上げると思いますが、「今は強い組織作りのために、作画以外のことに時間を割いてくれているので、この目標数で構わない」と皆には話しています。
作画監督や演出の生産性を上げる最も効果的な方法は、原画マンの力量を底上げすることです。上に立つ人間が若手を育てれば演出や作監のチェックがスムーズに進み、いずれ自分がラクになりますよね。大事なのは、その考えと成果が継承されていくこと。離職率が高くて、「あそこまで親身になって、オレの時間を割いて教えたのに一人前になった途端、辞めていった!」ということでは、一線を退いたベテランくらいしか教える気にはならないでしょう。
―― せっかく教えてもどうせ辞めていっちゃうんだろうな、と。
堀川 その無力感との戦いは常にあると思います。
―― なるほど。私も企業さんの働き方改革のWebサイトを手伝っていたりするんですけど、P.A.WORKSさんのトライアルは本当に働き方改革そのものですね。しかもITを使って云々ではなく、言葉は難しいですが生臭いというか、人の気持ちの部分が絡んでくるところに切り込んでいる。
堀川 そうですね……昨今は『なつぞら』のようにみんなが意見をぶつけ合う場が作れないんです。そういう体験がないし、場もない。活発な現場を作るには、まずそんな機会を作ることが必要だと思います。じつはトライアルの1期は高望みをしてしまったんです。どうやって成果物の物量を上げていくかと並行して、どうしたら上手くなるか/技能の質を上げる定性目標も立てながらやろうとしたのですが、後者は上手くいきませんでした。
―― 技能についても数値化しようとした?
堀川 評価指標を作り、「これが数値化できたら上手くなった」ということを月に1回見てみようとしました。でも半年続けてみて、まだそれをやるレベルじゃないなと思ったんです。原画の技術は数ヵ月くらいで急激に上手くなるものじゃないんです。
―― 数値化とは、たとえば描いた絵に作監の修正が入る割合とか?
堀川 ええ、どれくらいの割合で直しが入るか、などですね。しかし、ちゃんとスケジュールが確保されていないなかでそれをやっても、「そんなもので評価されたくない」とか、色々思うところが出てくるじゃないですか。
そこで、しっかり作画スケジュールを確保した作品であらためて見ていきたいんですが、生産性向上のうちの定量目標と定性目標は分けてやってみるつもりです。
「スタッフみんなで見るラッシュチェック」の
復活が技能向上のカギ!?
堀川 やりがいについて、みんなにシンプルなアンケートを取ったんです。それであらためて確認できたのですが、クリエイターは自分で描いたものが褒められると嬉しいという、当たり前の事実があるにもかかわらず、制作工程中にその機会がほとんどないんです。演出部などではあるんですけど。
自分が描いたものを他者がどう見ているのか、どう評されているのか……今の作り方ではそれを知る機会がないんだ、とクリエイション部の部長から言われて気づきました。
僕が業界に入った頃は「ラッシュチェック」というものがあって、そこではスタッフが大勢集まり、監督が中心になってフィルムを回しながらリテイク出しをする。それをみんながピリピリしながら見るんです。
でもフィルムが無くなってムービーがデータになってからは、「各自がデータで確認してください」が主流になっているので、スタッフが集まって見る機会がない。だからその機会を作ろうと思っています。編集後でも納品後でもいいんですけど、作品1本分のフィルムがつながったらやりたい。原撮/線撮=原画をそのまま撮ったムービーがあれば完成映像と比較したい。
5人の原画チームだったら、出席者はその5人と作監だけ。リテイク出しではなく、他者のカットを評価する。これをやることで、まず自分のカットが他者からどう見られているかがわかる。そしてもうひとつ勉強になるのは、他者のカットをどう評価するか。上手い人はこの技術的視点を沢山持っているんです。若手は「上手くなりたい」とか「誰々みたいになりたいなぁ」という漠然としたものはあるんですが、なぜ「誰々みたいになりたい」と思うのか。
たとえば中村豊さんというすごくアクションが上手い原画マンがいます。みんな「中村さんみたいな原画が描けたらいい」と言う。彼の原画はたしかにカッコいいけれど、なぜ自分はあれを生理的にカッコいいと思うのか、技術的な視点で探究する能力が弱いんですよ。
そのカットを「カッコいいね!」っていうレベルの評価ではなく、プロのアニメーターとして、「ここの体重移動が」「アウトラインの処理が」「カメラワークが」「カメラのレンズが」など、技術的な視点で他者の技術的特徴を語る習慣を作りたいんです。「上手い原画マンはそこを意識して描いているのか!」と、経験も知識もない若い原画マンが刺激を受ける機会になると思います。
―― ある意味では失われてしまった能力かもしれません。『なつぞら』の頃は皆持っていたのかもしれませんが。
堀川 昔はそれを語れる制作現場の環境が多かったのかもしれません。今も語れる人はいますが、それができる人は日常的に分析しているし、勉強もする人です。つまり、できる人は放っておいてもできるようになる。しかし、それでは業界クリエイターの人材不足は全く解消されないので、まず先輩がプロの職人としての技術的視点を提供し、若手が学んで継承するための場を作ってみようと思います。
おそらく3年とか5年かけてようやく技術論が活発に、フランクに交わされる社内文化が醸成していくものだと思うので、やはり人を育てるということは中長期スパンで計画的に導入しないとできません。「この作品を作る間だけはやる」というのでは人は育たないんですよ。

この連載の記事
-
第102回
ビジネス
70歳以上の伝説級アニメーターが集結! かつての『ドラえもん』チーム中心に木上益治さんの遺作をアニメ化 -
第101回
ビジネス
アニメーター木上益治さんの遺作絵本が35年の時を経てアニメになるまで -
第100回
ビジネス
『THE FIRST SLAM DUNK』で契約トラブルは一切なし! アニメスタジオはリーガルテック導入で契約を武器にする -
第99回
ビジネス
『THE FIRST SLAM DUNK』を手掛けたダンデライオン代表が語る「契約データベース」をアニメスタジオで導入した理由 -
第98回
ビジネス
生成AIはいずれ創造性を獲得する。そのときクリエイターに価値はある? -
第97回
ビジネス
生成AIへの違和感と私たちはどう向き合うべき? AI倫理の基本書の訳者はこう考える -
第96回
ビジネス
AIとWeb3が日本の音楽業界を次世代に進化させる -
第95回
ビジネス
なぜ日本の音楽業界は(海外のように)ストリーミングでV字回復しないのか? -
第94回
ビジネス
縦読みマンガにはノベルゲーム的な楽しさがある――ジャンプTOON 浅田統括編集長に聞いた -
第93回
ビジネス
縦読みマンガにジャンプが見いだした勝機――ジャンプTOON 浅田統括編集長が語る -
第92回
ビジネス
深刻なアニメの原画マン不足「100人に声をかけて1人確保がやっと」 - この連載の一覧へ