権利が保障されすぎている業界はイノベーションが起きにくい
高橋 そもそも論になってしまいますが、創造や創作という行為が果たして本当に無からなにかを生み出すものなのかという点に関しては相当疑問符がつくところですよね。前回話に出たレヴィ・ストロースの「ブリコーラジュ」ではないですが、僕の本職である「編集」なんてまさに複数のクリエイティブ素材をいかにリミックスするかという仕事なわけで、音楽のDJにしても服のスタイリストにしてもとても編集的なクリエイションです。
インターネット上ではそうした創造性の双方向の触発は禁止のしようがありませんから、著作権絡みの問題は今後も増えることこそあれ、決して減ることはないんでしょうね。
水野 結局のところいまという時代は、デジタルの世界における現代的な創造/創作の実像と、法律が概念的に想定している創造/創作の虚像とが乖離してしまっている状況なのではないでしょうか。もちろん著作権法も時代状況に合わせてそれなりにカスタマイズされてはいますけれども、おおむね昔ながらのオリジナル神話の上に成り立っている。
でも、そもそもの昔から創造性や創作性というのは共時的にも通時的にも誰かの作品に影響を受けているはずなんですよ。どんな表現活動にもそうした影響関係はかならず存在していて、そのプロセスの部分をきちんと斟酌(しんしゃく)できないと、現状のアーティストやクリエイターの表現活動にはまったく適合できないでしょうね。
さらに言えば、「アーティスト」や「クリエイター」という言葉を使うと問題を矮小化してしまうけど、これはネット社会に生きる一般人にも、ビジネスにとっても重要な視点です。
高橋 いまおっしゃった「昔から創造性や創作性というのは共時的にも通時的にも誰かの作品に影響を受けている」というのはまさにその通りだと思っていて、それがインターネットによって表面化しただけの話だと思っています。
水野 インターネットによって相互の影響関係が可視化されて、同時に、そうしたプロセスを背景とするクリエイションが爆発的に増えたというのが現在の状況ですよね。
高橋 それこそ江戸時代の人形浄瑠璃や歌舞伎なんて改作だらけですからね。近松門左衛門の作品なんてどれだけの二次創作を生み出したことか……。しかも、当人への許諾なんてなしに(笑)。
水野 これは最近始まった新しい議論ですけれども、“知的財産権はイノベーションのためにある”という根本的な大前提が疑問視されているんです。つまり、権利がガチガチに保障されている業界のほうがイノベーションが起きているかと問われるとそうでもないぞ、権利保護がない分野でも全然変わらずイノベーションが起きているんじゃないか、という説があるんですよね。
当然、既得権益のためには一定の成果を生んでいるんでしょうけれども、後続の若手の表現の制約にしかならなかったり、その業界の市場規模が広がるというような未来につながっていなかったり、全然いい影響をもたらしていない。ある程度のパクりパクられという循環が許容されているおおらかな環境のほうが、市場規模が広がり全体としては経済的にも好結果を生む可能性が高いのではないか、ということです。
パクられたからと言って誰も創造や創作をやめたりしないですし、イノベーションが沈滞してしまうことはない。ここらへんは「パクリ経済――コピーはイノベーションを刺激する」(みすず書房刊)という本が参考になると思います。
| Image from Amazon.co.jp |
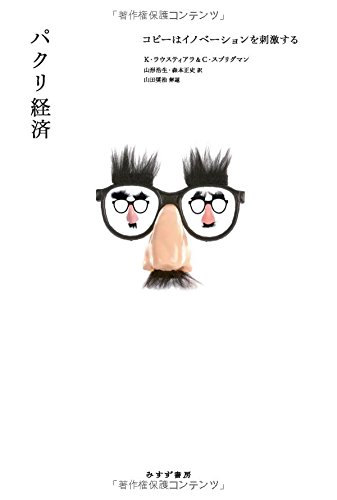 |
|---|
| カル・ラウスティアラとクリストファー・スプリグマンによる「パクリ経済―コピーはイノベーションを刺激する」(みすず書房刊)。「コピーは悪である」という一般的な認識に疑問の一石を投じる刺激的な書物 |

この連載の記事
-
第27回
トピックス
著作権法に対するハックでもあるクリエイティブ・コモンズ -
第26回
トピックス
なぜクルマほしいのか、水口哲也が話す欲求を量子化する世界 -
第25回
トピックス
「Rez」生んだ水口哲也語る、VRの真価と人の感性への影響 -
第24回
トピックス
シリコンバレーに個人情報を渡した結果、検索時代が終わった -
第23回
トピックス
「クラウドファンディング成立低くていい」運営語る地方創生 -
第22回
トピックス
VRが盛り上がり始めると現実に疑問を抱かざるをえない -
第21回
トピックス
バカッター探しも過度な自粛もインターネットの未来を閉ざす -
第20回
トピックス
人工知能が多くの職業を奪う中で重要になっていく考え方 -
第19回
トピックス
自慢消費は終わる、テクノロジーがもたらす「物欲なき世界」 -
第18回
トピックス
なぜSNS上で動物の動画が人気なのか - この連載の一覧へ




































