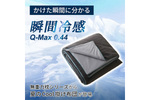HDDの容量を現在の2倍以上にできる磁気ヘッド!
電気自動車を走りながら充電できる装置!
うおおおヤバい! ゾクッとくる!(記者だけだろうか) CEATEC JAPAN 2011で見られるこの技術はTDKが発表したもの。シビれるのがHDDのヘッドだが、出展はすさまじく地味だ。メインブースの裏側にこっそり展示されている。ので、言葉足らずながら紹介したい。
※ まわりの記事は写真たっぷりでキレイですが、こちらは文字だらけの記事ですごめんなさい(記者)
HDDの容量を現在の2倍以上にする磁気ヘッド
現在HDDの容量は数百Gbit/in2だが、それを1Tbits/in2にするのがこの技術だ。
HDDにヘッドが書き込みをするときは、ディスク面の粒子(グレイン)に「N」「S」の磁性を割り当て、それをセンサーが「0」「1」として読みとっている。容量を上げたいと思ったら、その粒子のサイズを小さくすればいい。だが粒子を細かくすると、熱安定性が下がり、HDDが少し熱を持っただけで保磁力(磁性を保とうとする力)が失われ、記録情報が消えてしまうことになる。それをどうにかしようと保磁力が強い材料でディスクを作ろうとすると、今度はガチガチに硬くなり、これまでのヘッドでは書きこめない。そこで使うのが今回の「熱アシスト」記録方式だ。これはヘッドが書きこむ前に加熱用のレーザーを照射し、一瞬だけ粒子の保磁力を弱めるもの。そのとき重要なのがレーザーの照射口を小さくして、一点集中型の光をつくること。それを「近接場光」という。光が当たる面は幅にして50nm(ナノメートル)の超極小サイズ。その近接場光の発生部をヘッド(サスペンション)に搭載したのが、今回の技術だ。アホみたいに長くなったのでイメージでまとめると……
「ディスクに極細ビームを撃ちこみ、弱ったスキにデータを書き込む」ような技術だ。
実はこの技術、TDKでは以前から開発・研究を進めていたものではあった。今回、電気信号の伝送安定率を試す「ビットエラーレート試験」で10-2という低い値を記録したため、発表に至ったという。つまり技術はほぼほぼ実用化のレベルということだ。3TBが当たり前になってきたHDDの世界が、もうすぐ「5~6TBは当たり前」になるのかもしれない。
道路から電気自動車が充電できる“磁場共鳴”型給電装置
もう1つは道路を走っているだけで電気自動車が充電できる装置だ。
装置に使われているのは、NTTドコモのスマホ「SH-13C」に採用されたことで話題になった“ワイヤレス充電システム”。だが、TDKの電気自動車用装置は、使われる形式が少し違う。まず、スマホで使っているのは“近距離”向けの「電磁誘導」。電磁誘導は電力の“受け手”“送り手”ともにコイルを使うもの。1つのコイルに電流を流し、コイル間に磁束を発生させることで、もう一方に電力を発生させる仕組み(基本原理は「ファラデーの電磁誘導」)。スマホだけではなく電動歯ブラシなどにも使われてきた、伝統ある(?)ワイヤレス技術だ。昨年には90社近い会社が参加し、合弁団体WPC(Wireless Power Consortium)を発足。「Qi」(チー)という統一規格を策定した(関連記事)。規格に対応していれば、どのデバイスでも充電できるようになっている。だが、この電磁誘導方式はコイルとコイルの距離が離れられるのはせいぜい数センチ程度までという“近距離用”だった。
電気自動車用に使うのは“遠距離”向けの「磁場共鳴」という楽しそうな方式だ。
磁場共鳴は“共鳴”を使った仕組み。音叉を叩いたとき、震えが伝送されるのが“共鳴”とすれば、その震えが電力になったと考えると分かりやすい。受け手と送り手が同一の振動数(周波数)を出せば、電力を伝送できる。方法は、それぞれの側にコイルとコンデンサーによるLC回路(共振回路)を置き、回路と回路の間で電場と磁場を共鳴させること。この仕組みなら数メートル離れたところにも電力が供給できる。マサチューセッツ工科大学の研究チームはこの原理を使い、2007年6月に2m離れたところにある60W電球を点灯させることに成功した。同様のデモは2008年にインテルも実施している(Intel Developer Forum Fall 2008)。ただ、この技術は互いの位置がズレると、周波数が変化し、“共振”が途絶えてしまうという弱点がある。それをTDKは独自開発の自動調整回路(電力のチューナー)を挟むことで克服した。調整の仕組みは秘密だ。またしてもイメージで言うと、
「2つのコイルをチューナーで同じリズムにすると電力が送れる」ような仕組みだ。
TDKはこの仕組みを使い、トンネルやガードレール、道路の下など、360度どこからでも給電ができる「3D給電」というシステムを提案している。前回のCEATECでもチラッと見せていた技術ではあったが、今回ここまで具体的な形として提案したのは初めて。おそらく、ようやく技術を活かせるチャンスが来たというところではないかと思う。CEATEC JAPAN 2011で注目を集めていたのは日産の電気自動車「リーフ」だ。“走る蓄電池”を標榜する電気自動車にとって、これから重要になる1つの要素はやはり充電だろう。スマートシティの実現にTDKの「共鳴」が役立つ日が来るのかもしれない。
というわけで冒頭の予告どおり文字だらけの記事になってしまったが、TDKは先端技術の粋にふれられる超刺激的なブースだ。専門的な説明をみっちりしてくれる説明員さんもいらっしゃるので、ぜひディープなご質問をどうぞ。

この連載の記事
-
第19回
トピックス
EPUB電子書籍書店、「Yahoo!ブックストア」が年内開始 -
第18回
トピックス
ヤフー、タブレットとTVを連動させる「Yahoo!テレビアシスト」 -
第17回
iPhone
ヤフー、iPad用新トップページを11月公開—ソーシャル強化 -
第16回
スマホ
最新スマホを支える色々な技術をCEATECで見てきた -
第15回
トピックス
将来は電気自動車で何でも給電が可能に!? -
第14回
スマホ
ドコモでは放射線を測定できるジャケットなども展示中 -
第14回
トピックス
震災後の日本は“蓄電型クルマ社会”になるか -
第13回
スマホ
エンタメから医療教育まで! 新サービスを続々研究中のKDDI -
第12回
PC
山手線のスマホ向け情報サービス実験をCEATECで体験 -
第10回
スマホ
ついに来春スタート スマホ向けの新放送の名称は「NOTTV」 - この連載の一覧へ