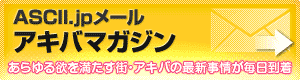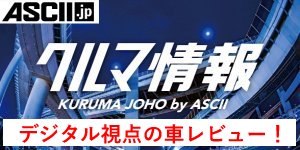“Core Duo”のオーバークロックにチャレンジ! ところが……
後回しにされた「Core Duo T2300」を試そうと「Celeron M 430」から交換して電源を投入。「あ、ジャンパピン戻すの忘れてた……」。でもBIOS起動してるし、いきなりFSB200MHz×10倍=2000MHzで検証始めてもいいかなと思い続行したが、OSが起動しない!! まさか、いきなり限界ですか「Core Duo T2300」くん!? 頭の中を飛び交う“CPUの限界”と言う文字を追い出しながら、ジャンパピンをデフォルトに戻してFSB166MHz×10倍=1660MHzの定格クロックで、まずはOS起動だ。しかし、OSが起動しない……。起動中に表示される「Windows XP」のロゴの後にフリーズしている。キーボードによる“Ctrl”+“Alt”+“Del”でのリセットも動作しないため、ハード的にフリーズしているようだ。BIOSは起動しているので、熱暴走の可能性はないと思われたが、念のためCPUクーラーを取り外してCPUとクーラーが密着しているかを確認したが、グリスはちゃんと広がっているので問題ないようだ。その他のパーツも取り付けし直したが同じ症状が出る。OSを再インストールするかと思ったのだが、ここで私の脳内に、以前読んだウェブでの書き込みがよぎった。その内容は「“i975Xa-YDG”でPCI-Express対応のビデオカードでOSのインストールに失敗。使わないデバイスをBIOSで無効にするのはよくないかも」という内容だった。確かに「Celeron M 430」での最終オーバークロック時にBIOSで使用していないデバイスは無効にしたので、試しにすべての設定を有効に戻して起動してみると、すんなりOSが起動した。「♪なぜ~なぜ~あなたは~起動したの~」と思わず歌う私。正確な原因は不明だが、OSが起動したのでこのまま検証続行だ。
 |
|---|
| 検証マシンの様子。パーツの構成は「Celeron M 430」を「Core Duo T2300」に交換しただけ。 つまり前編とまったく変わらない構成だ |
「Core Duo T2300」のオーバークロック耐性を探る
気を取り直してオーバークロック耐性の検証を開始しよう。なお、CPUクーラーは、マザーボードに付属の物ではなく、Thermalright製の「XP-90C」を使用している。まずは、コア電圧を“AUTO”に設定し、FSBはジャンパピンを外して200MHzにした。これでFSB200MHz×10倍=2GHzで起動だ。ちなみに、「Core Duo T2300」はデュアルコアなので、マルチスレッドに未対応の“Superπ”は104万桁のみを実行し、あとは“3D Mark 06”と“午後のこ~だ”の“耐久ベンチ”を10分間実行して、2つのCPU負荷を100%にすることにした。2GHzでの各種ベンチ結果は、“Superπ”104万桁が31秒。「え……遅くない?」と一瞬思ったが、先程まで「Celeron M 430」使っていたから「遅く感じただけね」と納得。実際は、定格1.66GHzでの計測結果が42秒なので11秒短縮だ。“3D Mark 06”のスコアが“1377”となり、CPU Scoreは、“1703”となった。このくらいは余裕だろうと、今度はFSBを216MHzに設定して「Core Duo T2600」と同じクロックの2160MHzに設定してみた。このクロックで動作に問題がなければ、店頭売価3万円近くのCPUが7万9000円近くのCPUと同性能となる。
 |
|---|
| CPUソケット横にある2つの赤いジャンパを外すことで、FSBを200~255MHzまでの範囲で変更できるようになる |
では、BIOSでFSBを216MHzに設定してスイッチオン! すんなりOSが起動したので、続けて各種ベンチを実行だ。うれしいことに、ベンチはあっさりと完走してしまった。しかし、「Celeron M 430」での3GHz超えが影響してか、微妙にテンションが上がらない……。いけない、このテンションだと検証終了後、このパーツたちの行く末は「Mac Mini」や「20インチ液晶モニタ」などのパーツたちと同じように、使われることなくT指令のベットの下でホコリまみれとなる運命を辿ってしまう。ベンチ結果を眺めつつ何かないかと探していると、“3D Mark 06”の“CPU Score”が目に入る。結果は“1833”。前編のデータと比較すると「Athlon 64 X2 4800+」のスコア“1832”とほぼ同じじゃないですか!! ここで、ちょっと耐性チェックから離れて「Core Duo T2300」の2160MHz動作時での各種ベンチを実行してみよう。
 |
|---|
| 2.16GHz動作時のベンチ結果。「Core Duo T2600」は「Athlon 64 X2 4800+」と価格、性能ともに同程度となるようだ。改めて「“Core Duo”の性能はなかなかいい」と感心する |
FSBの壁に激突! オバークロックも限界か?
ちょっとテンションが回復気味になったので、限界耐性をチェックしよう。まず、FSBを216MHzから220MHzに変更してチェックし、その後5MHz単位でFSBをアップしていった。「♪どこま~であが~るT2300」と歌いながら作業したが、コア電圧設定が“AUTO”の状態で、すんなりとFSB235MHz×10倍=2350MHzまで各種ベンチが完走した。だが、FSB240MHz×10倍=2400MHzでは“Superπ”104万桁がエラー発生で完走せず。次は、コア電圧を1.5Vにまで上げて再度FSB240MHzにチャレンジだ。しかし、“Superπ”でまたエラーが発生。コア電圧を上げている割にクロックが伸びない……。「へんだな~」と感じながら、FSBを238MHzに落として各種ベンチを実行すると問題なく完走した。CPUの動作限界にしては挙動がおかしい。これはどういうことかとネットを徘徊して情報を集めると、FSB230~236MHzの2300MHz近辺で、クロックの伸びが同じように止まった報告を発見した。とりあえず、ノースブリッジの電圧も上げてみたが、FSB240MHz×10倍=2400MHzでは、残念ながらベンチが完走しない。試しに、各種電圧を設定を“AUTO”に戻してFSB239MHz×10倍=2390MHzでベンチを実行したら、不思議と各種ベンチが完走してしまった。そういえば「Celeron M 430」でもFSB230MHz辺りからマザーボードの挙動が怪しくなった。もしかしたらマザーボードかCPUのどちらかにFSBの壁があるのかもしれない。
 |
|---|
| 2392MHz動作時のベンチ結果。“Superπ”104万桁は26秒、“3D Mark 06”のスコアは1397、同“CPU Score”は2022。このクロックが「Core Duo T2600」の最高の結果となった |
こうなったら、FSBをこれ以上上げられないのか確かめる必要がある。CPUの倍率を下げて、今よりFSBを上げることで、原因がFSBなのか見極めたい。これでダメならFSBの限界といえるだろう。まず、CPUのクロック倍率と電圧の変更が可能なツール“CrystalCPUID”を使用して、FSB239MHz×10倍=2390MHzの状態からCPU倍率を9倍に下げる。これにより動作クロックが2153MHzまで落ちるので、リモコンでFSBを上げてFSB245MHz×9=2205MHzの状態にセットする。ここで“Superπ”を実行したが、OSがフリーズしてしまった。「やっぱり壁・・・・・・?」とあきらめモード。ただし、ウェブの報告では、普通にFSB230MHzを超えて動作している人もいるようなので断定はできない。「倍率が上の“T2400”か“T2500”でも試そうかな~」とちょっぴり壊れ始めた私がいる。
 |
|---|
| “CrystalCPUID”を使用してCPU倍率を9倍に下げる。これでFSBは239MHzで動作クロックは2153MHzとなる |
結局“Core Duo”は投資金額に見合うのか?
今回の「Core Duo T2300」は、ちょっと不完全燃焼気味のT指令だが、とりあえず今回使用した「Core Duo T2300」でのオーバークロック耐性の限界は、“2.39GHz”となる。「残念無念、テンションが下がる。“Celeron M”の耐性チェックを後にするんだった!」とちょっぴり後悔。だが、コア電圧設定が“AUTO”の状態で、現在最上位クロックの「Core Duo T2600」と同じクロックの2.16GHzで動作したので、手軽なオーバークロックには悪くないCPUだと思う。また、“Pentium M”のときも同じだったが、今後さまざまなメーカーよりマザーボードやCPUの変換下駄などが登場すれば、さらに遊べるCPUとなる可能性を秘めているだろう。
●結論:“Yonah”コアの“Celeron M”は手軽に遊べて高性能。“Core Duo”はハイパフォーマンスでオーバークロックも可能。ともに購入しても損はしない!!
【機材協力】 【関連記事】