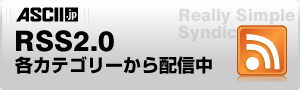コロナ禍にともなう半導体不足の中、
中国では爆発的にRISC-Vコアの半導体が出荷されるようになる
この傾向に拍車を掛けたのは、COVID-19に端を発する半導体供給不足である。
これにより、既存の半導体が猛烈に不足した。発端は中国や東南アジアなどがロックダウンによって工場の生産が止まったことだが、そこから急速に流通在庫の買い漁りやサプライチェーンそのものが止まるなど、さまざまな要因が重なったことで、2020~2021年は本当に酷い状況だった。
実際のところ、現時点でもまだわずかではあるが影響が残っているほどだ。2022年の時点でも、たとえば壊れた給湯器を交換したくても、コントローラーに使っている専用のASICの量産が間に合わず、数ヵ月まともに風呂に入れなかった(筆者の知人は風呂桶に投げ込み式の熱帯魚用ヒーターを入れてお湯を作っていた)なんて話がそこかしこにあった。
こういう状況だと、もう特定のASICを使ってシステムを構築しようというのはナンセンスで、とにかく入手できる汎用のチップで何とかシステムを組み上げないと、製品出荷が覚束ないことになる。
そしてこの時期、中国では爆発的にRISC-Vのコアが出荷された。記事冒頭の画像は2022年にSiFiveが示したものだが、この数が正確かどうかもよくわからない(なにしろ統計の取りようがないからだ)。ただ2021年までの範囲で、10億個以上のコアが出荷されたのはかなり確実らしい。それでどんな用途か? というと、実は電子タバコなのである。
喫煙者でない方には興味も知識もない話だろうが、電子タバコは何種類か存在する。大きく分けるとリキッド(フレーバーを含む液体)を過熱し、それを含んだ蒸気を利用者が吸うタイプと、タバコの葉(こちらにはニコチン/タールが含まれる)を過熱し、それを含んだ蒸気を利用者が吸うタイプがある(タバコの葉を過熱する方は、厳密には電子タバコに含まれないという議論もあるが、世間的には一緒くたになっているし、メカニズム的にも実は近いので、ここではまとめて取り扱う)。
細かい事を言い始めればさらにたくさんの種類に分かれるのだが、この電子タバコに求められる機能は
・リキッドなりタバコの葉を過熱する仕組み
ずっと過熱しっぱなしだと蒸気が熱くなりすぎるし、なによりあっという間にリキッドや葉っぱが終わってしまう。なので必要最低限の時間だけ過熱して気化させる仕組みが必要
・吸っている事を検知する仕組み
1つめの機能にも関連するが、利用者が吸引している事を検知し、その間だけ蒸気を送り出すような仕組みがないと、あっという間にリキッドや葉っぱがなくなる
・必要に応じて送風する仕組み
これは電子タバコの物理的な構造にも起因するが、強く吸わないと蒸気がユーザーまで届かない構造になっている場合、これを助ける意味で送風ファンが設けられる場合もある。もちろんそんなに強力なものではないが、吸いやすさを助ける意味で搭載されているものもある
・電池管理&充電管理
普通は内部に小容量の電池(リチウムイオンが多い)が搭載されており、1~2本分のカートリッジを吸うには十分な容量があるとされるが、逆に言えば無駄に放電しないように管理するとともに、なんならLEDなどで電池残量を表示することが、製品構成上求められる。またそのままだと電池が尽きるので充電することになるが、その管理も必要だ(過充電になると電池寿命が縮まるが、だからといってゆっくり充電していると、間に合わない場合もある。電池残量に応じて充電速度を調整できるような仕組みが望ましい)。といったあたりで、これらを満たしつつ小型で、かつ低価格であることが求められる。
当然ここまで機能が多いと、マイコンを入れて制御する必要がある。幸いにも処理そのものには、性能はあまり必要ないので、動作周波数は低めでいいし、なんなら8bitマイコンでも十分である。実際初期には8bitマイコンのIPコアを使っていることが多かった。ただ専用のチップの入手が困難になり、新規で何か起こすとなると、別に8bitである必要なくね? となる。ここでRISC-Vが有利だったのは、ライセンス料やロイヤリティーが掛からないという点も小さくはないのだが、すでにフリーで公開されている実装がいくつもあった点だ。
そして、とにかくコストを抑える必要がある。前述の機能を実現するためには、MCUのコアに加えてヒーター駆動用ドライバー、モーター駆動用ドライバー、吸引センサー接続と内蔵バッテリーの電圧測定用のADC、それとタイマーが必要となる。
ADCとかタイマーはともかく、ヒーターやモーター駆動用のドライバーを実装しようとすると先端プロセスは逆に不利であり、250~130nmあたりのBCD(Bipolar-CMOS-DMOS、センサー向けのBipolar、ロジック向けのCMOS、パワー半導体向けのDMOSの3種類を1つのダイ上に混在させる技術)プロセスを使うのがちょうど手頃である。
こうした古めのプロセスで問題になるのはプロセッサの面積が大きくなりがちな事だ。フリーのコアで最初に名前が出て来るのは、以前に紹介したRocketだが(「RISC-Vの仕様策定からSiFiveの創業までAsanovic教授の足跡をたどる RISC-Vプロセッサー遍歴」)、こちらは5段のパイプラインを持つそれなりに高性能なコアで電子タバコにはちょっと使いにくい。
ただ、RocketやBoomと同じく、UC BerkeleyからはSodor(https://github.com/ucb-bar/riscv-sodor)という教育用のコアも出ており、こちらは1~5段の構成なので、これで1段を選ぶとかなり小規模なコアができる。
あるいはPULP Platform(https://pulp-platform.org/)のsnitch(https://github.com/pulp-platform/snitch)というコアは1ステージのデュアル32bitコアで、ゲート数は約2万。
あるいは英ケンブリッジに本拠を置く、lowRISCという非営利企業の提供するibex(旧称zero-riscy)(https://github.com/lowRISC/ibex)は更に少ない1万1600とされる。
商用製品だとSiFiveが2018年にリリースしたE2コア(https://www.sifive.com/press/sifive-unveils-smallest-lowest-power-risc-v-designs)は最小構成で1万3500ゲートであり、Cortex-M0(最小構成で1万2000ゲート)と同等に収まっている。
このあたりのコアであれば、比較的古いプロセスであってもコアの面積はそれほど問題にならない。そして古いプロセスであれば製造コストも非常に安価で済むから、多少面積が大きくなっても許容されやすい。なにより従来だと汎用マイコンのほかにヒータ用のドライバーやモータードライバーなどを別の部品の形で組み合わせていたのがワンチップ化できれば、トータルでの部品コストはむしろ安くなる。
消費電力を抑えるためにCPUコアの動作周波数はギリギリまで低め(数百KHzオーダー)まで下げられるかもしれないが、RISC-Vだと、その状態でも電子タバコの制御には十分な性能で処理ができる。しかもこうした古いプロセスであれば、別にTSMCに委託する必要はまったくなく、たとえば台湾のPowerChipとかVIS、中国のSMICやHua Hong、韓国のDongbu HiTekといったさまざまなファウンドリで製造が可能だ。
ここまで条件が揃っていたら、RISC-Vに流れるのも無理はないなと感じる。そうして、かなり多くのこうした電子タバコ用のコントローラーを製造していた中国の半導体メーカーが、一斉にRISC-Vに流れる事になった。この結果が以下の画像である。2020~2021年のRISC-V Foundationへの加盟メンバーの増え方が前年比2倍を超えている。こうしたことが、いかにこの時期多数のファブレス企業がRISC-Vに参画したかを物語っている。
この中国に続いて、インドもやはり急速にRISC-Vに傾倒してゆき、その次が韓国だろうか(このあたりの話は筆者の感覚なので、ちょっと実情と乖離しているかもしれない)。

この連載の記事
-
第774回
PC
日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -
第773回
PC
Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -
第772回
PC
スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -
第771回
PC
277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 -
第770回
PC
キーボードとマウスをつなぐDINおよびPS/2コネクター 消え去ったI/F史 -
第769回
PC
HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -
第768回
PC
AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -
第767回
PC
Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -
第766回
デジタル
Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -
第765回
PC
GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -
第764回
PC
B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ - この連載の一覧へ