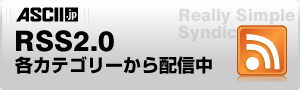GeForce RTX 4080のGPCとTPCを削ったのは性能調整のため?
ところで、不思議なのがAD103を使ったGeForce RTX 4080の構成である。基本に戻るが、Ada LovelaceではAD102は12GPCだと公言されている。おそらくAD103は8GPC、AD104は6GPC構成になっている。1つのGPCは6つのTPCと16個のROPから構成される。1つのTPCは2つのSMとPolyMorph Engineから構成される格好だ。
ということは、GeForce RTX 4080は7GPCである以上TPCは42個、SMは84個になるわけだが、実際には38TPC、76SM構成である。つまり7GPCに減らしたうえに、さらに4TPCを削った構成というわけだ。
もちろんこれまでもこうした例はNVIDIAの製品にはあったから、これが初めてというわけではないのだが、単に性能調整ないし消費電力調整のためにこうした実装にしたのか、それとも他の理由があるのかは不明である。
性能調整あるいは消費電力調整のためだとすると、妙にマッチしないのがメモリーである。再びホワイトペーパーの表に戻るが、GeForce RTX 4090やGeForce RTX 4080 12GB版の場合は21GbpsのGDDR6Xでこれは順当な構成なのだが、GeForce RTX 4080のみ、まだ出荷量も多くなく高価なGDDR6Xの22.4Gbpsを採用しているのだ。
実のところGDDR6に関して言えば、かつてはGDDR6に比べて低い消費電力で高い帯域を実現できるという売り込み文句で発表されたものの、対抗馬であるGDDR6の方はすでに24Gbps品のサンプル出荷が開始されているという状況で、速度面でのアドバンテージはほとんどない。
そしてGDDR6XはMicronのみが製造、NVIDIAのみが採用という状況に変化はなく、当然ながら相対的に価格は高止まりせざるを得ない。もし性能調整が目的でTCP/SM数を減じているのなら、もう少し性能を下げてGDDR6X 21Gbps版を採用すればコストも下げられ、入手性も相対的にマシであっただろうと思うのだが、どういう意図でこうした高価格のGDDR6Xを採用する決断に至ったのかは想像がつかない。
全体的に見て、GeForce RTX 4080のバランスの悪さが、筆者的にはどうにも気になるところである。間もなく発表されるであろうNAVI 3ベースのRadeon RX 7000シリーズと戦うのにこれで十分という判断なのだろうとは思うのだが。

この連載の記事
-
第773回
PC
Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -
第772回
PC
スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -
第771回
PC
277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 -
第770回
PC
キーボードとマウスをつなぐDINおよびPS/2コネクター 消え去ったI/F史 -
第769回
PC
HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -
第768回
PC
AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -
第767回
PC
Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -
第766回
デジタル
Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -
第765回
PC
GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -
第764回
PC
B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -
第763回
PC
FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ