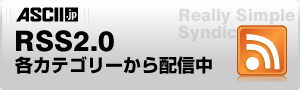●「3キャリアが安くなるかもオーラ」が流動性を下げている
2018年夏に菅官房長官(当時)が「携帯電話料金が世界に比べて高すぎる。4割値下げできる余地がある」と発言したため、総務省はこの2年間、大ナタをふるい続けてきた。9500円程度していた解除料を1000円以下にして、2年縛りも見直させた。SIMロック解除も中古端末でもできるようにしたり、最近では3000円かかっていたMNPの手数料をオンラインなら無料にするといった改訂も行おうとしている。
この2年、総務省がいろいろな手を尽くしてきたが、3キャリアの解約率は低減。競争は起るどころか、ユーザーの流動性は止まり、市場は冷え切っている。
実際、2018年以降、3キャリアは新しい料金プランを投入。端末販売と通信契約を完全に分離した。完全分離が進めば、ユーザーが他社に移行しそうな気もするが、実際は全く動いていない。なぜ、流動性が止まったのか。
ある関係者は「とにかくユーザーが動こうとしない。みんな、他キャリアに乗り換えることに対して、『面倒臭い』『わからない』『今のままで、特に不満がない』と言って動こうとしない」という。
菅首相がキャリアに対して「値下げしろ」とアピールすればするほど、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクを契約している人からすれば「格安スマホに乗り換えなくても、このまま契約し続ければ、いずれ安くなるかな」という期待を持ってしまっている。菅首相が醸し出す「3キャリアが安くなるオーラ」が結果としてユーザーの流動性を落としているのだ。

この連載の記事
-
第201回
スマホ
ソニー「Xperia 1 VI」はこだわりから“現実路線”に変わった -
第200回
トピックス
楽天モバイル 契約は絶好調だが、黒字化にはテコ入れが必要だ -
第199回
iPhone
アップル新型「iPad Pro」実物を見たら欲しくてたまらなくなった -
第198回
トピックス
ドコモ新社長は“経済圏”拡大より、ネットワーク品質とショップ網の再構築を最優先すべきだ -
第197回
トピックス
なぜソフトバンクやKDDIのネットワークは強いのか 「2.5GHz帯のTD-LTE」最強説 -
第196回
トピックス
F1の裏に“レノボ”あり 500TBのレースデータを高速処理 -
第195回
トピックス
格安スマホ、キャリアより「シンプルで安い」とふたたび注目 -
第194回
トピックス
中国スマホメーカー、日本への攻勢強める 格安折りたたみスマホで勝負 -
第193回
トピックス
ドコモが狙う“スマホの次“ iPhoneから「Vision」の時代へ -
第192回
トピックス
KDDI「povo」世界進出へ “黒子に徹する”新ビジネスとは -
第191回
トピックス
スマホ基地局を安くする ドコモとNECが世界展開する「オープンRAN」とは - この連載の一覧へ