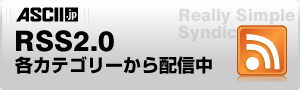USB給電をオンにすれば、バッテリーの消費が減って一石二鳥
記事執筆にあたって、ボディーは「α7RIV」と「α9」、レンズは「SEL24F14GM」「SEL85F14GM」「Voigtlander APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical」を使用してみた。
ボディーにより設定がやや異なるのだが、この点はダウンロードサイトに明記されている。α7RIVの場合は「スマートフォン操作」をオフ、「PCリモート」をオン、「PCリモート接続方式」をUSBに変更しておく。
ちなみに複数のソニー製カメラを同時に検出することはできない。この点は後発ツールとしては弱い部分であり、今後のアップデートに期待したい。ところで、「α7RIV」世代から後の機種では、ワイヤレス接続の強化が図られているのだが、ワイヤレスへの対応はないだろうか。お願いします。
オススメの設定としては、これもボディー次第だがUSB給電対応であれば同機能をオンにしておく。α7RIVの場合、とてもゆるやかにバッテリー残量が減っていく状態になった。
従来の「USB給電しながら撮影」の傾向からすると、α7RIIIは減ることもなく、延々と使用可能と思われる。ただどのボディーの場合でもどうしても熱を持つため、長時間運用の際は「自動電源OFF温度」を「高」にし、風通しをよくしておくといい。なお比率は16:9に強制的に変更される。
ピクチャーエフェクトやボケを違和感なく使える
そのまま使用する場合は、手持ちのレンズをフル活用できるメリットが大きいほか、ボディー側の設定も出力に反映される。露出補正のほか、クリエイティブスタイルやDレンジオプティマイザー、ピクチャーエフェクト、ピクチャープロファイルの効果の利用も可能だ。
これら効果は変更しても、プレビューが止まることはなかったため、状況に応じての使い分けもアリだろう。すっかり出番が減っている感のあるピクチャーエフェクトだが「ハイコントラストモノクロ」はけっこうインパクトがあるのでオススメ。またAPS-CとSuper 35mmの切換もOK。とりいそぎクローズアップしたい場合に便利だ。
動画モードの場合、AFレンズであればフォーカスは自動的に合わせてくれる。当然だが、フォーカスの追従についてはボディーとレンズの速度次第のため、事前にAF追従速度の設定を変更してテストしておくといい。
また複数人が登壇し、優先度がある場合は顔登録も効果的だ。あとはZV-1の「商品レビュー用設定」のようなアルゴリズムがあればいいのだが。
MFレンズの場合はMFアシストをオフにしておくと、プレビューの途切れを回避できる。そう記述するとピント拡大が使用できないように思えるが、カスタムボタンに登録してある場合は、問題なく使用できた。
このとき出力への影響はなく、またピーキングをオンにしていても同様なのでMFレンズ派も安心。これはAFレンズをMFに切り換えた場合も同様。マクロレンズを使ってみる場合にもいいだろう。
複雑な設定も面倒なインストールも最小でソニーカメラをウェブカメラにできる。急に需要が増したカテゴリーであり、今後も出番が多い。ソニーのカメラを所有しているのであれば、Imagin Edge Webcamを試してみるといいだろう。
従来のウェブカメラとは異なるフットワークを持つため、望遠で遠くを狙ってみるのもいいし、本体設定を酷使できるため、いままで使用していなかった機能を再チェックしてみるのもいいだろう。