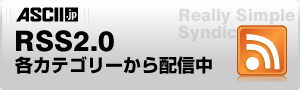問題は景気対策ではなくイノベーションだ
財政支出が役に立たない原因としては、次のようなものが考えられる。
- 1.財政支出は単年度の効果しかない
- 補正予算はその年に使い切ってしまうので、経済が自律的に回復するまでの「つなぎ」であり、経済そのものを改善する効果はない
- 2.財政赤字は将来の増税になる
- 定額給付金の2兆円は、いずれ将来の増税になる。したがって消費者が合理的なら、給付金を使わないで将来の増税に備えて貯蓄するので、消費刺激効果はきわめて小さい
- 3.需給ギャップの生じている部門に資金が回らない
- 今回の日本の場合、最大の打撃を受けたのは輸出産業だが、補正予算で支出されるのはそれとは無関係の部門である
こうした欠陥は理論的にもわかっており、前述のように実証的にも明らかだ。したがって先進国では景気循環の調節は財政政策ではなく、金融政策で行なうのが常識だ。
先週のG20(金融サミット)で「全世界で5兆ドルの財政支出で成長率を4%引き上げる」という目標が打ち出されたことが、今回の補正予算の根拠となっているが、この目標には何の根拠もない。経済が大混乱に陥っているアメリカが、一時しのぎに打ち出した巨額の財政政策も批判を浴び、欧州諸国は財政支出には消極的だ。「財政政策が世界を救う」と信じてはしゃいでいるのは麻生首相ぐらいのものである。
GDPギャップというのは、設備を完全利用した場合の潜在GDPから現実のGDPを引いたものだから、仮に補正予算が100%効果を上げたとしても、GDPは潜在水準に達するだけだ。その潜在成長率は90年代から下がり続け、以下の図のように1%以下になっている。80年代までの4%というトレンドが続いた場合と比べると、現在のGDPは20%以上低いと推定される。長期的な「成長力」の低下の影響は、短期的な景気刺激の効果よりはるかに大きいのである。
何十兆円も税金をばらまいても、効果は今年限りで、それが成功しても成長率1%以下の長期停滞のトレンドに戻るだけだ。本質的な問題は、この長期停滞からいかに脱却するかということである。それにはバラマキは役に立たないばかりか、非効率な企業を延命して経済全体の生産性を下げるおそれも強い。
潜在成長率を高めるには、財政・金融によるマクロ政策ではなく、企業の新陳代謝を進めてイノベーションを促進する規制改革が必要だ。それはマクロ政策ほど派手ではなく、即効性もないが、そういう産業構造から直さないかぎり、日本経済に展望は開けない。
筆者紹介──池田信夫
1953年京都府生まれ。東京大学経済学部を卒業後、NHK入社。1993年退職後。国際大学GLOCOM教授、経済産業研究所上席研究員などを経て、現在は上武大学大学院経営管理研究科教授。学術博士(慶應義塾大学)。著書に「ハイエク 知識社会の自由主義 」(PHP新書)、「情報技術と組織のアーキテクチャ 」(NTT出版)、「電波利権 」(新潮新書)、「ウェブは資本主義を超える 」(日経BP社)など。自身のブログは「池田信夫blog」。

この連載の記事
-
最終回
トピックス
日本のITはなぜ終わったのか -
第144回
トピックス
電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -
第143回
トピックス
グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -
第142回
トピックス
アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -
第141回
トピックス
ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -
第140回
トピックス
ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -
第139回
トピックス
電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -
第138回
トピックス
原発事故で迷走する政府の情報管理 -
第137回
トピックス
大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -
第136回
トピックス
拝啓 NHK会長様 -
第135回
トピックス
新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ