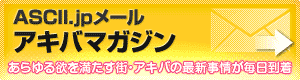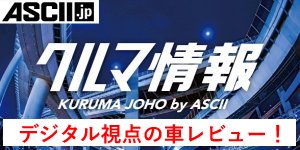液晶パネルのコントラスト調整
完成したらPCの電源コネクタと接続する。もし心配であれば、いったんPCの電源を落としてからコネクタを接続し、あらためてPCの電源を入れるといいだろう。異臭や異音、うまく動かない場合は、直ちにPCの電源を落とすこと。ハンダ付けに自身のある場合は、PCの電源を落とさずに電源コネクタを接続してもかまわない。ただし、起動中のアプリケーションはすべて終了させておこう。
回路に問題がなければ、写真のように文字が表示される(黒くて見えない場合もある)はずだ。
表示されない場合は、直ちにコネクタを抜いて配線間違えやハンダ付けの忘れ、ハンダの盛りすぎで隣の端子とショートしていないかなどを確認しよう。
問題がなければ、ドライバで半固定ボリュームをまわして、液晶のコントラストを調整しよう。左に回すとコントラストが弱くなり、右に回すと強くなる
PCから文字を表示させてみる
キットにはCD-ROMが添付されているが、DOS(コマンドプロンプト)用のプログラムなので使い勝手が悪い。そこでWindowsのハイパーターミナルを使って文字を表示さてみよう。がっ! Windows Vistaは、ハイパーターミナルが削除されてしまったので、“UTF-8対応TeraTerm Pro”など適当な通信ソフトをダウンロードして欲しい。
まずはシリアルコネクタの接続。これは必ず電源を切った(電源コネクタを抜いた)状態で行うこと。電源を入れた状態で接続すると、接続時にノイズが入り液晶パネルに変な文字列が表示される。シリアルコネクタの接続が終わったら、電源コネクタを接続しよう。
次は通信ソフトの準備だ。最近の通信ソフトは、シリアルポート以外にTCP/IPの通信も可能になっている。まずは通信先をシリアルポートやCOM1ポートなどに切り替えよう。
続けてCOMポートの設定をする。ボーレートなどを次のように指定して欲しい。
ポート 接続したポート番号(たいていの場合COM1)
ボーレート 9600bps
データ長 8ビット
ストップビット長 1ビット
パリティチェック NONE(なし)
フロー制御 NONE(なし)
改行コード(送信) CR
改行コード(受信) CR+LF
なお改行コードの設定は、動作テストをするだけであれば特に設定しないままでもかまわない。液晶表示ユニットとの通信は、常にこの設定となる。
これで通信関連の設定は終了だ。あとは通信ソフトで記号や数値、アルファベットなどを1文字ずつ打ち込んでいけば、液晶パネルにその文字が表示される。きわめて当たり前のことなのだが、自作となるとちょっと感動するだろう。
なおキーを押しっぱなしにすると、データの取りこぼしが発生し液晶表示ユニットのICが暴走するので、ポツポツと1文字ずつ打ち込んで行こう。また画面いっぱいに文字を表示してしまったら、[CTRL]+[I]キーを入力すると、液晶画面がクリアされる。このあたりの特殊文字コードについては、キットのマニュアルを参考にして欲しい。
このままケースに入れずに動かす場合は、液晶パネルと制御基板のハンダ面が金属にふれないように絶縁してあげよう。筆者がよくやるのは、基板と同じ大きさにダンボールを切って、輪ゴムで固定する方法。ビニールテープをハンダ面にしっかり貼ってもいいだろう。ただし後者は、時間が経つと粘着面がベチョベチョになるので、あまりオススメできない。
(次ページへ続く)

この連載の記事
-
第13回
ゲーム・ホビー
ノートユーザー救済企画! USB接続のPC電源連動型コンセントを作る -
第12回
ゲーム・ホビー
たまにはネタなしで真面目に工作! 激安のPC電源連動型コンセントを作る! -
第11回
ゲーム・ホビー
魔法の特定ゲーム用デバイス「みるきぃ・ソーセージ」【みるきぃ・マウス後編】 -
第10回
ゲーム・ホビー
魔法の特定ゲーム用デバイス「みるきぃ・ソーセージ」【みるきぃ・マウス前編】 -
第9回
ゲーム・ホビー
魔法の特定ゲーム用デバイス「みるきぃ・ソーセージ」【みるきぃCAT編】 -
第8回
ゲーム・ホビー
年末スペシャル! 漏電メイデン・プリンタお掃除大作戦! -
第7回
ゲーム・ホビー
眩しい彼は王子様!? 恋のアクセスランプは100W! -
第6回
ゲーム・ホビー
ルミナス・カンデラ・LED! 美しくフィギュアを照らせ! -
第5回
ゲーム・ホビー
熱にだって負けない! ファンでクールなブロードバンドルーターを作る! -
第4回
ゲーム・ホビー
魔法の呪文はヤスリ・ドリル・Pカッター! ハンドニブラでるるるる~! - この連載の一覧へ