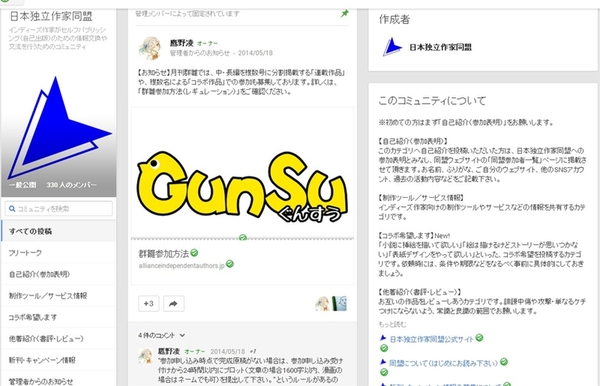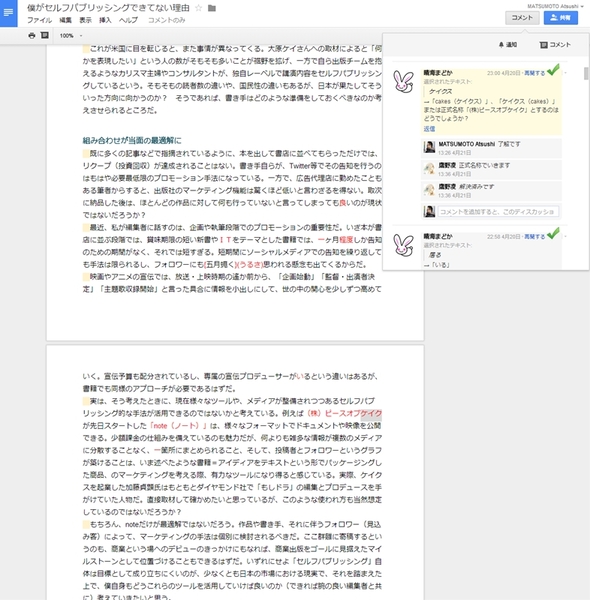電子書籍サービスのレビューなどを手がけてきたライターの鷹野凌(りょう)氏が、セルフパブリッシングの専門電子雑誌「群雛(ぐんすう)」を刊行し注目を集めている。鈴木みそ氏も活用するKDPのようにセルフパブリッシングのための環境は整ったが、それを紹介するメディアは不足しているのが現状だ。群雛は、その担い手になれるだろうか? 詳しく話を聞いた。
インディーズ作家のための旗
―― 「群雛」とはどういう雑誌なんでしょうか?
鷹野 「ちょっと格好良い言い方をしてしまうと、インディーズ作家のための旗なのかなと思っています。
無名の創作者でも出版ができるようになった。僕自身もやってきて痛感したのですが、作品を生み出し、配信に適したフォーマットにして、プラットフォームに登録するところまでは可能です。
でもその後の段階――作品を知ってもらい、それを読んでもらい、感想を寄せてもらうというのはまだまだ高いハードルがあります。
そこで、群雛という旗のもとに集まってもらうことで、1+1を2に、あるいはそれ以上にしていけるのではないか、という試みなんです」
―― たしかに、ソーシャルメディアを通じてのプロモーションは1人よりも、群雛の公式アカウントや、参加する作家、それぞれの知人友人や読者が言及するほうが、効果は高まりますね。
鷹野 「群雛という名前にも込められているのですが、雛が一羽ではちっぽけな存在ですが、集まるとすごい存在感が出てきます。実際、こうやって取材していただく機会も増えていて、想像以上の反響になっていますから」
―― noteやSTORYS.jp、小説家になろう、など広く作品やエピソードを読んでもらう投稿系のサービスも増えてきていますが、そういったサービスとの違いは?
鷹野 「KDPが登場する前から、たくさんのサービスが出てきました。iBooksやパブーのように無料で書籍を配付できるサービスもあり、広く読者に届ける環境は整いました。多くの人がそれらを用いていろんなチャレンジをしています。
僕自身、それらのサービスのレビューも数多く手がけてきましたが、果たしてその中から成功事例がどの程度生まれているか、というと心許ないというのが正直なところだったんです」注:KDPの最低販売価格は99円(容量などの条件あり)。無料で書籍を配付することはできない。
―― Airのような取り組みもありましたね。ただ確かにそういったところから、つまりセルフパブリッシング発の新人が活躍したという話は、なかなか生まれませんでした。
鷹野 「電子雑誌の多くは、無料だったり単価を安くすることで拡がりを得ようとしているケースが多いかと思うのですが、そういった先達と同じ事をやってもダメだなと。
ですから、群雛は逆に単価を高くしています。インディーズ作家の作品ばかりが載っている雑誌を好んで買うような人は、それほど世の中に多くないと思うんです。少ないパイに向けて安売りしても仕方がないので、仮に『100部売れれば、参加作家1人あたり5000円くらいは配分できる』というところから販売価格を決めました。
逆に、オンデマンド印刷になる紙の本の場合は、印刷・製本原価がどうしても高くなってしまいます。ほとんど利益は乗せてないのですが、それでも結構な額になっちゃってますね。もう参加作家さんが記念で持って置いたり、あるいはコレクター向けという価格設定です(笑)」
実際、2~4月合わせても電子版の販売部数はトータルで200部前後です。取り扱い書店も増えていますし、こうやってメディアに取り上げていただく機会もありますので、これから上向いていくとは思っています。が、では価格を例えば4分の1の200円に下げたからといって、4倍売れるかというと、そんなことはないと思うんですね。あくまでもインディーズの雑誌で一部の人しか読まないというのが、現実ではないかな、と」
―― 電子書店への露出やこういった取材も告知の一環だとは思いますが、その他にはどういったPRをされているんですか?
鷹野 「先ほどの“集まれば強くなる”という話に通じるのですが、日本独立作家同盟という団体を立ち上げ、Google+で参加者を募っています。
集まってくる同好の士が、群雛やその掲載作品、作家についてブログ・ソーシャルメディアなどで言及することで少しずつ拡がっていくことを期待しています。
あとは、参加して頂いた作家さんにはBCCKSのクーポンをお渡ししています。そこから、友人・知人に“献本”していただければと」
―― インディーズ作家のコミュニティーがベースにあり、定期的に、つまり〆切が設定されつつ、作品を発表する場があるという点が、これまでの取り組みとは異なる点ですね。
鷹野 「そうですね。あとは、作り方も少し異なるかもしれません。ボーンデジタルである、ということはもちろんなのですが、表紙デザインや編集・校正も含め制作はすべてネットで完結しています。
広く参加は募りつつ、編集チームが誤字脱字を指摘するのはもちろん、内容や構成についてもGoogleドキュメントを使って意見を加えることもあります」

この連載の記事
-
第102回
ビジネス
70歳以上の伝説級アニメーターが集結! かつての『ドラえもん』チーム中心に木上益治さんの遺作をアニメ化 -
第101回
ビジネス
アニメーター木上益治さんの遺作絵本が35年の時を経てアニメになるまで -
第100回
ビジネス
『THE FIRST SLAM DUNK』で契約トラブルは一切なし! アニメスタジオはリーガルテック導入で契約を武器にする -
第99回
ビジネス
『THE FIRST SLAM DUNK』を手掛けたダンデライオン代表が語る「契約データベース」をアニメスタジオで導入した理由 -
第98回
ビジネス
生成AIはいずれ創造性を獲得する。そのときクリエイターに価値はある? -
第97回
ビジネス
生成AIへの違和感と私たちはどう向き合うべき? AI倫理の基本書の訳者はこう考える -
第96回
ビジネス
AIとWeb3が日本の音楽業界を次世代に進化させる -
第95回
ビジネス
なぜ日本の音楽業界は(海外のように)ストリーミングでV字回復しないのか? -
第94回
ビジネス
縦読みマンガにはノベルゲーム的な楽しさがある――ジャンプTOON 浅田統括編集長に聞いた -
第93回
ビジネス
縦読みマンガにジャンプが見いだした勝機――ジャンプTOON 浅田統括編集長が語る -
第92回
ビジネス
深刻なアニメの原画マン不足「100人に声をかけて1人確保がやっと」 - この連載の一覧へ