映像やテレビ作品の映像編集などに携わる東映ラボ・テックは、通信の帯域幅が拡大することを見越し、制作会社に向けて新サービスの提供を始めている。カメラで撮影された動画をクラウド上に置いてCGを合成処理し、共有する映像制作システムだ。同社の根岸誠取締役に、東映ラボ・テックの取り組みと戦略について話を聞いた。
――映像制作システムを始めたきっかけを教えてください。

東映ラボ・テック 根岸誠取締役
ビジネス自体は2012年からスタートしました。映像の仕上げを担う、我々のようなポストプロダクション(ポスプロ)は撮影所から離れた場所にあったのですが、ハリウッドのように撮影場内にポストプロダクションを置く形式をとれないかと考え、できたのが東映デジタルセンターです。撮影する場所で撮影から局への納品まで、敷地内で一貫してできるのがメリットです。
実際の制作は、他のポスプロと協力し、最終的に東映デジタルセンターで集約して局に納品したり劇場に公開したりしています。東日本大震災前は、デジタルテープを当社に持ち込んでもらっていましたが、震災以降、デジタルテープからファイルへの転換が起こりました。市場の大半を占めていたソニーのデジタルテープ工場が被災し、生産ストップに陥ったんです。そこで、ポストプロダクションへの配送方法をどうするか、という議論が起こったことが、ビジネスをスタートさせるきっかけになりました。
――システムを運用するにあたって気をつけたことは?
クラウド上にデータをアップして、利用者はそこからデータをダウンロードしてもらうシステムは2012年から提供を開始しました。一番気をつけたのはセキュリティです。公開前の映像なので絶対に外に出てはならないので、いかに万全なセキュリティ対策を施すかに苦心しました。暗号化したデータを送ることを含め、さまざまなノウハウを詰め込み、クラウド上で展開できるようにしました。
――1年やってみてどうでしたか?
1年やって、わかったことは日本のポスプロのネット環境は非常に悪いということ。日本はおそらく、インターネットの環境が悪すぎるんだと思います。東映デジタルセンターは、最初からクラウド環境の整備を前提にしていますが、他のポスプロさんの場合、データセンターから1時間分のテレビ番組のデータをインターネット回線でダウンロードしようとすると、当社が配布しているツールを使っても30Mbpsぐらいの通信速度で7、8時間はかかってしまう。
このようなポスプロさんの状況もやってみて初めて理解できました。中には、「便利ですね」と言ってくださるお客様も出てきました。クラウド上でデータを共有する習慣がこれまでなかったのですが、サービス提供から1年経って、お客様からもレンダリングをやりたいという声が上がってきたので、次の段階に進もうということで、昨年から撮影された動画をクラウド上に置いてCGを合成処理し、共有(レンダリング)する映像制作システムを提供開始しました。
――4Kの普及がビジネスを後押しする?
今は、先行投資をしている最中。当初は普及を目的としていたので、利益は正直なところ出ていません。これから4Kコンテンツが増えていく中で、チャンスも増えてくると思っています。来年、再来年には胸をはって利益が出る状態に持っていきたいですね。
4Kで撮影できるカメラがやっと出てきたので、皆さん4K映像を撮りたがっている。4Kで撮影した映像を4Kで仕上げているものはまだ少ないですが、近いうちに、4K放送がBS中心で始まると思います。いつ、切り替わっていくかはわかりませんが、その時に当社のシステムを有効活用してもらいたいですね。
4Kで撮影した映像の容量は2Kの4倍。つまり、ダウンロードするのに4倍かかってしまう。さらに、合成作業のための計算に膨大な時間がかかってしまう。そうなると、早く仕上げるために、マシンを増やさなければなりませんが、コストの面もあってなかなか増やせない。また、パソコンを買っても3年もすると古くなってしまう。1日で40台使いたい時、その1日のためだけに40台のマシンを購入することは現実的ではありません。
そこで始めたのが、欲しいときに使いたいだけマシンの台数を用意するシステム。使った時間だけ請求する有料サービスです。
――料金は非公開だが。
自分で機材を買って作業するのに比べて安い価格を設定していますが、状況を見て、現状からは、もう少し下げたいですね。ご協力いただいているデータセンターには大分安くしてもらい、感謝しているのですが、利用会社が多くなれば競争原理が働いて交渉材料が増えて、データセンターへ支払う費用もさらに安くできるのではないかと思っています。
――4Kテレビの普及のタイミングは?
今年は、スポーツ番組で4K放送を狙っていると思います。ただ地上波はすぐできない。BS中心に当初はなると思いますが、そのうち少しずつ増えていくでしょう。
テレビの歴史を見れば一目瞭然です。SD放送からHD放送に切り替わり、データ容量が数倍に増えた時は、「こんな重いデータで番組が作れるのか」と制作側も大騒ぎしたものです。しかし、今はHD放送が当たり前。同じように4Kがそのうち一般的になっているのではないでしょうか。もちろん、あくまで需要と供給の関係ですから、各家庭に4Kがどれだけ普及するかによるでしょう。
――今後の戦略を教えてください。
次のステップは、クラウドを利用したデータ共有とクラウドレンダリングのワークフローを普及させることだと考えています。そしてその先には、合成・編集などすべてのアプリケーションをクラウドに置くことが可能な時代が見えてきます。これが実現すれば、ノートPCと作業用の机卓さえあれば、どこでも作業ができるようになります。
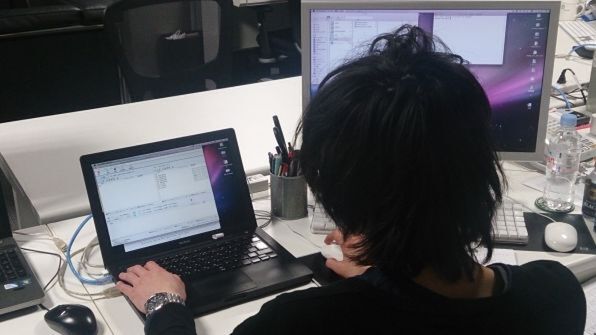
レンダリングの作業風景
実現のためには、日本のネットのインフラが大幅に改善されることがポイントになります。しかし、通信インフラの技術も進歩してきているので、まったく絵空事だったことが現実に近づいてきていると思います。
――スマートフォン(スマホ)で4K映像を見るようになるか。
現状のスマホでは、2K映像と4K映像の違いが肉眼ではほとんどわかりません。ただ、タブレット端末とスマホ端末の棲み分けが微妙になってきていて、タブレットが小さくなり、スマホが大きくなってきています。個人的には、スマホが小型タブレットと置き換わるのではないかと思っているんです。そのサイズで映像を見ると、4K映像と2K映像の違いも明確になる。4Kコンテンツをスマホ用にエンコードできるビジネスも将来的にはやっていきたいですね。
「通信網の帯域幅はムーアの法則の3倍の早さで拡大する」という「ギルダーの法則」を提唱したのは、経済学者のジョージ・ギルダーだ。彼は著書「テレコズム」にて、次のようにも言っている。「使いすぎを気にせず、帯域幅を極限まで利用する企業が繁栄する」——例えばドワンゴは、16和音専門の着メロサイト「いろメロミックス」、ストリーミング放送「パケラジ」、そして「ニコニコ動画モバイル」と、通信帯域の増加に応じたモバイルの新サービスを繰り出し、成長してきた。
東映ラボ・テックの視線の先にあるのも、「ギルダーの法則」が予測する、将来の通信帯域の拡大で生まれるビジネスチャンスだ。アスキークラウド2014年3月号(1月24日発売)では、「ギルダーの法則」をはじめとするクラウドコンピューティングの法則・概念を取り入れた急成長企業の「成功法則」に迫る。





































