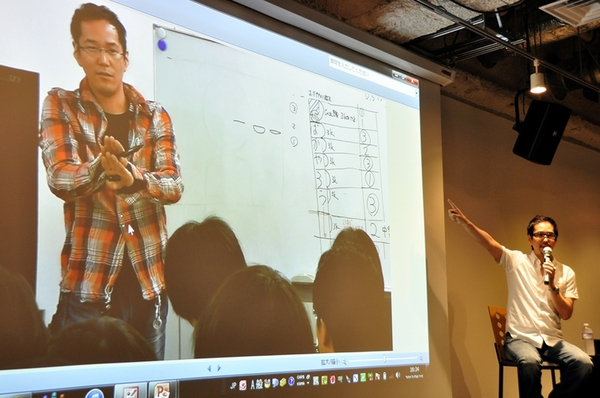まつもとあつしの「メディア維新を行く」 第38回
サンジゲンハリウッド始動&松浦社長インタビュー
アニメを3Dで作る是非―日本のアニメ表現にこだわることにこそ未来あり
2013年08月06日 11時00分更新
プロダクション I.G 神山監督と1カットずつ“開発”する日々

サンジゲン代表取締役 松浦裕暁氏

『009 RE:CYBORG』プロデューサー 石井朋彦氏

『009 RE:CYBORG』監督 神山健治氏
まずサンジゲン代表取締役の松浦裕暁氏より、自身の独立から『009 RE:CYBORG』制作に至るまでの経緯が紹介された。
松浦氏はCGを活用したアニメスタジオとしてその名を馳せていたGONZO出身。当時のアニメ制作は、セル(2D)パートと、3Dパートが明確に分れており、松浦氏は後者を専門に腕を磨いた。その後、GONZOを辞め、2006年にサンジゲンを設立。
ペプシコーラのコマーシャル映像などキャラクターも含めアニメの全パートを3Dで作りきる「フル3Dアニメ」を手がけていく。
そこに、サイボーグ009の新作劇場作品を手がけることになったプロダクション I.Gの石井朋彦プロデューサーが相談を持ちかける。
新作では3D立体視ありきの上映が前提条件となっており、従来のセルアニメの手法では一定のクオリティーを保つことが難しかったからだ。
もちろんプロダクション I.Gでも『攻殻機動隊 S.A.C.』シリーズに登場する「タチコマ」などのメカを3Dで表現してきたが、キャラクターすべてを手がけた経験はなかった。
石井プロデューサー曰く、「国内の制作会社を何社も回ったが、これまでの、トゥーンレンダリングの範囲内でセルっぽく見せるというものがほとんどだった。そんななかサンジゲンの『迷い猫オーバーラン』の次回予告を見せてもらい、ひっくり返りました。すぐに連絡して一緒にやろうということになりましたね」。
ちなみにサンジゲンの作品では、セルアニメらしくみせるために、3Dモデルに後から影を書き足すといった技法が使われているという。
制作パートナーを石井プロデューサーと共に探していた神山健治監督も、「手描きのパートと3Dがシームレスに融合されていて非常に驚きました」と振り返る。
一方、2人の訪問を受けた松浦氏は、さっそくアニメーションディレクターを務める鈴木大介氏と共に、009の登場人物である島村ジョーとフランソワーズをわずか数日で制作。
まだ顔だけの状態だったが、神山監督は劇場版制作に必要な表現がすでに実現されていることにあらためて驚かされる。「キャラを3Dでどれだけ表現できるか注目して欲しかった」という松浦氏の狙い通りの結果となったのだ。そこからTVアニメ『ブラック★ロックシューター』のスタッフがそのまま移行する形で『009 RE:CYBORG』の制作がスタートする。
サンジゲンはもちろん、神山監督にとっても、計1200カット以上に及ぶ劇場アニメすべてを3Dで制作するのは初めての体験。
セル2Dの場合、監督とアニメーターによる打ち合わせ後、監督はアニメーターから上がってくるカットを“チェック”するが、描き上げたアニメーターとマンツーマンで確認することはない。
しかしフル3Dである本作は、監督も現場に半年以上張り付きになり、各担当アニメーターと1カットずつ“開発”していく日々だったという。モデリングデータ、ライティング、各種エフェクトなどをその場で調整できるフル3Dアニメならではの手法と言える。
神山監督は、「例えば口パクや歩く・走る所作などの芝居をキャラクターに付けてみて試し、調整を繰り返していった。3Dについては我々が学びつつ、サンジゲンのスタッフに対してはセルアニメの作画の技法を伝えていきました」と言う。
松浦氏も、「技法については頭で『すでにわかっている』と思い込んでいた部分も正直大きかった。プロダクション I.Gと密に仕事をすることで、あらためて身に付けることができた」と明かす。
じつはこの部分こそが、日本のアニメが3D制作の時代になっても世界のライバルに打ち勝っていくことができる理由だ、というのが今回登壇した三人の共通見解だ。
■Amazon.co.jpで購入
迷い猫オーバーラン!第1巻 〈初回限定版〉 〈Blu-ray〉ジェネオン・ユニバーサル

この連載の記事
-
第102回
ビジネス
70歳以上の伝説級アニメーターが集結! かつての『ドラえもん』チーム中心に木上益治さんの遺作をアニメ化 -
第101回
ビジネス
アニメーター木上益治さんの遺作絵本が35年の時を経てアニメになるまで -
第100回
ビジネス
『THE FIRST SLAM DUNK』で契約トラブルは一切なし! アニメスタジオはリーガルテック導入で契約を武器にする -
第99回
ビジネス
『THE FIRST SLAM DUNK』を手掛けたダンデライオン代表が語る「契約データベース」をアニメスタジオで導入した理由 -
第98回
ビジネス
生成AIはいずれ創造性を獲得する。そのときクリエイターに価値はある? -
第97回
ビジネス
生成AIへの違和感と私たちはどう向き合うべき? AI倫理の基本書の訳者はこう考える -
第96回
ビジネス
AIとWeb3が日本の音楽業界を次世代に進化させる -
第95回
ビジネス
なぜ日本の音楽業界は(海外のように)ストリーミングでV字回復しないのか? -
第94回
ビジネス
縦読みマンガにはノベルゲーム的な楽しさがある――ジャンプTOON 浅田統括編集長に聞いた -
第93回
ビジネス
縦読みマンガにジャンプが見いだした勝機――ジャンプTOON 浅田統括編集長が語る -
第92回
ビジネス
深刻なアニメの原画マン不足「100人に声をかけて1人確保がやっと」 - この連載の一覧へ