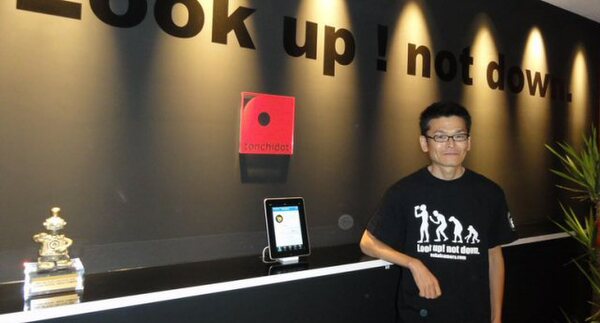頓智ドット株式会社 近藤純司CTOが語る
完成度2%──セカイカメラはまだ50倍進化する!
2010年12月01日 09時00分更新
セカイカメラを起動して、iPhoneやAndroidケータイなどのカメラで街を眺めると、店や施設のいたる所にユーザーや企業が用意した情報「エアタグ」が貼られているのが見える。
初めて来た街でも、「この店のもんじゃが美味しいんだ」「あそこがあの会社のオフィスなんだ」と、肉眼で眺めるだけでは得られない現実を拡張した世界が広がるのだ。
2009年9月に製品版をリリースして以来、iPhone版だけでも120万ダウンロードを超え、世界各地にユーザーによるエアタグが貼られ続けている。
この拡張現実アプリを作り出したのは、日本のベンチャー企業である頓智・。
単一アプリの成功に留まらず、セカイカメラ上で動く他社のアプリを採り入れた「セカイアプリ」計画も進めており、プラットフォームのような存在にまで進化を遂げている。
最初の構想発表からわずか2年で驚くべき展開を見せている企業なのだ。「ネットに生きる現代の匠“CTO・エンジニア”に聞く」第5回は、その頓智・で技術分野の展望を握るCTOの近藤純司氏に話を伺った。
スマートフォンの定番アプリ「セカイカメラ」
セカイカメラ。ユーザーのエアタグが見られる標準タイプだけでなく、ツイッタークライアン ト「CooKoo」やアンビションのオンラインRPG「セカイユウシャ」などのセカイアプリもラインアップを拡大している
言わずと知れたスマートフォンの定番アプリ「セカイカメラ」。iPhone版とAndroid版のほか、KDDIのEZアプリとして組み込まれた「セカイカメラZOOM」を提供している。ユーザーのエアタグが見られる標準タイプだけでなく、ツイッタークライアン ト「CooKoo」やアンビションのオンラインRPG「セカイユウシャ」などのセカイアプリもラインアップを拡大している。
UNIXからLinuxへ、LinuxからAndroidへ貪欲に技術を吸収
── まずは近藤さんのバックグラウンドを教えてください。デジタルに興味を持ったのはいつ頃ですか?
近藤 中学生の頃ですね。まだパソコンはなくて、関数電卓にベーシックなプログラミングができ始めたくらいのときでしたが、すごく興味が引かれたんですよ。
わずか1行を表示する程度のディスプレイですが、そこにプログラムを打ち込むと、命令どおりにちゃんと動くのが楽しくて。
もともと何か作ることが好きだったので、すっかりはまってしまいました。この道に進むことも、その頃から考え始めたんだと思います。
── では、就職もプログラミング方面に?
近藤 OSが作りたかったので、富士通グループのソフトウェア開発会社に就職しました。望みどおりにUNIXベースで大型コンピューターやスーパーコンピューターのOSが作れたので、仕事が楽しくて仕方なかったですね。
しかし、2000年前後にダウンサイジングの波が来て、大型機はどんどんシュリンクする時代になりました。
するとどうしても保守フェーズといいますか、だんだんと新しいモノを作らない時代になってしまいます。
そこで、今度はUNIXの延長線上にあるLinuxにモノ作りを求めました。それからしばらくしてLinuxは組み込みの世界で使われだし、対象のハードウェアはどんどん小さくなっていきました。
その行き着いた先に、Androidがあったというわけです。
井口尊仁CEOと出会い、セカイカメラ実現に向けて走り出す
── 頓智・への転職も、やはりAndroidがキーになったんですか?
近藤 そうですね。CEOの井口は、2008年9月にTechCrunch50でコンセプトを発表して以来、色々なところでセカイカメラをアピールしていました。
その講演を聴きにいったのが2008年11月。講演後に話す機会があって、「今僕はAndroidをやっているんですよ」と伝えたら、「Androidって何?」と興味を持ってくれて。そこから一緒にやってみるということになりました。
── プロトタイプはiPhone版でしたが、そちらのプラットフォームの腕も持っていたんですね。
近藤 いや全然(笑)。まったくやっていなかったので、そこから勉強しましたね。まだ頓智・は数人しかいなくて、実質2人でプログラムを書いたりしました。実践しているうちに覚えていった感じです。
── その後、2009年9月にiPhone版、2010年6月にAndroid版のセカイカメラをリリースされましたね。技術的な苦労はありましたか?
近藤 おかげさまで、iPhone版は公開から4日で10万ダウンロードをしていただいて嬉しかったですね。
技術的なところに関しては、iPhone版もAndroid版も実行環境がまったく違うので、それぞれで苦労するところがありました。
たとえば、AndroidはJavaで動いているので、ある意味冗長になりやすいんです。しかも3Dグラフィックスを素早く表示するために、色々な問題をクリアしなくてはなりませんでした。

この連載の記事
-
第7回
ビジネス
疲れないゲーム「モバプロ」を支えるプログラマー -
第6回
ビジネス
共同購入のグルーポン、圧倒的強さの秘密をCTOが語る -
第4回
ビジネス
「30min.」はなぜスパムが混ざらないのか? -
第3回
ビジネス
2000年に慶應版「Facebook」立ち上げた文系女子 -
第2回
ビジネス
理想のコミュニティ像を追い続ける、マインドスコープ藤川氏 -
第1回
ビジネス
ライフレシピで人生をハッピーに、ロケットスタート和田CTO - この連載の一覧へ