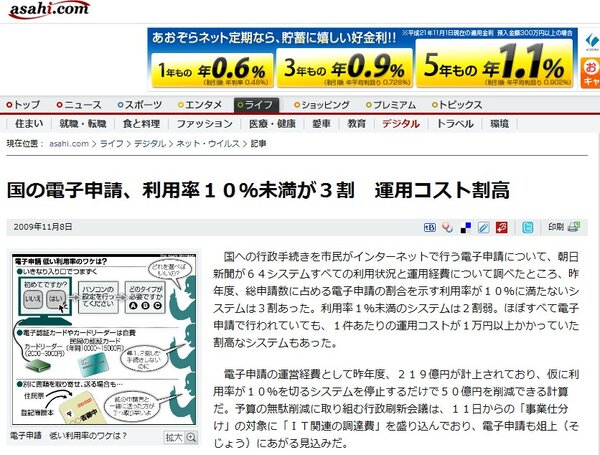「利用率1%」も珍しくない電子申請
今週日曜の朝日新聞の1面トップで「国の電子申請、利用率10%未満が3割」という記事が出た。その内容は、私が経済産業研究所に勤務していたとき開催したシンポジウムなどでも指摘したことで、私もコメントした。特に大きな問題は、申請の方法が複雑で各省庁バラバラになっていることだ。
利用率が低い最大の原因は、ITというキャッチフレーズさえつけば予算がつくというので、各省庁が縦割りでシステムを構築したため、高価で非効率な大型コンピュータ中心のレガシーシステムになっていることだ。それも経産省は富士通、総務省はNTTデータというように「御用達」の業者が決まっており、大学などをダミーにして一般競争入札を避けて出入り業者に随意契約で発注するやり方がまかり通っている。
こうしたITゼネコンが役所を食い物にする手法は、銀行のオンラインシステムと同じだ。最初は「1円入札」のように安値で落札し、システムの増設は自社でないとできないようにコテコテにカスタマイズして囲い込み、高価なシステムをいつまでも売りつける。ある担当者によると、こういうやり方を「シャブ漬け」といい、これを巧妙にやるのが営業の腕だという。
では悪いのはITゼネコンかといえばそうではない。顧客の無知につけ込んで(合法的な範囲で)高値で売るのは、企業努力として当然だ。悪いのはコスト意識なしに高価なシステムを随契で調達するキャリア官僚である。その原因は、彼らが2年ぐらいで転々とポストを変え、ITについての専門知識もないからだ。このため新しい課長になるたびに出入り業者が「ご進講」に及び、そのときさりげなく自社でしかできないシステムを売り込むのだ。
これを防ぐには、官僚のローテーションを改めて専門知識をもつとともに、各省庁に情報システムの責任者を置いて外部のコンサルタントなどによって客観的評価を行なうべきだ――というのが7年前のシンポジウムで多くの出席者が指摘したことだ。この点はさすがに少し改められ、各省庁にCIO(最高情報責任者)が置かれるようになった。それなのに「全体の2割が利用率1%」という状態になるのはなぜなのか。

この連載の記事
-
最終回
トピックス
日本のITはなぜ終わったのか -
第144回
トピックス
電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -
第143回
トピックス
グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -
第142回
トピックス
アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -
第141回
トピックス
ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -
第140回
トピックス
ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -
第139回
トピックス
電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -
第138回
トピックス
原発事故で迷走する政府の情報管理 -
第137回
トピックス
大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -
第136回
トピックス
拝啓 NHK会長様 -
第135回
トピックス
新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ