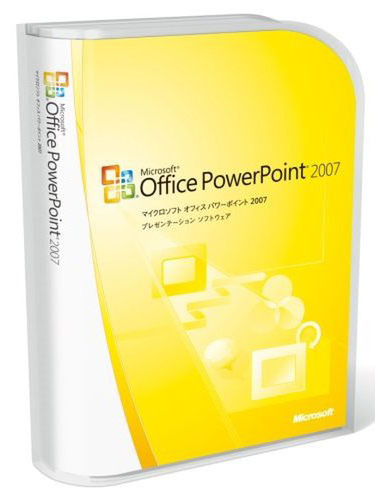買い増しのムダ、買いすぎのムダを低減
それではボリュームライセンスの導入によって、どのぐらいコストに差が出てくるのだろうか。導入形態によっても異なるが、以下のような考え方ができると福富氏は話す。
「段階的に2~3回ハードを入れ替えるような、長期的な運用では特にメリットがあると言えるでしょう。マイクロソフトとしても、運用期間の長いビジネス製品に関してはボリュームライセンスの導入を推奨しています」
「また、プレインストールモデルで提供されているOffice Personalで利用できるのは、Excel、Word、Outlookのみです。実際にはPowerPointやAccessといったソフトを別途追加で購入しているケースが多く、これらを標準で含む『Office Standard』や『Office Professional』といったパッケージに比べ割高となってしまいます」
もうひとつ重要なのはソフトウェアの買いすぎを防げる点だ。購買担当者が複数の部署にまたがっている場合でも、全社で情報を一元化できる。導入規模によっても異なるが、「数十台の規模になると一元化の必要性があるのではないか」(福富氏)としている。
これまでは、50台を超すような導入を中心にマーケティング活動を実施してきたが、ここ数年それ以下の規模でも案件が増えており、選択肢の一つとして提案を進めているとのことだ。
ボリュームと聞くと大規模な導入を想像してしまいがちだが、Open Licenseというプログラムを利用すると、3台以上の小規模から導入できる。もちろん価格もパッケージを個別に購入するより安価だ。
パソコンを普段購入しているディーラーや、コピー機器などを扱っているリセラーに加え、ヨドバシカメラやヤマダ電機といった量販店の法人窓口などでも購入が可能で、入手に対する敷居も低いと言える。
製品で性格の異なるボリュームライセンス
ボリュームライセンスは、OS(Windows)など、さまざまな製品で提供されているが、その位置付けは、オフィスソフトとは若干異なるようだ。
例えば、OSの場合、OEMでPCメーカーに提供したものを利用するケースがほとんど。ボリュームライセンスはアップグレードライセンスという位置付けだ。オフィスソフトとは異なり、PC本体にひもづけて管理したほうが分かりやすいためだという。具体的には、プレインストールされていたWindows Vistaをこれから投入されるWindows 7にアップグレードするケースなどが該当する。
またWindows Serverなどは接続するクライアント数に応じたライセンス形態になるなど製品によって若干違いがある。
なぜマイクロソフトが「パッケージではなく、ボリュームライセンスを推すのか」という点も気になる部分だ。この点に関しては、ライセンスプログラムで導入することで、ユーザープロファイルが明確になる点が挙げられるという。ユーザーの顔が見える化することで、IT化のメリットやソリューションに対する、マイクロソフトのメッセージを伝えやすくなる。企業に特化したメッセージを展開し、情報提供の機会を増やすことが目的だという。

この連載の記事
-
第45回
ビジネス
【45本目】パートナー参加でストックフォトが安くなる? -
第44回
データセンター
【44本目】無個性だけど低価格!アリスの裏メニューとは? -
第43回
ビジネス
【43本目】FAXのようにメールを送るNetSpartで通信費削減 -
第42回
ソフトウェア・仮想化
【42本目】あのDBからの乗り換えで半額に!IBM DB2という選択 -
第41回
データセンター
【41本目】モジュラー型データセンターのコスト勘定とは? -
第40回
ネットワーク
【40本目】機器のコストを下げる中古という選択肢 -
第39回
ソフトウェア・仮想化
【39本目】データ統合ツールで人海戦術を排除したら? -
第38回
ネットワーク
【38本目】1時間4.5万円で、あのテレプレゼンスが使える! -
第37回
TECH
【37本目】ウイルス対策ソフトを無料で強化する方法 -
第36回
TECH
【36本目】管理者泣かせのパッチ地獄から逃れる方策 -
第35回
サーバー・ストレージ
【35本目】アーカイブ活用でExchangeサーバーをなんと半分に - この連載の一覧へ