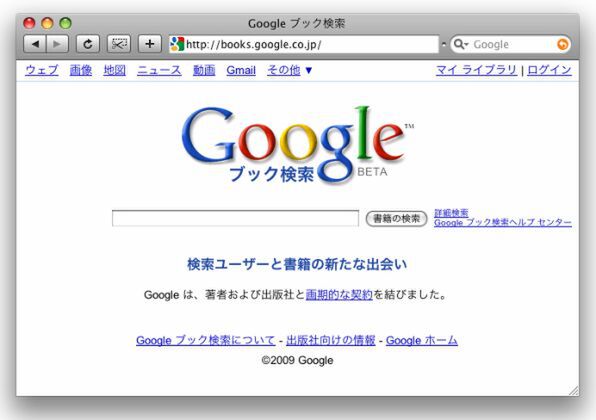このところネットや出版業界では「Googleブック検索」の和解が話題だ(関連記事)。
Google ブック検索は、その名の通りインターネット上で実際の書籍を検索できるサービスだ。グーグルが自分でスキャンしたり、出版社や著者から提供された書籍をデータベース化し、ユーザーがキーワードを入力して検索すると、その言葉が含まれる書籍がずらりと現れる。
話題になっているのは、この書籍の「著作権」だ。
グーグルは著作権者に許諾を得ずに書籍をスキャンしていたため、米国で集団訴訟(クラスアクション)を起こされて和解に至っている。そしてこの和解には、実は日本の著者や出版社も含まれている。
どうした経緯で裁判が和解に至り、なぜ日本の出版社が巻き込まれたのか。今後はどういった展開が考えられるのか。著作権に詳しい、ジャーナリストの津田大介氏に話を聞いた。
日本の出版業界も「巻き込まれた」
── これまでの経緯を簡単に教えてください。
津田:Google ブック検索は、もともと2004年秋から「GooglePrint」というサービスで展開していたものです。グーグルは、その頃から2005年にかけて世界中の図書館と連携し、主に著作権の切れた蔵書をスキャンして検索データベースに登録する作業を始めていました。
グーグルの狙いは、ネット上の情報だけではなく、書籍の情報も検索可能することで、情報検索において支配的地位を強めるところにあるのでしょう。
Googleブック検索でも、特定のキーワードで検索をかけると、その単語を含む書籍を表示してくれます。といっても、市場に流通している書籍に関しては、いきなり全ページをネットで見られるようにするのではなく、一部だけをプレビューで表示するようにしていました。2003年に先行して始まっていた米Amazonの書籍全文検索サービス「Search Inside the Book」(日本では「なか見!検索」として、2005年から開始)も意識していたのだと思います。
ただ、出版社や著者の許諾を得た上で全文検索を提供したAmazonとは異なり、グーグルは出版社や著者の許可を得ずにサービスを始めてしまった。それに対して2005年秋、米国にて全米作家協会と全米出版社協会が、著作権侵害を理由に集団訴訟を起こして、昨年まで裁判をやっていたんです。
グーグルは「ブック検索はフェアユースの範囲内のサービスだ」と主張していましたが、裁判では範囲内/範囲外という両方の意見があり、どちらに転ぶかわからない状況だった。結局、結論を出すことなく和解に至っています。
今回問題になっているのは、和解の「クラスアクション」が世界中、つまり、日本の出版社や作家にも関係していたからなんです。

この連載の記事
-
第36回
トピックス
津田大介が語る、「コルシカ騒動」の論点 -
第35回
トピックス
津田大介が語る、日本版「フェアユース」とは? -
第34回
トピックス
これはひどい? 「薬のネット通販禁止」騒動の顛末 -
第32回
トピックス
津田大介に聞く「改正著作権法で何が変わる?」 -
第32回
トピックス
なくならないネットの誹謗中傷、どうすればいい? -
第31回
トピックス
テレビ局はなぜ負けた? 津田氏に聞くロクラク事件 -
第30回
トピックス
DRMフリー化は必然──津田氏が語る「iTunes Plus」 -
第29回
トピックス
法律が現実に追いつかない──津田氏、私的録音録画小委を総括 -
第28回
トピックス
「小室哲哉」逮捕で露呈した、著作権の難しさ -
第27回
トピックス
ダウンロード違法化が「延期」していたワケ - この連載の一覧へ