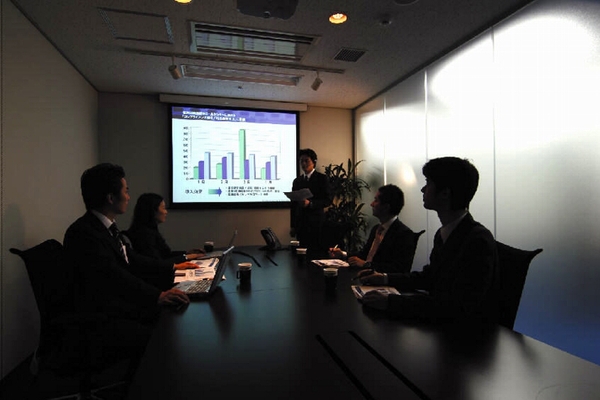今更ながら、ケータイは携帯電話であり、電話は声で話をする道具である。しかし現在のケータイは違っている。死語かもしれないが、親指族としてケータイでメールを打ちまくる様子を揶揄していた時代があったはずが、電車内のケータイマナーとして喋ることは禁じられるようになった。
しかし、今目の前にあるドコモの「らくらくホン プレミアム」は違っていた。「今、2時38分です。会議はもう少しかかりますので、次の会議を4時半からにしてもらえますか?よろしくおねがいします」とケータイに向かって喋っているのは、アドバンスト・メディア代表取締役会長の鈴木清幸氏。AmiVoiceという音声認識システムを開発・販売している企業である。
機械が人の「言うことを聞く」世界観
お邪魔したアドバンスト・メディアのオフィス内にある会議室のテーブルの上には家庭にもありそうな電話機の子機が置いてある。鈴木氏がその受話器を耳に当て、「スライド」と話しかけたかと思うと、部屋の照明が落ち、スクリーンが降りてきて、プロジェクターのランプが灯る。そしてPCのスライドショーを映し出して、鈴木氏が喋り始める。
一瞬の出来事だったが、驚きと示唆に富んだ瞬間でもあった。これが、声で機械を操る日常生活の世界なのである。
決まったルーティンの動作は、受話器に向かって喋ればよいのである。これを人の手でやろうとしても、大した苦労はないかもしれない。スライドを天井から専用の棒で引っ張りおろし、リモコンを探してプロジェクターの電源を入れ、入力を切り替える。そして部屋の電気を消しに席を立って、戻ってくる。しかしこれが毎日の会議の度に繰り返され、片付けもするとなると、大した苦労ではない、とも言えなくなってくるのではないだろうか。
人間の声で身の回りの機械を操作する、ということは、機械が人間の意志を理解して役だってくれる象徴的な動作だ。使いこなせていない機械を前にして、よく「機械に使われている」なんて言い方をするが、文字通り機械が「言うことを聞いてくれる」と、機械へのストレスも下がるし、誰にでも使いやすい道具としての存在へ近づくのだと思う。
話はそれるが、一方ではドコモのi コンシェルやauのエージェント機能など、ケータイがデータを収集してきて、人が欲しそうな情報を察して用意してくれる機能も開発が進んでいる。こちらは機械側が「データ収集」という知性を働かせて、人間をお膳立てするというアプローチだ。確かにこれらに知性を感じるほど洗練されてくるかもしれない。しかし「言うことを聞いてくれる」のとは違うのだ。

この連載の記事
-
第100回
スマホ
ケータイの“ミクロな魅力”とは、なんだったのか? -
第99回
スマホ
フォロワー計32万人の2人が語る2009年のiPhoneとメディア -
第98回
スマホ
写真で振り返るケータイ10のミクロなシーン -
第97回
スマホ
ケータイが支える、マイクロ化と遍在化するメディア -
第96回
スマホ
ノマドワークのインフラをどう整えるか? -
第95回
スマホ
冬春モデル発表会で見えた、本当に欲しいケータイ -
第94回
スマホ
デザインから考える、ケータイのこれから -
第93回
スマホ
次の自動車社会とケータイとの関係 -
第92回
スマホ
モバイルアプリを実際に作るにあたっての考察 -
第91回
スマホ
楽しい使い方は現在模索中の「セカイカメラ」 -
第90回
スマホ
iPhoneと過ごしたNYとメキシコの旅でわかったこと - この連載の一覧へ