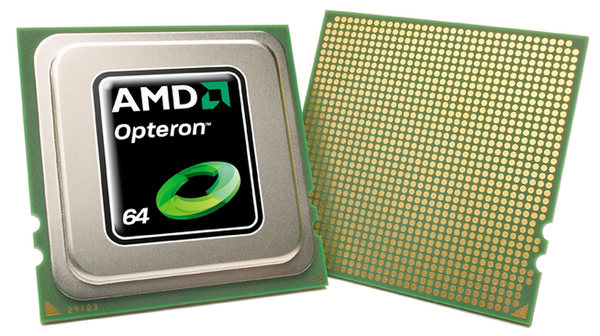コンピューターの中心であるCPUは、これまでの高クロック志向から、マルチコア志向へと大きく進化の方向性を変えた。またプロセスの微細化にともなうトランジスタ数の増加により、これまでCPUの外にあった機能も取り込みつつある。
- 第1回 5分で丸分かり! PCアーキテクチャーの基本
- 第2回 統合進化するCPUとチップセット
- 第3回 グラフィックスアクセラレーターは描画専用から汎用へ
- 第4回 メモリーの種類と転送方式を押さえる
- 第5回 低価格化著しいストレージとフラッシュメモリー
- 第6回 ワイヤレスが熱い! ネットワーク
プロセッサーと関連技術
今回はプロセッサーと、チップセットなどプロセッサーに直接関連する技術の最新動向を解説する。
最近では、PCアーキテクチャーに使われるCPUとチップセット(およびネッワークモジュール)を一組にして「プラットフォーム」と呼ぶことが多い。なぜなら、CPUとチップセットがセットになってさまざまな機能を提供しており、また、組み合せが比較的限られていて、システムのデザインがある程度規定されるからだ。
ソフトウェアについても、同一のプラットフォーム内では、ドライバなどのセットは共通のことが多く、さまざまな拡張機能、たとえばインテルのAMT(Active Management Technology。クライアントマシンをネットワーク経由で集中管理する機能)などは、プラットフォームごとに進化していく。
かつてPCのプロセッサーでは、クロック周波数を高めることで性能を向上させてきた。しかしクロック周波数が3GHzを超えたあたりで、壁にぶつかることになる。半導体の微細化が進んだ結果「スイッチオフ」の状態でも電流が流れてしまう「リーク電流」が増えてしまったからだ。リーク電流は低負荷のときも流れるので、平均の消費電力や発熱量を増大させることになり、システムとしての限界に近づいてしまった。
ところが、インテルやAMDは、より高性能な製品を作るために微細化を止めることはできない。また、プロセスの微細化によって増えたトランジスタを遊ばせることなく、有効に使う必要が出てくる。
(次ページ「電力効率と性能を両立させるマルチコア」に続く)