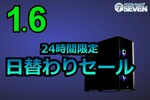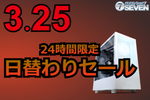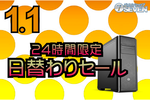裏配線の方法は事前に打ち合わせ、梱包時にはプラスドライバーも同梱?
“真心”感じるパソコンショップSEVENのBTOPC製造現場に潜入、組み立てスタッフのプロフェッショナルさに驚き!
2024年01月27日 11時00分更新
注文票には購入した方のこだわり事項も書いてある!
パソコンショップSEVENでは、注文したマシンの入金が確認できたら、さっそくパーツやケースのピックアップから始まる。注文票は在庫データとも連動しており、パーツの在庫がなくなると、カスタマイズページで選択できなくなるようになっているため、選択したパーツとは別のメーカーの製品が搭載される……なんてことも起こらない。加えて、注文票と一緒に購入した方の指定のこだわり事項やチェックリストも一緒に印刷されるとのこと。単に組み上げるだけでなく、ユーザーのこだわり事項も対応可能なことは対応するというのには、驚いた。
ピッカーと呼ばれるピックアップを担当するスタッフさんが、注文票に沿ったパーツをピックアップする。各パーツはピックアップ担当の方がわかりやすいように棚にまとめてある。また、奥にも棚があり、そこにはダンボールに入ったままの在庫パーツが保管してあった。手前の棚のパーツが少なくなってくると、ここから新たにピックアップして、手前の棚に補充するという仕組みだ。
組み立てスペースは、2ヵ所にわかれている。1つは、ケース内にパーツを組み込む作業。マザーボードにCPUやビデオカード、メモリー、ストレージを差し、CPUクーラーや電源といったパーツも取り付ける。ここまで終わると、もう1ヵ所にバトンタッチし、ケーブルの取り回しや裏配線といった細かい作業を実施したうえで、完成まで組み上げる。
前者は2人(1人が作業、もう1人がサポート)、後者は作業スペースが4つあり、それぞれに1人が担当につくといった感じだ。注文されたパーツは台車にまとめられており、そこからパーツをピックアップしてケースに組み込んでいく。取材をしていた時間はあまり長くなかったが、それぞれスタッフさんは作業中に相談をすることもなく、スタンドアロンで黙々と作業されているのが印象的だった。
ケーブルの取り回しは事前に相談
“いかに表面に余計なケーブルがないか”にコダワリ
ここで疑問に思うのが、自動で組み上がるわけではなくスタッフさんが1台1台丁寧に組み上げていくなかで、ケーブルの取り回しや裏配線についてスタッフさんによって違いがあるのかという点だ。
この点を聞いてみると、ケースを採用するかしないかの段階から、組み立てスタッフの意見は取り入れられており、無茶な組み方にならないようにしっかりと話し合っているのだという。その際に、組み立てスタッフ同士でラジエータやケーブルの取り回しのルール決めを行なう。それによってスタッフさんによって仕上がりに違いが出ないようにしているそうだ。
パソコンショップSEVENには何度もレビュー機のインタビューのために取材に伺っているが、その際に組み立てスタッフさんのお話を聞くことも少なくない。例えば「組み立てスタッフによるとこのケースはとても組みやすい」「ファンがとても多いので、組みたてが結構大変だ」というような内容だ。
同社の組みたてスタッフの皆さんは経験豊富なベテランぞろいで、ケーブルの取り回しや裏配線などについてのコダワリもかなり強く、新モデルを作る際にも多くの意見が取り入れられている。こういったやり取りがあるため、パソコンショップSEVENのBTOパソコンは、かなりキレイにケーブルがまとめられており、表面に余計なケーブルが出ているということがないというわけだ。
テストに一番時間を要する
パソコンが組み上がってからが一番長い工程になる。チェックリストを使用して、クオリティチェックを行なう。まずは自身の最終チェックに加えて、もう1人のスタッフさんにも確認してもらうダブルチェックを実施し、内部の組付けのミスがないか、製造ルールが守られているかを確認する。次に動作確認部門がパソコンを引き継ぐ。テストスペースに設置されさまざまなテストが開始される。ここでは、OSを始めとしたソフトがしっかり動作するか、各種ポートは問題なく起動するかなどがテストされている。
テストにはパーツ単位の事前テストを除いてだいたい5~6時間かかり、大型のモデルになってくるとまる1日24時間以上テストに時間をかける場合もあるとのことだ。主な内容は、OSの正常動作確認、ドライバーインストールテスト、ウェブ接続テスト、USB全ポート認識テスト、エージングテスト、CPU(CINEBENCH)・GPUストレステスト(3DMark、ビデオカード搭載モデルのみ)、ストレージ動作テストなどなど。
組み上がったマシンはテストスペースに設置され、テスト担当のスタッフさんが1台1台テストを実施していく。取材する前は、テストは自動でやっているのかなと予想していたが、スタッフさんが1つ1つ目視確認で行なっているということを知り、驚いた。