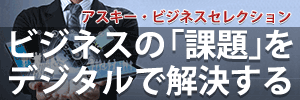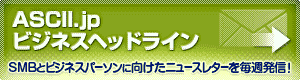東北大学と浜松医科大学の共同研究チームは、1歳時におけるスクリーンタイム(画面を備えたデバイスの使用に費やされた時間)と、2歳時および4歳時における5つの発達領域での発達特性との関連を解析。その結果、スクリーンタイムの長さと、2歳時および4歳時点でのコミュニケーション領域および問題解決領域の発達特性が特異的に関連していることが明らかになった。
東北大学と浜松医科大学の共同研究チームは、1歳時におけるスクリーンタイム(画面を備えたデバイスの使用に費やされた時間)と、2歳時および4歳時における5つの発達領域での発達特性との関連を解析。その結果、スクリーンタイムの長さと、2歳時および4歳時点でのコミュニケーション領域および問題解決領域の発達特性が特異的に関連していることが明らかになった。 研究チームは今回、東北メディカル・メガバンク計画三世代コホート調査に参加している7097人の子どもを対象に、1歳時のスクリーンタイムと、2歳時および4歳時の5つの発達領域における発達の遅れの有無との関連を調査した。 スクリーンタイムは保護者による1歳時調査票の回答に基づき評価し、1日あたり、1時間未満、1~2時間未満、2時間~4時間未満、4時間以上の4群に群別した。5つの発達領域は、コミュニケーション、粗大運動、微細運動、問題解決、個人・社会で構成。領域ごとに点数を集計し、個人の合計点数が平均マイナス2標準偏差以下の得点だった場合「発達が遅めである」と定義した。 調査の結果、1歳時でスクリーンタイムが1時間未満の子どもと比較して、スクリーンタイムが4時間以上の子どもでは、2歳時、4歳時のコミュニケーション領域における発達の遅れがある割合がそれぞれ4.78倍、2.68倍と推定された。さらに、2歳時、4歳時の問題解決領域の発達の遅れがある割合が、それぞれ2.67倍、1.91倍と推定された。 研究チームは今回の結果について、長いスクリーンタイムが発達の違いの原因なのか結果なのかはわからず、発達の領域別に検討する必要があるとしている。スクリーンタイムの制限を推奨するものではないという。研究論文は、小児科学の専門誌ジャマ・ペディアトリックス(JAMA Pediatrics)に2023年8月21日付けでオンライン掲載された。(中條)