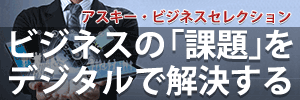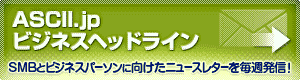理化学研究所と東京大学らの国際共同研究グループは、量子計算のための光電場の非線形測定を初めて実現した。同研究成果により実現した測定は、光を使った量子コンピューター(光量子コンピューター)において汎用的な量子計算を可能にする非線形計算に相当し、誤り耐性型汎用光量子コンピューターの基礎原理となることが期待される。
理化学研究所と東京大学らの国際共同研究グループは、量子計算のための光電場の非線形測定を初めて実現した。同研究成果により実現した測定は、光を使った量子コンピューター(光量子コンピューター)において汎用的な量子計算を可能にする非線形計算に相当し、誤り耐性型汎用光量子コンピューターの基礎原理となることが期待される。 光量子コンピューターでは、パルス列状に飛んで来る光の量子状態の変化と補正をしながら計算する「測定型量子計算」の手法がすでに開発されている。この計算手法では、測定の種類と精度が量子操作の種類と精度に対応しており、これまでに光電場の加減・定数倍操作に相当する測定はできていたが、「掛け算」操作に相当する非線形測定は実現していなかった。 研究チームは今回、電気-光のフィードフォワード制御をデジタル回路により柔軟かつ高速に実行する手法を考案。その手法を用いた制御系と非線形スクイーズド光(非線形項の量子ゆらぎが圧搾された光)を組み合わせることで、非線形測定の原理実証に成功した。提案手法では柔軟な制御が可能であえるため、別の補助量子光(測定対象となる光に干渉させる光)と組み合わせれば、誤り耐性型汎用量子計算にも利用できるという。 非線形測定の基礎的な手法は2001年に提案されたが、非線形計算を電気的に実行する際にかかる時間が長いなどの問題があり、これまで実際の測定はできていなかった。同チームは、フィードフォワード制御中の測定結果に対する非線形計算において、ルックアップテーブルと呼ばれる計算表を用いる手法を提案。測定系・制御系における入出力処理のため専用ボードを作成することで、この問題を解決した。 研究チームはさらに、構築した実験系の評価として、27通りの強度・ランダムな位相を持つ弱いレーザー光を216万通り、測定対象として入力することで、入力した光と測定結果の関係を検証。構築した実験系が目標としていた非線形測定となっていることを実証した。研究論文は、オンライン科学雑誌ネイチャー・コミュニケーションズ(Nature Communications)に2023年7月12日付けで掲載された。(中條)