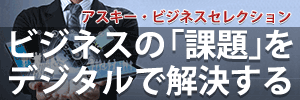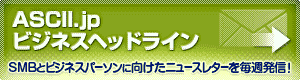慶應義塾大学の研究チームは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の1000例規模の症例を対象とする多施設共同調査研究を実施。診断12カ月後でも約3分の1の人に一つ以上の症状が残存することがわかった。
慶應義塾大学の研究チームは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の1000例規模の症例を対象とする多施設共同調査研究を実施。診断12カ月後でも約3分の1の人に一つ以上の症状が残存することがわかった。 同研究チームは、全国27施設において、2020年1月から2021年2月末日までに新型コロナウイルス感染症と確定診断されて入院加療を受けた8歳以上の約1000人を対象に、入院中、診断3カ月後、6カ月後、12カ月後にわたり、罹患後によくみられる24項目の症状の有無についてアンケート調査を実施。併せて、国際的に使用されている各種質問票を用いて、健康に関連したQOL(生活の質)への影響に関しても調査した。 その結果、何らか一つ以上の症状を認めた人の割合は、時間の経過とともに統計学的有意に経時的に低下していたが、診断から12カ月経過した後も約3分の1の人に何らか一つ以上の症状が残存していることが確認された。さらに、診断後3カ月の時点の解析で罹患後症状が1つでも存在すると、健康に関連したQOLの低下、不安や抑うつ傾向の増加、新型コロナウイルスに対する恐怖感の増長、睡眠障害の増悪、労働生産性の低下などの影響があることが判明した。 同研究は、日本における新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に関する過去最大規模の調査であり、経時的に、退院までに認めた症状、3カ月後、6カ月後、12カ月後と長期にわたり罹患後症状を検討した初めての報告である。各罹患後症状の有症状の比率だけでなく、国際的に確立された各種質問票を用いており、多面的で定量性が高く、比較解析が容易な報告である点でも国内では初めての調査になる。(中條)