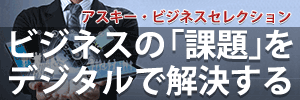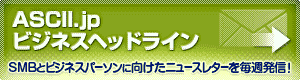モバイルコマースの台頭や購買方法の多様化がもたらす課題、「小売業界のテクノロジー改革調査」発表
現在の買い物客は小売業者が考えるほど満足していない ―ゼブラ調査
2022年02月25日 07時00分更新
ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパンは2022年2月24日、「小売業界のテクノロジー改革に関するグローバル調査」の結果を発表した。同調査からは、買い物客と小売業者の間で「満足度」や「信頼度」に対する認識に大きなギャップがあることが浮き彫りになっている。同社社長の古川正知氏は「買い物客と小売側の認識ギャップは、テクノロジーの活用を通じて解決することが急務」だと指摘している。
パンデミックの収束後も“ハイブリッド”な購買行動が続く
米ゼブラ・テクノロジーズ(ZEBRA Technologies)は、世界最大手の自動認識機器メーカー。世界45カ国に128のオフィスを展開しており、グローバルの売上高は44億4000万ドル、従業員数は8800人以上。RFIDやハンディリーダー、モバイルコンピュータ、バーコードスキャナー、ラベルプリンタなどの製品を、運輸、物流、小売、製造、医療分野の顧客に提供している。日本では1998年からビジネスを展開しており、2014年10月にモトローラソリューションズのエンタープライズ事業部門を買収、ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパンを設立した。日本市場向けに開発した倉庫/製造向けデバイスも提供している。
小売業界のテクノロジー改革に関するグローバル調査は、同社が定期的に実施ている調査であり、今回で14回目となる。今回は2021年6月~7月、北米やアジア太平洋(日本を含む)、欧州、中南米、中東の各地域において、買い物客4000人、店舗従業員650人、小売業経営層450人の合計5110人を対象に、米調査会社のAzure Knowledge Corporationが聞き取り調査を実施した。
冒頭で触れたとおり、今回の調査からは、買い物客と小売業者の間での大きな認識差、ギャップが明らかになっている。たとえば、オンラインショッピングの注文を買い物客の指定どおり処理することについて、小売業経営層の55%は「買い物客から全面的な信頼を得ている」と自負しているが、実際に全面的な信頼を寄せている買い物客は38%にとどまる。さらに、店舗従業員でも信頼できると考える人は51%で、雇用主である小売業経営層ほどは信頼を寄せていないことがわかった。
パンデミック収束と購買行動の変化についても調べている。69%の買い物客が実店舗を持っているオンライン小売業者での買い物を希望しており、また64%の買い物客はパンデミックの収束後には実店舗での買い物を増やしたいと考えていることから「客足は実店舗に戻りつつある」と分析する。ただし、「店舗での滞在時間を短くしたい」と考えている購買客は7割を超えており「コロナ禍以前の購買行動には戻らない」とも指摘している。
さらに、ミレニアル世代とX世代の購買客は、フィジカルとデジタルがシームレスにつながる“フィジタル”を指向しており、実店舗とオンラインストアが融合したシームレスな買い物体験を求めていることもわかっている。
実店舗/オンラインがシームレスに融合することで生じる課題
古川氏は今回の調査結果から、小売業には「モバイルコマースの台頭」「流通経路の多方向化」「購買方法の多様化」という3つの課題があることを指摘する。
まず「モバイルコマースの台頭」は、買い物客からオンラインと実店舗のさらなる融合が強く求められている状況を指す。
今回の調査では、実店舗とオンラインの境界線がなくなることを希望している消費者が69%に達すること、買い物客の58%は店舗従業員に尋ねるよりも自分のスマートフォンで必要な情報を探すほうが効率的だと考えていることがわかった。
「買い物客は、店頭で購入するか、オンラインで購入するかの区別はなく、買い物の途中でも、店頭からオンラインに問題なく切り替えている。ミレニアル世代の74%と、X世代の73%は、実店舗とオンラインショッピングの融合を求めている」(古川氏)
買い物客のスマートフォン利用も定着している。50%が店舗情報の閲覧に、46%がセールやプロモーション、クーポンの確認に、39%がオンライン上での製品の閲覧にスマートフォンを利用しており、「モバイルコマースは、新しいeコマースになっている」(古川氏)と語る。
加えて古川氏は「オンラインの便利さを、店舗にも持ち込みたいニーズが高い」と指摘する。たとえば、60%の買い物客は店舗やカーブサイド(ドライブスルー方式)、ロッカーなど、通常とは異なる場所での商品受け取りができる小売業者から購入したいと考えているという。「今後は、オンラインストアと実店舗におけるシームレスなサービスを提供することが求められる」(古川氏)。
こうしたモバイルコマースの台頭も背景として、2つめの「流通経路の多方向化」という課題が生じている。
eコマースやスマートフォンの浸透によって、買い物客はいつでもどこでも望みどおりに買い物ができるようになったが、その結果、小売業者側ではサプライチェーンが複雑化している。買い物客が望む手段で迅速に商品を提供するためには、店舗、倉庫、製造拠点のすべてのポイントで在庫を把握しておく必要があるためだ。
実際、買い物に店舗を訪れたものの、1つも商品を手にしないまま店舗を出た経験を持つ買い物客は71%に達しており、そのうち49%が「品切れだった」ことを理由としている。しかし、小売業経営層の87%、店舗従業員の75%は「商品の品切れを常時、リアルタイムで可視化することは非常に難しい」と考えており、経営層の84%、従業員の73%は「もっと優れた在庫管理ツールが必要だ」と回答している。
在庫切れをリアルタイムで可視化できる在庫管理ツールに対するニーズは、食料品店で90%、量販店で82%、ドラッグストアで82%、コンビニエンストアで80%に達する。「サプライチェーン全体のリアルタイム在庫管理、在庫の可視化により、買い物客と店舗従業員の満足度を向上させることが必要だ」(古川氏)。
3つめの「購買方法の多様化」では、とくに返品による現場の混乱を指摘した。買い物客の10人中8人は、通販でも実店舗でも、購入したところに簡単に返品できるほうがよいと考えている。しかし、小売店における返品管理はオンラインとオフラインのチャネルが融合することで大きな課題となっており、店舗従業員の67%、経営層の86%は「オンラインで受注した商品の返品受付や返品管理が組織にとって大きな課題」だと認識している。この比率は、前年調査よりも増加しているという。
「商品の流れと返品の流れは、決してシームレスではないプロセスとなっている。オンラインで購入した商品の店舗への返品ニーズの増加に対して、店舗における返品処理プロセスを簡素化、改善する必要がある」(古川氏)
店舗従業員もテクノロジーの活用に前向き
こうした小売業の課題に対し、ゼブラ・テクノロジーズではテクノロジーの導入による解決を提案する。
「店舗従業員の間では、最大の不満である在庫問題がますます負担になっている一方で、ロボットが業務の増強に役立つとの期待も高まっている。店舗従業員の70%は『テクノロジーの利用が満足度を高めることにつながる』と見ており、テクノロジーに仕事を奪われるという考え方が薄まって、テクノロジーの活用に前向きになっている」(古川氏)
今回の調査では、店舗従業員の7割以上が「より良い顧客体験の創出に役立つ」と答えたテクノロジーとして、「在庫のリアルタイム可視化」「店舗従業員スケジュール管理」「タスク管理ソフトウェア」「接触追跡アプリケーション」が挙がっている。
タスク管理ソフトウェアについては、すでに50%の小売店で導入されており、今後5年以内には98%が導入すると回答している。ただし「日本においてはこれからの導入になる」(古川氏)。また、価格確認やバーコードスキャン、在庫確認などの業務でウェアラブルデバイスを活用することで顧客体験が向上すると考える従業員は69%に達している。
また、店舗従業員が考えるモバイルデバイスのメリットとしては「正しい価格を検索する」「製品を探す」「お客様の質問に答える」が上位に挙がり、経営層の8割以上が、スマホやハンドヘルド型バーコードスキャナーなどのモバイルデバイスを、今後1年以内に導入する計画だと回答している。