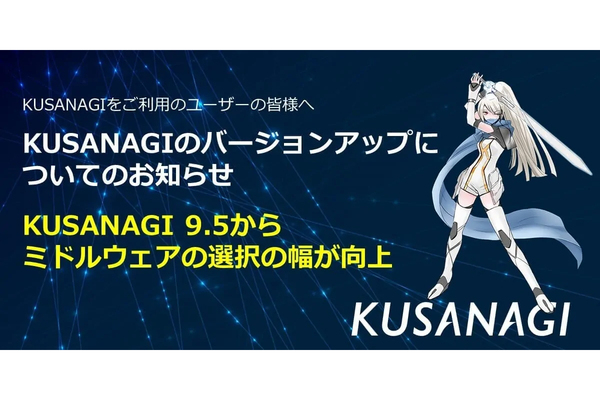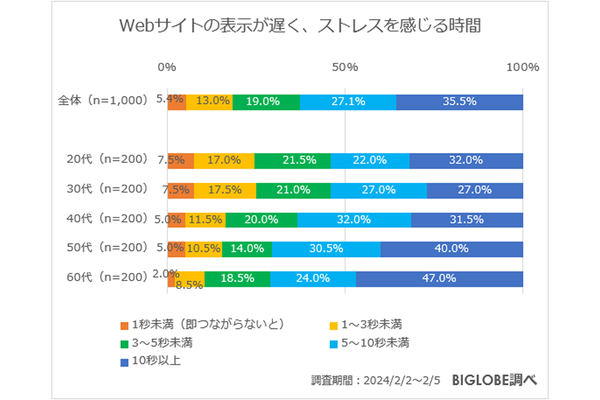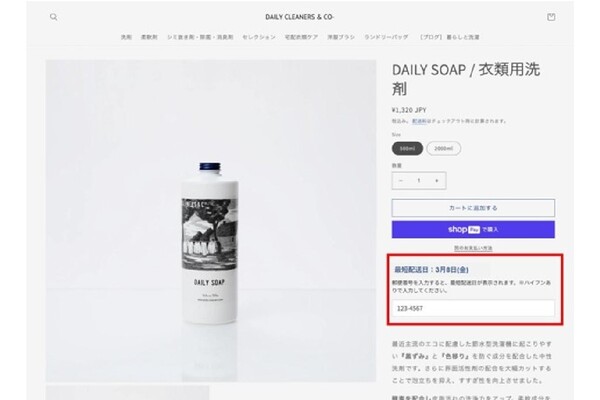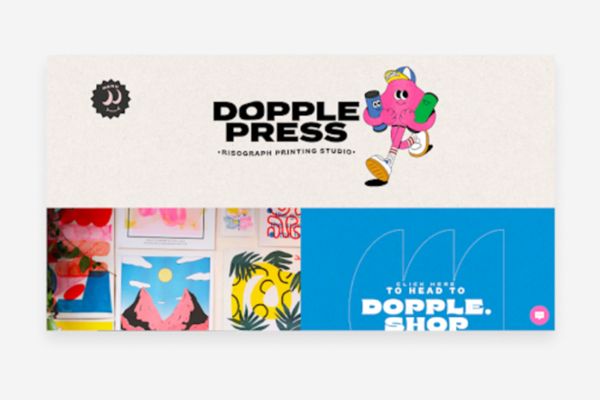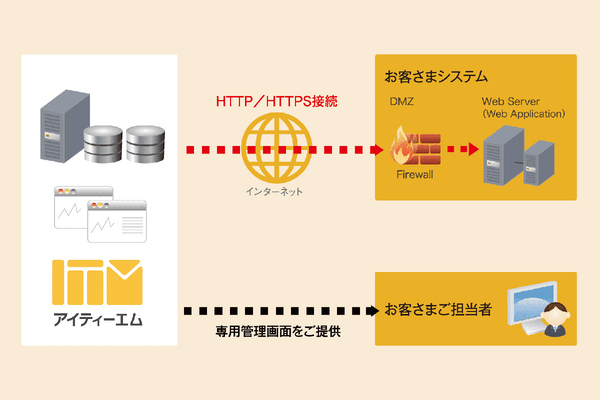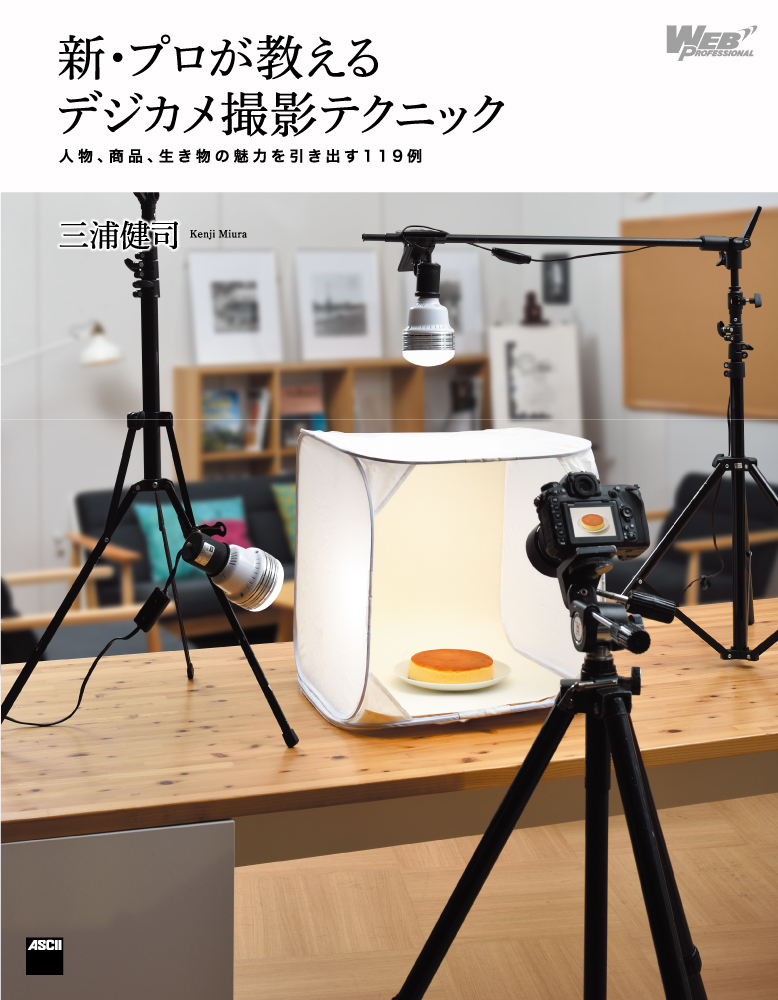先日、Twitter にてパンダアップデート4.1の傾向と対策の記事を書きますとツイートしつつ、本日現在まで公開していませんでした。書こうと思ったものの、次の理由で取りやめとしました。
- パンダアップデートのページ品質判断の仕組みは複雑過ぎる、一般化不可能
- どれだけパンダの研究をしても最終結論(アクション)は「ユーザーのために良いコンテンツ、良いサイトをコツコツ作れ」以外に言えない
- SEOの代理店側の人間は個人的な興味で知っていても良いが、少なくとも世間一般のSEO担当者が知る必要はない
- 情報処理コストを考えたら、むしろ「伝えない」方が世の中のために良い
- 文章でインターネットに公開するには適当な話題ではない
重要なことは2点目です。長らく実務をやって来た経験から、個人的には「最終アクションが変わらないなら、どうでもいいじゃないですか」というのが持論です。SEO 大好き、検索エンジン大好きという方は(私もそうですが)Googleアルゴリズムにはすごく興味がありますし、辻大先生のようにゴハン食べなくてもSEOで生きていける人もいることでしょう。でも、実務(現場での具体的なアクション)に何ら影響しない、情報処理コストと比較してあまりにメリットが小さいようなものは、逆に知らない方がいいと思います。知っているからこその弊害もあるのです。
とりわけパンダアップデートはここ3年ほど大きなアップデートされる度に様々なデータを眺めて仮説を立てていますが、正直、最終アクションは変わらない、「ユーザーエクスペリエンス」考えつつコンテンツ作り続ければ最後に到達する場所は同じであることに気がついたので、あまり興味関心の高い分野ではありません。
とはいえ、SEOサービスを提供する会社に勤めている人間ですので、業務としてそれなりの分析はしています。していますが、上記の通り「細かな説明をしたところで、だから何?」的な側面も多いのです。私の立場で「だから?」と思う内容を、一般的なインハウスSEO担当者が知って何か業務に役立つ可能性があるかを考えると、たぶんないと思います。
パンダアップデートの考察
インターネット上には、様々な SEO に関する情報があります。日本語の記事も増えました。そうした記事を見たクライアント様から「これってどうなの?」という質問を頂くこともあります。もし明らかにおかしなもの、でも確実に相談してくるだろうといった話題に対しては、とりあえずこの場で先に説明をするようにしています。今回はその流れで、某メディアに掲載された記事が言及する『パンダアップデートにより低品質評価される原因』について。
元記事はGoogle Panda and the High Risk of Using Aggressive or Deceptive Advertisingですが、こちらの内容は、私がパンダアップデート4.1を分析した時の第1印象と全く同じです。しかし「第1印象」つまりざっくりと表面的なデータを眺めた時の所感です。でも数日考えてから、「Google はこんな単純に済ませていないでしょ」と考えて、その所感は捨ててもう一歩深い分析に踏み込むことにしました。理由は次の通りです。
第1に、上記の話の多くはページレイアウト分析に関する話題であり、パンダではないでしょうか。インタースティシャル広告は以前から順位が変わっていますよね。私も最初にデータを眺めた時に、広告とページレイアウト、ページ左右のカラムの幅に着目しました。非常に類似点がありますが、2点目で触れるようにジャンルによって傾向が異なるのです。また、ページレイアウト分析のアルゴリズムと考えた方が適当ですよね。
第2に、私の調査ではパンダアップデート4.1で影響を受けた Webページを細かに分けて行くと、カテゴリ/ジャンル毎に、傾向が全く異なることが見えてきました。例えば「eコマース」と「音楽」と「ニュースメディア」は異なる傾向がありますし、同じニュースメディアでも「通信」「ライフスタイル」「健康」「不動産」でこれまた違う傾向があります。
例えば「歴史の話」と「現代社会の問題」と「最新ニュース」はコンテンツの性格が全然違いますから、同じ判断基準で考えても上手くいかないと思いませんか?そう考えると検索ジャンルによって傾向が違うのも納得いきます。
第3に、パンダアップデートは元々オフライン処理されていたように、Google が社内で保有する他の何かのデータも使って定期的に処理をしていた、かつては検索と直接連動していない(させていなかった)データを使うからオフライン処理が必要だったわけで、もっと複雑な処理をしているに違いありません。評価するまでの時間(=そのタイムフレームで蓄積されるデータ)、検索行動、検索需要などですね。しかし上記に紹介した記事で言及していることは、表面的な、ページをレンダリングして分析すれば済む程度のことですよね。
ユーザーエクスペリエンスの話であって、パンダじゃない
『ユーザーエクスペリエンスを考慮した SEO のベストプラクティス』であれば私は全然同意なのですが、パンダの話じゃないですよね、というのが私の見解です。
ですからインハウスSEO担当者の方は、一般的な、少し未来(2015年~)の SEO の方針を検討する上で、上記の5つのポイントを「ユーザーエクスペリエンス面から考える SEO の要所」として捉えていただくにはとても有用なことなのですが、パンダと切り離して考えていただくといいのではないでしょうか。ユーザーエクスペリエンスは大事です。
パンダの分析をしたい
パンダアップデートの分析は、作業コストと得られる成果のバランスを考えると、何度も繰り返しますが「最終アクションは変わらない」ことも考えるとあまりお勧めしません。分析したい方は、次のレシピを用意すると良いでしょう。
順位チェックしている検索キーワードの (1) Googleトレンドの傾向値、(2) キーワードプランナーから取得する検索数、(3) サードパーティーが提供する検索数、(4) その調査対象ウェブサイトの直近(1ヶ月くらい)のトレンド(流行ったモノゴト、季節要因など)、検索行動に影響を与えたに違いないキーワードリストの作成、(5) サードパーティーの検索行動分析情報、以上を集めると、たぶん何か考察できると思います。たぶん。
実際徹夜でやったのですが、お勧めしません。