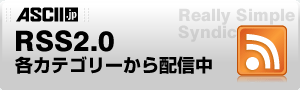昨年「ユーキャン新語・流行語」にノミネートされ、一挙に知名度が上がった「ソー活」。ところが同時期に、採用担当者から「ソーシャルメディア経由でアプローチしてくる学生の質が落ちた」という声が聞かれた。ソー活の現場では、何が起きているのだろうか。
ふと気づいた。「ソー活」「ソーシャルリクルーティング」などと、いまさら口にするのも恥ずかしいな、と。実は、それほど新しい概念でもないのだ。
ソー活のゴッドファーザー(名付け親)はリクルートだ。同社が2011年1月に発表した「トレンド予想」に初めて「ソー活元年」というキーワードが登場する。同社は、学生と企業の双方がネット上で本音をさらしあい、「リアルな場よりリアルな双方向の白熱コミュニケーションが展開される」と予測している。
具体的には、以下のような取り組みがソー活に含まれる。
(1)FacebookやTwitterを通じた、企業からの情報発信 →SNSの採用ページから企業が情報を発信し、学生がそれにコメントを付けることで疑問を解消したり、企業研究に役立てたりする。
(2)SNSを利用した、学生と人事担当者/先輩社員とのやり取り →学生がFacebookで就職を希望する会社の社員を調べ、直接質問したりOB・OG訪問をお願いしたりする。
(3)就活生同士の情報交換 →学生が、就活中に知り合った仲間にSNSで近況報告や情報交換をする。
(4)学生のセルフ・ブランディング →採用担当者に自分のキャラクターを少しでもつかんでもらうために、学生がSNSのプロフィール欄を充実させたり、学生生活について発信したりする。
これだけ聞いていると、「個と個がつながりあい、企業と学生が出会う素晴らしい時代になった」と思うかもしれない。事実、2012年にかけてリクルートの予測通りソー活はそこそこ盛り上がった。
ところが、この盛り上がりには裏がある。そもそもSNSを使った就活は、2009年ごろのTwitterブームからすでにあった。2011年から2012年にかけてソー活が注目されたのは、2011年3月に日本経団連が倫理憲章を改訂し、企業の採用開始時期を大学3年生の10月から12月へと後ろ倒ししたことも大きく関係している。
企業としては、早い段階でできるだけ優秀な学生を確保したい。ところが、大学3年生の12月まで採用のための広報活動を禁じられてしまった。そこで目を付けたのが、扱いがグレーのFacebook。2011年12月時点の学生のFacebook利用率はわずか13%で、感度の高い優秀な層が集まっていたことも幸いした。彼らを早急に囲い込むためのアプローチツールとして使われたのが真相だ。

この連載の記事
-
最終回
デジタル
ソー活と就活の終わらない日常 -
第3回
デジタル
人事の残念なソーシャル活用 -
第1回
デジタル
「世界一即戦力な男」の巧妙な戦略 - この連載の一覧へ