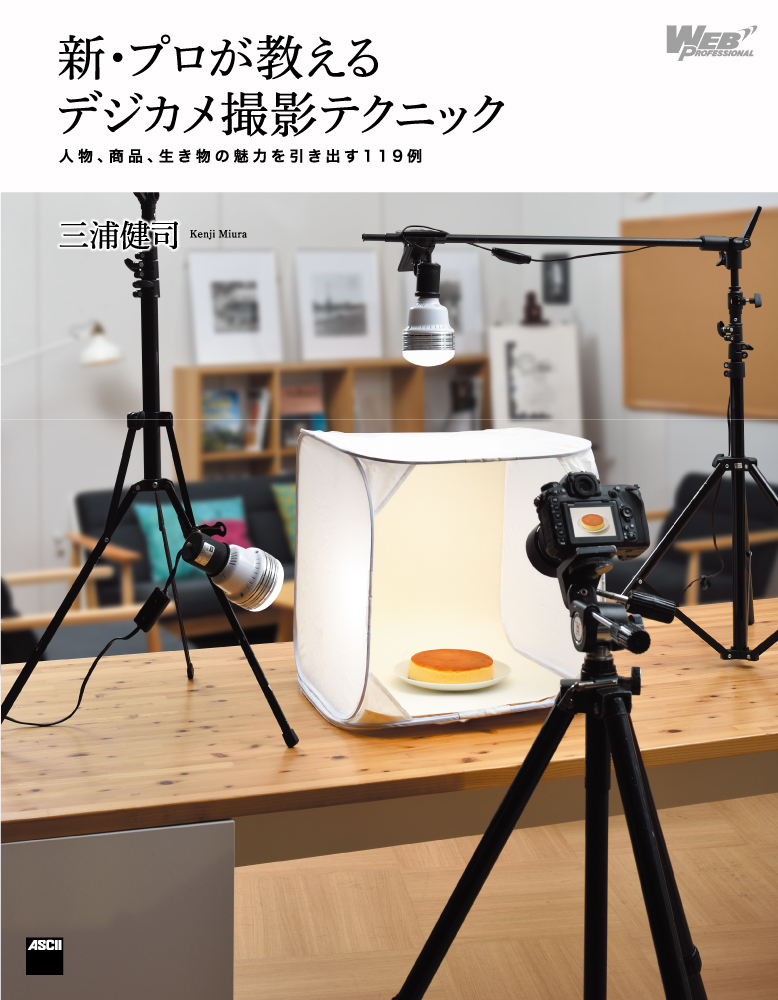デバイスの多様化やソーシャルメディアの台頭など、Webの利用環境が変化している。ユーザーのニーズを追い求め、利便性を追求した結果、Webはどのように変わってきているのか。ユーザーの“Web利用”の変化から見えてきた課題と解決策を探る。(編集部)
情報の変化からみえてくる Web の原点回帰
20年前はパソコンがWebへアクセスするためのデバイスだったが、今では携帯電話をはじめさまざまなデバイスから情報へアクセスできるようになった。生活・仕事に欠かせない存在になりつつあるWorld Wide Webを発明したティム・バーナーズ=リーは1997年に以下のようなことを述べている。
「Webが優れているのはユニバーサル(普遍的)であることだ。障碍のあるなしに関わらず誰でもアクセスできることはWebの欠かせない特徴である (The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.)」
技術の標準化を進める団体W3Cが勧告しているアクセシビリティガイドラインは、「誰でも Web にアクセスできる」という彼の言葉が反映されているが、Webの普遍性・包括性は高齢者を含む障碍者だけに止まらない。Webへアクセスできるデバイスが増えたのはもちろんだが、ユーザーのニーズが多様化・詳細化し、欲しい情報(データ)が欲しいタイミングで必要な分量だけ手元に届くことをユーザーは期待している。もうネットユーザーは情報があるページを探すのではなく、必要なデータが手元に届くことを当たり前と感じているだろう。
SNSやTwitterのようなストリーミングサービスを通して多くの情報がユーザーに直接届けられるようになったのも、Webの情報がどこにでも誰にでも届けられている兆候といえる。人が必要としている情報を届けられるWebの特徴は、ティム・バーナーズ=リーが提唱している「Access by everyone (誰でもアクセスできる)」と密接な関係にあるわけだが、こうしたWebの情報の行き来を実現するには以下の条件が必要とされる。
- 1. 小さい
- さまざまな情報が掲載されているページではなく、必要とされているコンテンツごとに細分化されている
- 2. 持ち運び可能
- 小さくなったコンテンツはさまざまな場所 (Webサイト) やデバイスに移行できる
- 3.ハイパーリンク
- それぞれのデータとデータを繋げることで細分化されたデータが意味をもつだけでなく、ストーリーが完成する
紙媒体のページの概念が強く残っていた従来のWebは、次第に「ページ」という領域があやふやになり、データがさまざまな場所で行き来するユニバーサルなWebへと進化した。ティム・バーナーズ=リーのビジョンにやっと近いものになり始めたといえるかもしれない。小さくなければ、即時性を求めるユーザーのニーズに応えられない。小さくなければ持ち運びが難しい。持ち運びができない状態ならユーザーのもとへ情報を届けられない。ハイパーリンクを駆使しなければ、情報に意味を持たせて価値を生み出すこともできない。
今日のWeb上の情報のあり方は、デバイスやそれを使う人々のニーズに応えるための必然な変化といえる。近年頻繁に取り上げられているソーシャルメディアのビジネス活用も、こうした情報の性質や流れの変化が背景にある。