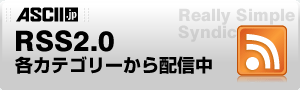台北に来ている。
今年から来年にかけてのパソコンの動向が分かる“COMPUTEX TAIPEI 2007”に3日目から参加中だ。その会場で会った業界関係者に「今年のCOMPUTEXの特徴は何か?」と聞いたら、次の3つを挙げてくれた。
- 新製品が多い
- ロシアやブラジル、インドのバイヤーが多い
- 雨の日が多い
会場となる世界貿易センターのメインホールから、パソコン本体が追い出されて久しいが、今年は、パソコンの周辺機器やメディア関係の会社が並んでいて、アキバな気分がよみがえる。USBメモリーのナンバーワン・トランセンドが露出度の高いお姉さんを踊らせまくっていたかと思えば、キングストンは地元台湾の有名モデルにビラを配らせている。
それにしても、ロシア人が多いとは気付かなかった。ブースに意味もなくいるお姉さん*の中には、露出度の高い白人系の外国人が多く
「おっ、ロシア、それともルーマニア?」
という感じの人が何人もいたが、男のバイヤーには目がいかないからだ。
*意味がないってことはないと思いますが……。(編集部)
中国よりも低コストなロシアの人件費
日本人は、なぜかインド人の認識能力が高い。それは、かなりいい加減な説を唱えるとすると、仏教美術との関係があると思う。しかし、ロシア人とブラジル人というのは、なぜかあまり意識しないのだ。しかし、その気になって会場や商談エリアのあたりを歩いてみると、たしかに! 業界関係者の言うとおり、ロシア人とおぼしき古き冷戦時代のKGBみたいな感じのふたり連れが歩いていたりする。
今回のCOMPUTEXでは、コンピューター関連だけでなく、エコ関係のソーラー発電なんかも注目らしいのだが、広いロシアにはピッタリきそうである。いやいや、あらゆるものがロシアに流れているというのが本当のところらしい。たしかに、欧米のエレクトロニクスとは隔絶した世界だったとはいえ、相応の技術水準を持つ国だったはずだからだ。
かくいう私も、ebayでロシア製の電卓を何台か買ったことがある。しかし、某光メディアメーカーの方によると、ロシアが注目されているのは、そんな理由ではないそうだ。CD-ROMのプレスに関しては、中国すら価格競争力で太刀打ちできなくなりつつあるのだという。
いまから20年近く前、米国のコンピュータショー“COMDEX”に、日本のコンピュータ関係者がどっと増えたときに、会場の片隅で“日本風の弁当”が売り出されたことがあった。米国でオシャレな人たちにすっかり定着していた“SUSHI”というのならまだ分かるが、それは、いかにもな“コンビニ弁当”で脱力したのを思い出す。COMPUTEXは、いまのところ全体的な構成比では米国人バイヤーの数が多いだろう。そんなわけかどうか、“SUBWAY”が、しっかり休憩・軽食エリアに陣取っている。
今回のご提案!
そうなのだ、今回の「ご提案」は、コレである!
今年秋、日本で開催されるのCEATEC JAPAN 2007で、駿河台下のサラファンかバラライカにスペシャル弁当をお願いしてみてはいかがだろう?
私の友人は、近々ロシアに転勤になる。彼の事前調査によると、モスクワでは日本のマンガやアニメが人気で、そのせいで髪の毛を黒く染めたりしている人もいるそうだ。その勢いで、ロシアと日本で、この業界をよろしく組んでやっていけないものかなどとも思う。いやいや、すでにメーカーのブースには“EXHIBITOR”のバッチを付けた東欧風の人だっていたりするのだ。
さらにいえば、編集部のQくんによると、今年3月に、ロシアと至近距離にあるドイツで行われたCeBITはロシアと提携しており、ここにもロシア人が大挙して押し寄せていたという。
自然にまかせる日本の“禅”の文化もよいのだが、ロシア、ブラジル、インドに、もっと積極的に迫るべきではないか? 日本には、インド料理屋はたくさんあるからいいとして、まずは、ロシア料理だろう。ロシア料理と言われて、日本人がピンとくるのはボルシチ? 私は、カレーパンの元になったという説もあるピロシキがいいと思うのだが。
江戸時代、青木昆陽がサツマイモを栽培したことで知られる幕張の地で、噛みしめるピロシキの味はどんなものだろう?
筆者紹介−遠藤諭

(株)アスキー取締役。91年~2002年まで『月刊アスキー』編集長、現同誌編集主幹。日本のモバイルやネットのこれからについて、業界での長い経験を生かした独自のスタンスで発信している。著書に、日本のコンピュータ黎明期に活躍した人たちを取材した『新装版 計算機屋かく戦えり』、朝日新聞に連載した『遠藤諭の電脳術』など。ブログ“東京カレー日記”も更新中。

この連載の記事
-
第7回
トピックス
アンドロイドはスタートページの夢を見るか? -
第6回
トピックス
ちょっと怖い、唐の予言書の話 -
第5回
トピックス
iPhone? PRADAフォン? いやいや“イロモノ”でしょ -
第4回
トピックス
パックマン世界選手権 -
第2回
トピックス
セカンドライフの中の名前 -
第1回
トピックス
Macをはじめよう -
トピックス
遠藤諭の“ご提案”〈目次〉 - この連載の一覧へ