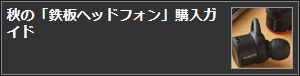多彩に使える、DYNAUDIOの高音質無線スピーカー
無線ならXeoで決めろ! 狭い我が家で、本物の音を (1/4)
2013年06月24日 12時00分更新
記事の最後にASCII.jp読者限定のプレゼントキャンペーン企画の案内があります。合わせてお読みください。
ひと昔前のオーディオシステムというと、重量級の単品コンポーネントに大口径のスピーカーをつなぐ……といった大掛かりなものが主流だった。もちろんハイエンドオーディオでは今もそういう製品が存在するし、そうしなければ実現できない音もある。
しかし極めて多様化してきた昨今のオーディオソースに柔軟に対応し、かついい音をより身近にしたいと考えるなら、別の選択肢を検討してみてもいい。
その一例として提案したいのが、無線スピーカーの導入だ。
現実的になってきた、無線使用のオーディオ構築
無線利用オーディオシステムと聞いて、どのようなものを思い浮かべるだろうか?
まず思いつくのは一般的になりつつある、Bluetooth利用のオーディオ機器だろう。スマートフォンやパソコンといった機器にBluetoothが標準的に搭載されるようになり、気軽にペアリングして再生するというスタイルが浸透してきた。
ヘッドセットを中心に普及してきたBluetoothだが、最近ではパソコンとの接続を想定したBluetoothスピーカーも増えてきた。ただしまだまだ周辺機器然とした小型の製品が中心で、携帯性などを重視したオーディオ的にはミニマムな製品が主流という面もある。
また、オーディオ的にみるとBluetoothには、限られた無線帯域で効率よく音声を送信するため、圧縮が必須という側面も気になる。これは、簡単に言うと圧縮によって音の情報が欠落し、圧縮・復元の処理のために遅延が生じるといったデメリットが懸念されるということだ。
もちろん伝送時の圧縮に利用するコーデックは日々改善されており、apt-XやAACを使い高音質・低遅延を目指すという取り組みもある。しかしソースの情報をそのまま、手を加えずに伝送するというHi-Fi的な考え方とは方向感が若干異なる面もある。
ならば、やはり単品のオーディオをケーブルをつないでシステムを組むのが最上という結論になるかというと中々難しい。自宅の限られたスペースに単品コンポを設置し、自由な音量で再生できるような恵まれた環境がある人はそれほど多くはないのも事実だろう。
単品のコンポは設置するために、少なくとも幅と奥行きに400~500mm程度のスペースが必要だし、部屋の中でケーブルを引き回すのもあまり美しいものではない。リビングに置くにしろ、ワンルームに置くにしろ、専用の部屋で音楽を聴くというのは極めて贅沢だ。確かに、広い部屋とケーブルをうまくまとめ隠す手間を惜しまなければ素晴らしいオーディオルームが作れるが、「そこまでは……」と躊躇してしまうケースは少なくない。

この連載の記事
-
Audio & Visual
第11回 DITA「Answer」は、インイヤーの究極の“答え”となるか -
Audio & Visual
第10回 価格だけでなく音も本当にすごい「Layla」と「Angie」 -
Audio & Visual
第9回 ハイレゾ機の定番、第2世代Astell&Kernを比較試聴 -
Audio & Visual
第9回 本格派USB DACのバランス駆動で、音の世界に浸る -
Audio & Visual
第8回 力感と繊細さを兼ね備えた新進ブランドのイヤフォンを聴く -
Audio & Visual
第7回 驚きのHi-Fi感をぐっと凝縮した、パイオニア U-05を聴く -
Audio & Visual
第6回 真空管のサウンドをポケットに、「Carot One」のポタアンを聴く -
Audio & Visual
第5回 最高のプリメインアンプを求め、LUXMANの試聴室を訪問した -
Audio & Visual
第4回 伝統と革新の両立、DA-06とDA-100が受け継ぐラックストーン -
Audio & Visual
第3回 コンパクトなボディーからあふれ出る上質、ELAC AM50 -
Audio & Visual
第2回 無線ならXeoで決めろ! 狭い我が家で、本物の音を - この連載の一覧へ