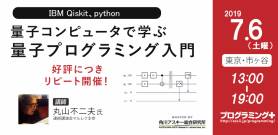日本には火縄銃とともに伝来した“ねじ”だが、世界的に見ても“甲冑”や“火縄銃”がねじを育てたそうだ。ねじの螺旋は生命的に惹かれるものがあると思う。(今回は「週刊アスキー連載中の『神は雲の中にあられる』より転載です)
ねじとコンピューターの関係
『ねじとねじ回し』(ヴィトルト・リプチンスキ著、春日井晶子訳、早川書房)という本に、“旋盤”についての興味ぶかい記述がある。1701年に書かれた本に「この技術は、今日のヨーロッパで知的な人々が熱心に行う趣味として確立されている。純然たる気晴らしと知的娯楽のあいだに位置するものとして、時間をもてあますことで生じている不都合を避けるための最高の暇つぶしとし考え、真剣に取り組む人々もいる」と書かれている。18世紀の終わりまで、紳士にとって“旋盤”を回すことが婦人における刺繍にあたるものだったとも書いている。
山高帽にシルクハットを被っているような紳士が、自宅の工房でなにやらガリガリやっている。産業革命の民主化ともいうべきか、なんでも数学的な正しい円断面に加工してしまう“旋盤”が、紳士の“たしなみ”だったというのは、なんとなく納得のいく話のような気がする。そう考えると、21世紀のいまの紳士どもの知的娯楽は、やっぱり“プログラミング”であるべきだなどと言ってみたくなる。
『ねじとねじ回し』は、ニューヨークタイムズの記者に“この千年で最高の発明はなにか?”というお題をもらった著者が、悩みぬいていたら1冊の本になってしまったというものだ。人類の最高の発明といえば、“紙”であるとか“文字”であるとか、誰でも1つや2つは思い浮かべると思うが、西暦1000年から1999年となると話は変わってくる。相応の教養と見識が必要になるはずで、英国生まれでペンシルベニア大学教授の建築学や都市論の専門家がたどりついた結論が、“ねじとねじ回し”だったわけだ。その知的探検作業のあい間に出てくる、いま我々が暮らしている産業社会に至るまでの諸事情も、それを“切る”ための旋盤だけでなく学ぶべきエピソードにあふれている。
これに出てくる機械で、私がいちばん気に入ったのは16世紀イタリアの軍事技術者アゴスティーノ・ラメッリの“回転式書見台”である。それは、1メートル80センチもの高さのあるメカニズム的には観覧車に似た装置で、8冊以上の本を次から次へと堪能できるというものだ。これは、次から次へと情報を閲覧できるインターネットの元祖的なものかもしれない。

アゴスティーノ・ラメッリの回転式書見台。ヴァニバー・ブッシュの“メメックス”をおも連想させる活字中毒者のための発明
また、アンドロイドなのかiOSなのかをはじめさまざまな規格争いが、このネットデジタル業界の大きなテーマだが、ねじはその歴史的摂理を100年ほど前にたどっている。中でも著者が興味を持ったのは、1907年に米国のピーター・L・ロバートソンが特許をとった“ロバートソンねじ”だ。これは、頭(お皿)の部分に四角い穴があり、そこにねじ回しを入れて回すものだ。一時期は、その生産されるねじの3分の1をフォード社がT型フォードを作るために買っていたともいわれる。ねじ回しの先端は少しとがっていて、穴のフチは斜めにテーパがかかっており、六角レンチよりスムーズに入ると思えるほど工夫されている。ねじの歴史をくまなく調べた著者をして「ここで告白しよう、私はロバートソンねじの信者である」とか「20世紀最高の小さな大発見」(?)とまで書かせるものだった。
しかし、歴史はロバートソンねじを我々に忘れさせることになる。古典的なマイナスの溝つきねじか、1930年代にジョン・P・トンプソンが発明し、ヘンリー・F・フィリップスが特許を買い取って改良したプラス式のねじだけが、21世紀のいまコンビニの棚で売られている。フィリップスは、ロバートソンねじを知っていたし、同じように当時いちばん勢いのある自動車産業をねらった。ところが、ロバートソンが自らねじを製造したのに対して、フィリップスは特許の使用権だけをねじ製造者に貸与したのだ。さながら、トンプソンはマイクロソフトに“QDOS”を売ったシアトル・コンピューターのティム・パターソンで、フィリップスはビル・ゲイツといったところか(シアトル・コンピューターも、またハードウェアの会社だった)。
ねじの本を読み返そうと思ったのは、カメラの三脚ねじをあれこれやっていたからだ。リコーの360度カメラ“THETA”は、手で持って使うと自分の親指が大きく映り込んでしまう。そこで、手ごろな“自撮り棒”のようなものを探していたのだが(しかも、スマホも一体化するとうつくしい)、THETA本体にもついている“1/4インチ”の三脚ねじ穴というものがポイントとなる。そう、いまどきインチねじなのですね。カメラの三脚ねじは、国際規格の“ISO 1222”と日本工業規格の“JIS B7103”で、オスねじを“1/4-20UNC”、または“3/8-16UNC”、長さは4・5±0・2ミリと定められているそうだ(ねじの直径と1インチあたりの山数であらわされる=ちなみにねじ業界では1/4は8で通分して2分《ぶ》と呼ぶそうな)。ご存知のように古いカメラにも三脚ねじ穴がついていて、「そういえば、ねじの本を持っていた」とねじの由来を調べたくなったわけだ。
結論からいうと、三脚ねじそのものはこの本に出てこないのだが、それが、英国で最初に決められたねじ規格が使われたことは分かった。正確には、古いカメラに使われているのは1841年にサー・ジョセフ・ウィットワースが提案した規格の1/4インチねじである。米国のそれと競合するねじ業界がわずかに異なるUNC規格を作り、いつの間にかその市場をとってしまった。この点も、IT業界であてはめられる事例がいくつも出てきそうではあるが。いまではウィットワースねじは建築などごく一部の分野でしか残っていない。
そのため古いカメラの三脚ねじ穴にもいまの三脚ねじが使えてしまうのだ(厳密には山の形状が異なっているために材料力学的に負荷が増えるはずなので無理をして入れていると思えるが)。ちなみに、ウィットワースは職人で旋盤の開発者でもあったヘンリー・モーズレーという人物の徒弟だったが、コンピューターの祖先といわれるチャールズ・バベッジの“階差機関”を製作したジョセフ・クレメントもモーズレーのもとにいた職人でだそうだ。
そのコンピューターといえば、PCの中身はハードディスクなどの基幹部品はインチねじであるのに対して、光学ドライブなどはミリねじを使うようになっている。つまり、インチねじとミリねじが混在しているという困った製品である。それにしても、300年前のヨーロッパの紳士たちは、自宅で旋盤を回しながら何を考えていたんですかねか? 旋盤が18世紀のPC(パーソナルコンピューターならぬパーソナル産業革命)だったのだとすると、いわゆる後期産業主義(産業革命後の社会)の世界を夢に描いていたのかもしれません。

この連載の記事
-
第168回
トピックス
オープン直前の新「マイコン博物館」におじゃまして展示品や施設を案内してもらった! -
第167回
トピックス
Googleの始め方――スタートアップをいちばん知っている人物が語る3つの条件とは? -
第166回
トピックス
女子大生が100日連続で生成AIで100本のプログラムを書いたらどうなったか? -
第165回
トピックス
生成AIも体験して学ぶ「AIのアイ」展がはじまった! -
第164回
トピックス
新しくなったChatGPTにできること、できないこと -
第163回
トピックス
日本にはコンピューター博物館が必要だ! 青梅の新「マイコン博物館」のクラファンがスタート -
第162回
トピックス
遊べるWebサイトを240秒で作る方法――DeployScriptを試そう -
第161回
トピックス
情報理論の父クロード・シャノンとChatGPTによる完全パングラムの生成 -
第160回
トピックス
アルファベット26文字をすべて使ってできるだけ短い文を作る with ChatGPT -
第159回
トピックス
最短15分! ChatGPTに自分の過去原稿を合体して“自分GPT”を作る -
第158回
トピックス
ChatGPTの新機能コードインタープリターに《未来の仕事の全自動化》が見える - この連載の一覧へ