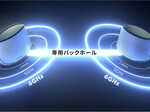ReadyNASをオフィスでとことん活用する!実践使いこなし術 第1回
RAIDボリュームの作成から設定、拡張までGUIで簡単にできる
ReadyNASの「Flex-RAID」でRAIDを柔軟に設定してみる
2015年03月17日 14時00分更新
本連載では、企業向けネットワークストレージであるネットギア「ReadyNAS」の実践的な使いこなしTipsを、実機レビューを踏まえながら紹介していく。第1回はFlex-RAIDの使いこなし術だ。
ReadyNASには2つのRAID設定モードがある
RAIDは、複数台のドライブ(ハードディスク)をまとめて使い、データを各ドライブにコピー/分散して書き込むことで、一部のドライブが故障してもデータが失われないようにする技術である。ドライブの組み合わせ方を「RAIDレベル」と呼び、RAIDレベルによって耐障害性が異なる。
さて、以前も触れたとおり、ReadyNASには「X-RAID2」と「Flex-RAID」という2つの設定モードがある。標準設定のX-RAID2は“自動RAIDモード”で、ディスク本数に応じて最適な(データ保護と容量のバランスを取った)RAIDレベルが自動選択される(関連記事)。ファイルサーバーを止めることなく、ディスクを追加/交換していくだけで容量を拡張することもできるので、とても便利だ。
だが、X-RAID2には「複数のボリュームを作れない」「自分でRAIDレベルを指定できない」といった制約がある。こうした制約を回避したい場合は、Flex-RAIDモードを使うことになる。ただし“手作業モード”とはいえ、そこはReadyNASらしく簡単かつ柔軟に使えるようだ。さっそく試してみよう。
なお本連載では、6つのドライブベイを備えたデスクトップ型モデル「ReadyNAS 716X」を使って説明を進めていくが、紹介する機能はReadyNAS全機種で共通して利用できる。執筆時点でのファームウェアバージョンは「ReadyNAS OS 6.2.2」だ。
Flex-RAIDモードへの切り替えは簡単!
前述のとおり、ReadyNASの標準設定ではX-RAID2モードが有効になっており、「data」という名前のボリュームが1つだけ作成されている。
Flex-RAIDモードへの切り替えは簡単だ。ReadyNAS本体の管理画面で「システム」>「ボリューム」を開くと、右脇に「X-RAID」ボタンがあり、緑色になっているはずだ。これをクリックするだけで、Flex-RAIDモードに切り替えることができる。
この段階では、ボリュームはそのまま残っている。RAIDレベルも元のままで、中のファイルもそのままなので、引き続きアクセス可能だ。
ただし、Flex-RAIDモードに切り替えても、すでに存在するボリュームのRAIDレベルを変更することはできない(例外もある、後述)。Flex-RAIDモードでは、RAIDレベルはボリュームの作成時に指定しなければならない。つまり、ほかのRAIDレベルに変更したければ、いったんボリュームを破棄して新たに作成し直す必要がある。
ボリュームを破棄するとボリューム内のすべてのファイルが削除されるので、すでにファイルを保存している場合は、いったん別のメディア(USB接続の外部ドライブなど)にバックアップしてから作業を続けなければならない。この点には十分に注意してほしい。
新しいボリュームを作成する
続いて、ボリューム破棄で空になったドライブを使い、新しいボリュームを作成する。せっかくなので、今回はRAIDレベルの異なる2つのボリュームを作成してみたい。
ボリュームの管理画面で、ボリューム作成に使用したいドライブをクリックして選択し(薄いグレーから濃いグレーに変わる)、「新しいボリューム」を押すと、設定ダイアログが表示される。ここではドライブ2台を指定し、RAID 0のボリュームを作成した。
同じようにして、残り4台のドライブでRAID 6のボリュームを作成する。なお、RAIDレベルとドライブの容量によっては、ボリュームの構成に数時間~数十時間かかることがある。
このように、RAIDレベルの異なる(=保護レベルの異なる)ボリュームを複数用意することで、「保存するファイルの重要度の違い」や「ファイルサーバー/iSCSIストレージの用途の違い」などで使い分けることができる。
また、ReadyNASのバックアップ機能では、ボリューム単位でバックアップ元/バックアップ先を指定することができる。たとえば重要なデータを保存したボリュームのバックアップ頻度を高くするなど、バックアップも柔軟に適用できるだろう。
(→次ページ、ドライブを追加してボリューム容量を拡張するには?)


この連載の記事
-
第10回
TECH
ReadyNASの新しいテストマシンが届いたので観察してみる -
第9回
TECH
Macの「Time Machine」でReadyNASにバックアップしてみる -
第8回
TECH
ReadyNASをバックアップデータ保存先にする際の注意点を考える -
第7回
TECH
「Acronis Backup Advanced」でReadyNASへのバックアップを試す -
第6回
TECH
「arcserve UDP」でファイルサーバーへのバックアップを試す -
第5回
TECH
「Symantec Backup Exec」でReadyNASへのバックアップを試す -
第4回
TECH
雷!台風!急な停電に泣かないようReadyNASをUPSにつないだ -
第3回
TECH
ReadyNASの「回数無制限スナップショット」を使い倒す -
第2回
TECH
暗号化+USBキーで、ReadyNAS上のデータに“鍵”をかける -
TECH
ReadyNASをオフィスでとことん活用する!実践使いこなし術 - この連載の一覧へ