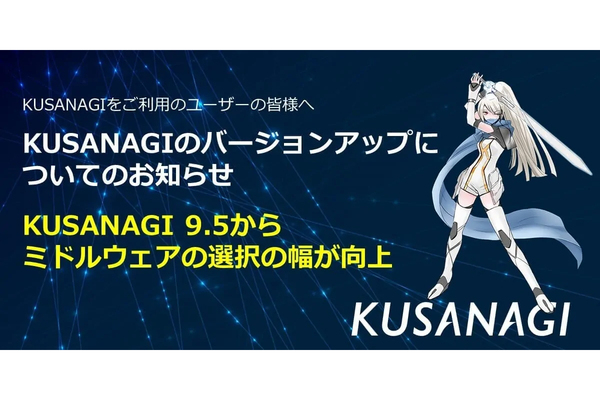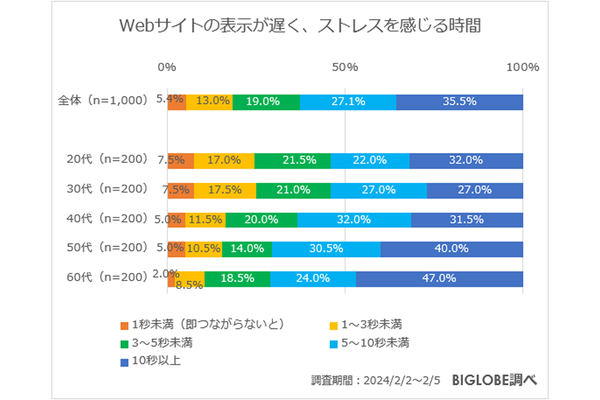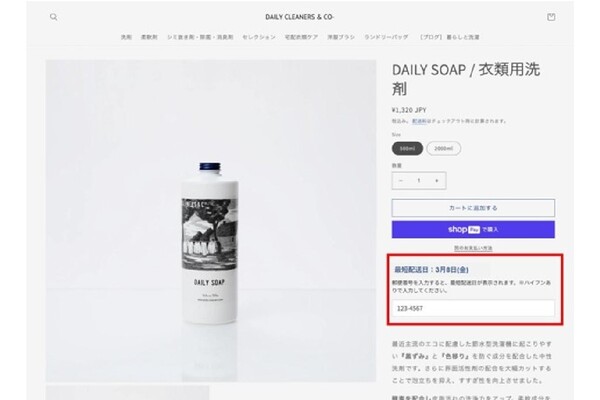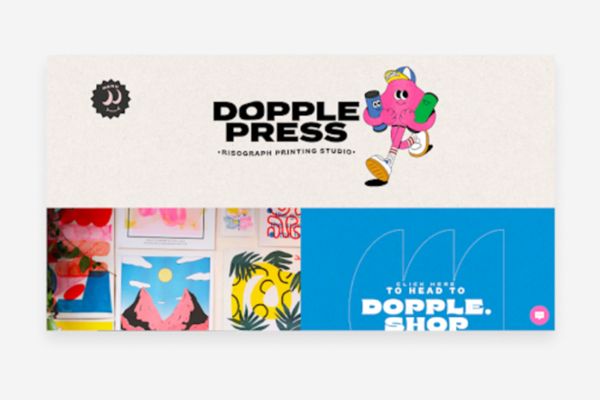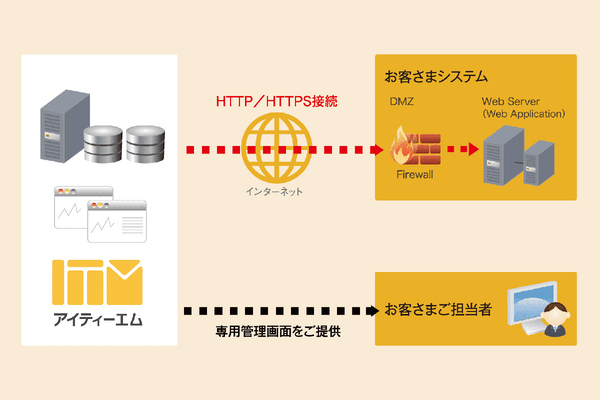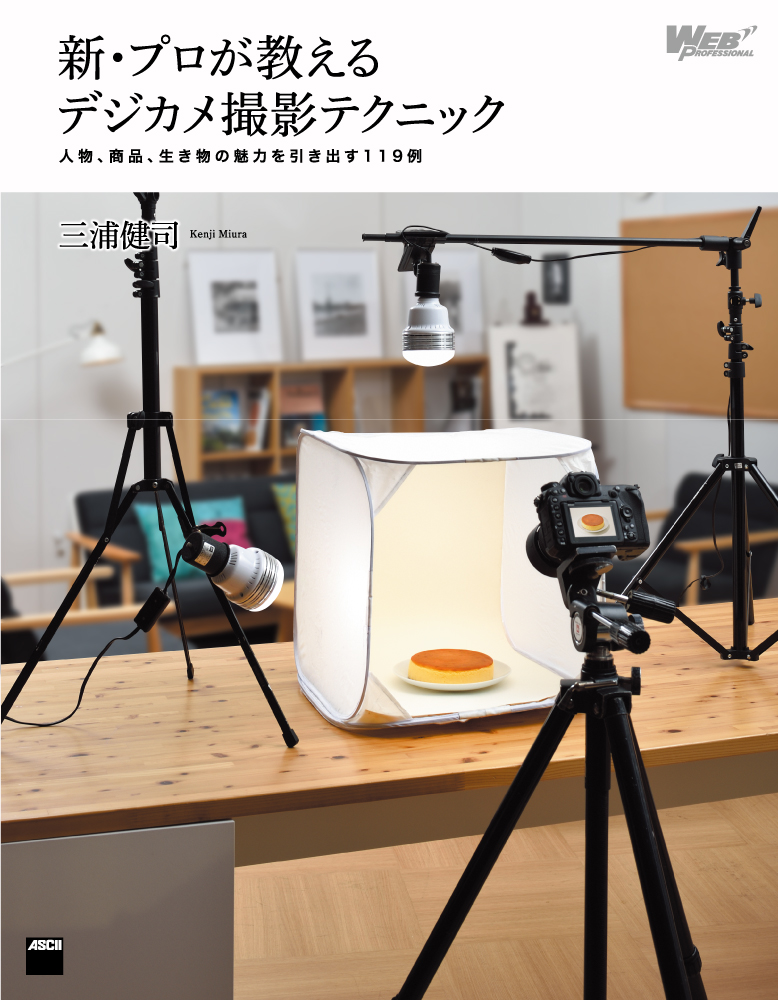気軽にネットショップを始めては見たけれど
「あなたがネットショップを始めたきっかけはなんですか?」
「ネットショップは儲かると聞いた」「同業他社で儲かっている人がいる」というような答えをよく聞きます。具体的には、お店を持って小売りをしていた、もしくは卸をしていたが、ネットだと簡単にたくさんのお客さんに接触できるらしい。そんな話からネット通販に興味を持ちます。確かに、一面的にはそれは嘘ではありません。インターネットビジネスは始めた途端に日本中の見込み客に接触できる可能性があります。とくに日本のインターネットトラフィックが集中しているYahoo!やGoogleで狙ったキーワードで上位表示が出来ればそれだけで今までとは1桁、2桁多くのお客さんに自社の商品、サービスを知ってもらえる可能性があります。インターネットのテクノロジーは新時代のマーケットを生んだのです。しかし、実際にネットショップに取り組んでみると、そんなに簡単では無いことに気付かされます。
最近はネットショップを開店することは難しくありません。モールで出店すれば簡単にサイトの制作はできますし、アドバイスをしてくれるコンサルタントもつきます。また独自ドメインを取得してレンタルサーバーを利用すれば年間数万円の低コストでショップを開設できます。
しかし、いざショップをOPENすると、最初はほとんど売り上げが立ちません。なぜなら、サイトの訪問者がいないからです。「お客さんを呼び込まないといけないんだ」。そこで初めてマーケティングという発想に至ります。お客さんがいなければ受注がありませんし、出荷の仕事もメールマガジンを書く仕事もありません。最初の売り上げが上がるまでは暇なのです。
暇なので、専門雑誌(「インターネットでお店やろうよ!」のような)やウェブサイト(「EC応援隊」のような)で勉強したり、専門セミナーを見つけて参加したりします。たくさんの情報に触れる中で、多くの方は最初にSEOやメルマガ配信の手法を学び、アクセスを獲得します。商品がよければ、多少サイトが汚くても少し売り上げが上がります。そうなると、自分で勉強して売り上げを上げていくことが楽しくなり、「まずは行けるところまで行ってみよう!」となるわけです。
これまで暇だったのですから、売り上げが上がるのはうれしいものです。最初は仕事の効率は考えず、まずは時間がある限り働きます。昼夜を問わず働きます。いつしか暇な時間は無くなり、1日中働いています。その段階になると、(商品にもよりますが)一人でも数十万円~数百万円の売り上げが上がるようになります。そうなると今度は楽になりたい、と思いはじめ、スタッフを雇用することを考えます。
知人の紹介や、専門の紹介会社(サポタントさんのような)の支援によって、なんとかスタッフを雇用します。一人から二人になると労働力が2倍になるわけですから、売り上げも2倍になると思うでしょう。しかし、なかなかそうはなりません。なぜなら、ビジネスオーナーとスタッフのスキルや労働時間は大きくかけ離れているからです。

簡単にいえば、オーナーはたくさん働きます。労働量を数値化するのは難しいですが、たとえば一日15時間働きます。その結果、売り上げが5万円、固定費1万円、人件費1万円、原価1万円だと利益が2万円です。仮に1カ月25日働くと、25万円の給料と、50万円の利益が残ります。これなら会社員よりも割がいいかもしれません。(労働時間はとても長いですが。)
ここで欲が出ます。「スタッフを増やしたらもっと楽になって、もっと儲かるんじゃないか?」。試算してみましょう。まず、オーナー経営者との違いは労働時間です。スタッフは15時間も働けません。たとえば、労働時間が8時間、労働時間が半分ですから、そうなると比例して売り上げが2万5千円、しかし固定費、人件費は変わらず、固定費1万円、人件費1万円、原価だけは変動費なので売り上げに比例して5千円になります。そうなると、結果利益が0になってしまいます。「あれ、なんで儲からないんだろう?」そう思いながらももう一人スタッフを追加します。それでも同じように利益は増えません。気がついたら多くのスタッフを抱えて、必死に働いているのに儲からない構造が出来上がっています。


なぜこのようなことになってしまうのでしょうか。直接的な原因は利益率が低いことです。利益率が高ければスタッフも利益を生むことができ、結果規模拡大が利益の拡大になります。
それでは、利益率が低いビジネスではネットショップは適さないのでしょうか。原則的にはそうですが、上記の例のように、一人で経営している間は大きな利益を生んでいます。つまり、どんな事業でも儲かる最適規模がある、ということです。
商売と事業 「儲かる!」ための最適規模を見極める
上記のように、一人でやればもうかるビジネスはその規模を追及しなければある人にとってはハッピーなモデルです。その代わりに、人を雇えない以上、規模を追求することはできず、自分自身が引退するとこのビジネスも終わりをつけるでしょう。
逆に一人では儲からないが、大勢でやると儲かるビジネスがあります。そのためには個人技で儲けを追及することはせず、誰がやっても儲かるような仕組み化が必要です。
この2つのビジネスモデルの違いは簡単に言えば「商売」と「事業」の違いです。「商売」は小人数による限定的な期間の中でのビジネスです。「事業」は組織によるスケールを追及するビジネスで、ビジネスオーナーと運営者が異なる場合があります。「商売」は個人の収入を高めることができますが、桁違いの収入は期待できません。「事業」は自分がビジネスを行うのではなく、人を使ってビジネスをさせるため、その実現には商売以上の組織を動かすための工夫が必要ですが、成功すれば永く、桁違いの収入を実現することもできます。一見同じく「儲け」を目的としていますが、たとえば、家族経営のひもの屋さんが実店舗の延長線上でお客さんを増やすためにネットショップを持つのであれば、事業規模を追求するのではなく、家族を養うことが目的でしょう。あえてスケールを追及するよりも自身のノウハウとスキルの範囲で「商売」を目指すでしょう。逆に最初から「事業」家を目指す方にとっては最初から従業員を雇うことが視野に入っているはずです。
「商売」か「事業」か。この見極めが重要です。その選択によってビジネスモデルも大きく異なるのです。
理念に立ち返る
多くの方はお客さんを増やしたくてネットビジネスに参入します。その時点ではネットでのビジネスモデルを真剣に検討せず、これまでの「商売」の延長線上で集客方法としてのインターネットの活用を考えます。このようなインターネットの活用方法を「手法」としての活用と呼びます。お客様のイメージや提供する価値は既存のままで、売るためのシナリオの一部としてインターネットを活用しています。
しかし、より本格的にインターネットビジネスに取り組む中で、「規模を拡大するにはどうやら実店舗とは違った工夫が必要だ」と感じるわけです。そうなると、インターネットで売るための商品の見直し、ターゲットとなるお客さんの見直しを行います。これが「商売」から「事業」への脱皮です。このとき、改めて自身の価値観や人生か(理念)やそれを自身に当てはめた時の理想形(目的・目標)、そしてそれを実現するための戦術を考え、再度具体的な手法を検討します。

このような「商売」から「事業」への脱皮はネットショップに限らず、多くの事業オーナーが経験しています。結局大きなことを成そうとするならそのベースとしての世界観や思想が必要だと言うことです。多くの人の人生を巻き込むのですから、当たり前といえば当たり前ですね。
インターネットビジネス成功のため、まずは自身が何のためにネットショップ経営に取り組むのか。真剣に考え、常に自身に問い続けることが必要です。
著者プロフィール

| 名前 | 権 成俊(ごん なるとし、左)、李 泰成(り やすなり、右) | info[アットマーク]gonweb.co.jp |
|---|---|---|
| ※著者に直接問い合わせをする際は、お名前、会社名、サイトURLなどを明記してください。 | ||
| 会社 | 株式会社ゴンウェブコンサルティング | |
| サイト | http://www.gonweb.co.jp/ | |