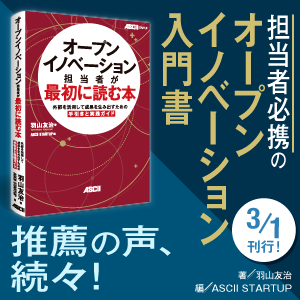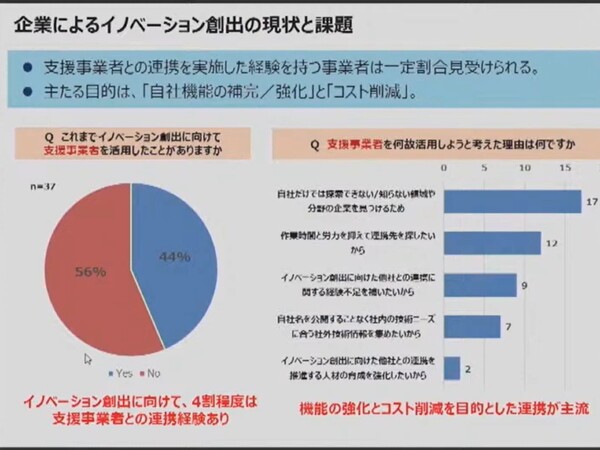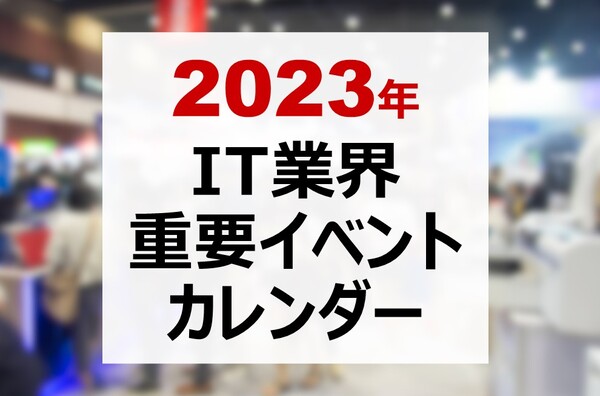オープンイノベーションと知的財産権:成果を出した先進的な企業は何をやったか
1 2
オープンイノベーションコンテストと知的財産権
オープンイノベーションコンテストでは不特定多数の問題解決者が関わることから、知的財産権に関する特別な配慮が必要となってくる。この点に関してはde Beerの報告が参考になる。
●クラウドソーシングの提案を活用する際には、問題解決者の許可を得る必要がある
●クラウドソーシングでは実施主体である問題提供者がより多くを求めるほど、問題解決者の参加するモチベーションが低下する
●クラウドソーシングを実施する際には、法的な基盤として注意深く検討された利用規約が必要である
●利用規約は法的に正しいだけでなく、参加する問題解決者にとって公正に感じられるものでなければならない
●問題解決者を利用規約に同意させる方法にはさまざまな種類があるが、承認ボタンのクリックにより画面上の契約内容が承認されたとするクリックラップ契約が一般的である
●問題解決者はアイデアを活用してもらいたいと思って提案するが、黙示ライセンスに頼らずに使用許可を利用規約に含めるべきである
*de Beer, Jeremy, Ian P. McCarthy, Adam Soliman and Emily Treen [2017], "Click here to agree: Managing intellectual property when crowdsourcing solutions," Business Horizons, 60(2), 207-217.
不安がある場合は経験豊富な仲介業者が提供しているサービスを活用すれば、知的財産権に関する問題に対応してもらえる。
知的財産権を活用した機会の探索
特許は各企業やその他の研究開発組織の戦略を映し出したものと考えられるため、オープンイノベーションの機会を探すための有用なツールとなりうる。特許データははるか昔から存在するものであるが、以前は紙ベースであったこと、また言語の違いの問題から活用が困難であった。しかしながら現在ではデータベースが整備され、さまざまな解析ソフトウェアやAIを用いたデータマイニングサービスも出てきている。
Germeraadは特許データベースを用いてオープンイノベーションの機会を見つける方法を提案している。
●インバウンド型のオープンイノベーションにおける成功の鍵は、どの技術や解決策を外部に求めるかを素早くかつ精度よく見極めることである
●現時点で特許が確認されていない領域では自社開発やアカデミア/企業との共同研究/開発を行い、すでに特許が多数存在している領域では実証済みの技術を調達することが基本的な戦略となる
●対象技術を特定した後に特許データベースからオープンイノベーションの機会を見つけるステップは以下の通り:
・対象技術が属する分野を取り巻く状況や見通しを理解する
・本分野における直近のトレンドを理解する
・対象技術に焦点を当てて状況を理解する
・考えられる限りの選択肢を抽出する
・それぞれの選択肢におけるIPリスクを見積もる
・SWOT分析を行ってオープンイノベーションプロジェクトの方針を決める
*Germeraad, Paul and Wim Vanhaverbeke [2016], "How to Find, Assess and Value Open Innovation Opportunities by Leveraging IP Databases?," les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society, LI(3), 154-166.
これらは専門的なスキルを必要とするため、オープンイノベーションチーム自身が実行するには荷が重い。企業としては知財法務部が実務を行うことになるだろう。一方で下記のようなサービスも出てきており、チームが窓口となって活用できる。
●VALUENEX(https://www.valuenex.com/jp/valuenex-radar):
類似特許の探索ツールなど特許情報を軸に、さまざまなテキストデータを扱うコンサルティングを提供している
●アスタミューゼ(https://www.astamuse.co.jp/service/):
技術/知財データに加えて、ベンチャー企業/研究テーマ/商品サービスアイデアに関する投資額データを組み合わせたコンサルティングを提供している
コラム:オンライン特許市場
オープンイノベーション活動を推進していると、未使用特許を有効活用したいという相談が出てくる場合がある。これはインサイドアウト型の活動の一種であるが、一般的には難易度が高く、成果が出にくい取り組みである。そもそも使用していないということは、自社が有効活用できるビジネスモデルを生み出せなかったということであり、そのようなものを欲しがる企業を探すのは困難である。
関連する話として、研究開発に関わる人であれば誰しも、特許売買のプラットフォームの可能性を考えたことがあるかもしれない。これに関してオンライン特許市場を20年間運用してきた仲介業者のyet2.comが振り返りを行った記事がある。
●1999年にyet2.comが大企業を顧客としたオンライン特許市場を立ち上げた
●数年間は登録数・マッチング数が着実に増加し、有名企業の取引も拡大していった
●より持続的なビジネスモデルにピボットして、2019年にオンライン特許市場から撤退した
●立ち上げ時に存在した30社の競合サービスは、いずれも現時点で存続していない
●過去20年間に毎年1~2社の市場が生まれたが、どれも成功しなかった
●市場の運営から得た学びは以下の通り:
・買い手の交渉力がはるかに強い
・大企業が売ろうとする技術は面白みがない
・スタートアップ企業の代理は継続して儲からない
・特許売買ではデジタルの強みが活かせない
・成功報酬に基づいたアプローチには持続性がない
*Marcus Widell [2021], Why Online IP Marketplaces Fail, https://www.yet2.com/why-online-ip-marketplaces-fail/.
結局のところ、シーズ起点の取り組みは難しいということではないだろうか。アウトサイドイン型のオープンイノベーション活動のほうが容易であるし、オープンイノベーションチームの判断で社外の情報を集めてくるよりも、探索ニーズの収集から始めるほうが効率的に業務を行える。新規事業開発ではソリューションではなく顧客から検討を始めることが推奨されているが、ニーズ起点であるところが共通している。
著者プロフィール
羽山 友治
スイス・ビジネス・ハブ 投資促進部 イノベーション・アドバイザー
2008年 チューリヒ大学 有機化学研究科 博士課程修了。複数の日系/外資系化学メーカーでの研究/製品開発に加えて、オープンイノベーション仲介業者における技術探索活動や一般消費財メーカーでのオープンイノベーション活動に従事。戦略策定者・現場担当者・仲介業者それぞれの立場からオープンイノベーション活動に携わった経験を持つ。NEDO SSAフェロー。
https://www.s-ge.com/ja/article/niyusu/openinnovationhayama2022
※次回は9月4日掲載予定です
1 2