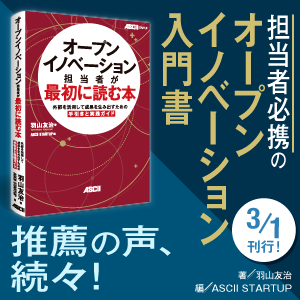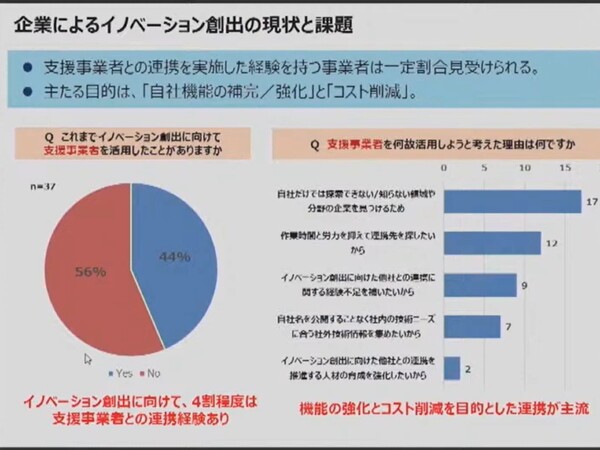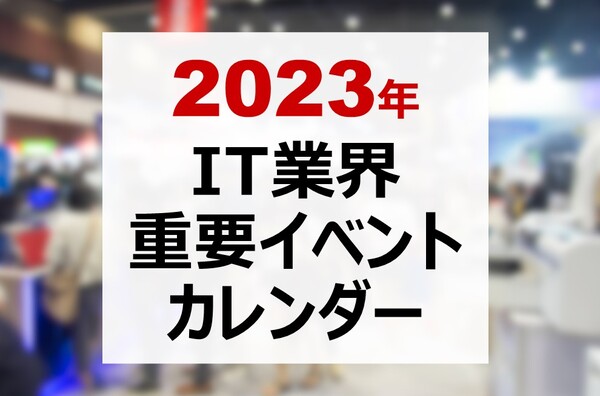コーポレートベンチャリング:ベンチャー・スタートアップ企業に限定したオープンイノベーション活動の要点
コーポレートベンチャリングの共同実施
2023年のIESEの報告によると、コーポレートベンチャリングを目的として少数の企業グループが形成されるようになってきており、コーポレートベンチャリングスクワッド(CVS)と名付けられている。またその特徴および企業が参加の是非を検討する際に評価すべきポイントを明らかにするため、さまざまな業界における西ヨーロッパ・南北アメリカ・中東・アジア太平洋の大企業に対してインタビューした結果を紹介している。
●CVSは活動の段階と協業の頻度で6種類に分類できる:
・スカウティングフォース(探索:単発)
協業案件を収集する単発の取り組み
・スカウティングプラットフォーム(探索:繰り返し)
スカウティング活動の繰り返し
・共同PoC(検証:単発)
製品/サービスの開発を目的としたスタートアップ企業との単発の協業
・パートナーシップ(検証:繰り返し)
メンバー企業とスタートアップ企業の間のPoCの繰り返し
・共同投資(投資:単発)
スタートアップ企業に対する1回限りの投資
・共同ファンド(投資:繰り返し)
スタートアップ企業に対する複数回の投資
●多くのCVSが以下の3つの役割を有していることが明らかになった:
・問題提供者
解決策を必要とする問題を提供する
・イネーブラー
メンバー企業とスタートアップ企業の協業を促進する
・アライアンスマネージャー
メンバー企業の間の関係性を取り持つ
●CVSに参加するベネフィットは以下の通り:
・より多くより質の高い協業の機会の獲得
・イノベーションエコシステムにおけるネットワークの拡大と地位の向上
・ベストプラクティスの学習と共有
・信頼性と評判の向上
・リスクとコストの低減
●CVSの課題は以下の2つに分けられる:
・ガバナンス面
目的の決定・意思決定プロセスの立案・ベネフィットの分配・知的財産権への配慮など設立時に発生するもの
・オペレーション面
リソース不足など日々の事業活動の中で発生する摩擦に関するもの
●適切なCVSの類型を活用することで、企業は単独でコーポレートベンチャリングを行うよりも、ベンチャー・スタートアップ企業に対してより強力な価値提案を示せるようになる
*Prats, Mª Julia, Josemaria Siota, Carla Bustamante and Beatriz Camacho [2023], Open Innovation - Corporate Venturing Squads: Teaming Up with Other Corporations to Better Innovate with Start-Ups, IESE.
ベンチャー・スタートアップ企業の立場で見た場合、複数の企業が集まっているほうが、自社の製品やサービスに合ったニーズが見つかる可能性が高くなる。これはコーポレートベンチャリングに限らず、例えば大学の研究者や中小企業を対象としたオープンイノベーションコンテストにおいても同じである。そのため今後はオープンイノベーション活動全般においても、大企業間の連携が進んでいく可能性がある。
一方で競合他社となる企業との取り組みは、社内を説得することが難しいかもしれない。そこで化学メーカーがその顧客である一般消費財メーカーと垂直的に連携したり、新薬を開発している医薬品メーカーとサプリメントを開発している食品メーカーが分野を越えて協力したりする取り組みはどうだろうか。どちらの場合も求めるシーズの棲み分けができることから、ガバナンス面の問題が生じにくく、着手しやすいと思われる。
1対1の協業がオープンイノベーション1.0、多様な組織が参加するエコシステムなどの多対多の関係性がオープンイノベーション2.0と呼ばれるなら、少数の大企業が連携して協業パートナーを求める試みはオープンイノベーション1.5と名付けられる。1.0から一足飛びに2.0に向かうことが難しい場合は、この種の取り組みで経験を積んでいくことが有効かもしれない。
大企業がベンチャー企業と協業する際のポイント
ベンチャー企業と協業する際の作法や心構えといったことに関しては、さまざまなところで話題になっているため、深くは立ち入らない。代表的なところでは経済産業省や特許庁が、大企業のコーポレートベンチャリング担当者に向けた「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き(第三版)」や「事業会社とスタートアップのオープンイノベーション促進のためのマナーブック」を取りまとめている。
また多くの企業がコーポレートベンチャリングに取り組んでいるため、とりわけ競合他社と差別化する方法について考えておく必要がある。メンタリングに関しては業界の知識ならベンチャー企業のほうが勝っている可能性もあるし、資金提供はベンチャーキャピタルや公的機関から調達できる金額に比べて見劣りするかもしれない。よって自社に特有のデータの提供など、できる限り独自性のある資産を見つけておきたい。
著者プロフィール
羽山 友治
スイス・ビジネス・ハブ 投資促進部 イノベーション・アドバイザー
2008年 チューリヒ大学 有機化学研究科 博士課程修了。複数の日系/外資系化学メーカーでの研究/製品開発に加えて、オープンイノベーション仲介業者における技術探索活動や一般消費財メーカーでのオープンイノベーション活動に従事。戦略策定者・現場担当者・仲介業者それぞれの立場からオープンイノベーション活動に携わった経験を持つ。NEDO SSAフェロー。
https://www.s-ge.com/ja/article/niyusu/openinnovationhayama2022
※次回は8月14日掲載予定です